現代の採用活動において、ChatGPT は企業の人事担当者にも注目される存在です。
対話型の生成AIであるChatGPTを上手に使えば、求人原稿の作成から応募者対応まで様々な業務を効率化できると期待されています。
本記事では 「ChatGPT 採用活動」 をテーマに、ChatGPTの基本と特徴、採用業務での具体的な活用例7選、メリット・デメリット、注意点、効果的な使い方のポイント、さらに関連サービスやよくある質問まで網羅的に解説します。
競合サイト以上に深掘りした情報を提供しますので、採用担当者の方はぜひ参考にしてください。
ChatGPTとは
ChatGPT(チャットジーピーティー)とは、アメリカのOpenAI社が開発した大規模言語モデル(Large Language Model)を用いた最新の対話型AIサービスです。
人間のように自然な文章で会話できる点が特徴で、ユーザーからの質問に対して的確な回答や提案を生成します。
例えば質問に答えたり文章を作成したり、翻訳したりといった幅広いタスクに対応可能で、その知識は学習した大量のテキストデータに基づいて提供されます。
ChatGPTの主な特徴
ChatGPTの主な特徴として、以下の点が挙げられます。
| ChatGPTの主な特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 大量データから学習した高度な言語能力 | 文法や文脈を理解し、自然な文章を生成できます。雑談から専門的な質問まで柔軟に対応可能です。 |
| 対話を通じた自己改良 | やり取りを通じて回答を調整できますが、リアルタイム学習はしません。プロンプトの工夫で徐々に精度を高められます。 |
| 最新モデルへのアップデート | 2023年3月登場の「GPT-4」は、回答精度や対応範囲が向上し、創造的な文章やコード生成も得意です。 |
| 誤情報のリスク | ChatGPTは優秀ですが、誤った回答(「幻覚」)をすることがあります。学習データ依存のため、最新情報には対応できない場合もあります。 |
ChatGPTで実現できること
ChatGPTは汎用性が高く、工夫次第で様々な業務に活用できます
| 実現可能な主なユースケース | 詳細 |
|---|---|
| 文章の要約 | 長文の記事やレポートの重要ポイントを抽出し、簡潔に要約できます。膨大な資料を読む時間がなくても、短時間で内容を把握できるのが特徴です。 |
| アイデア出し(ブレインストーミング) | 新規企画や問題解決で行き詰まった時、ChatGPTに質問すると新しい視点や提案が得られます。例えば「○○の改善策を5つ提案して」と指示すれば、幅広いアイデアを提供してくれます。 |
| 問い合わせ対応やFAQ作成 | ChatGPTは質疑応答が得意で、FAQ作成やチャットボットによる自動回答に利用できます。深夜や週末も自動で対応でき、24時間体制でカスタマーサポートの初期対応が可能です。 |
| 文章の生成・翻訳 | ChatGPTは指定したテーマで文章を作成したり、テキストを翻訳できます。例えば、求人票の英訳も短時間で対応可能です。多言語対応が強みです。 |
それでは、本題である採用活動での具体的な活用方法を見ていきましょう。
ChatGPTを会社の採用活動で使う7つの具体例
ChatGPTを人材採用の現場で活用することで、どのような業務効率化や効果が期待できるでしょうか。
ここでは、企業の採用担当者がChatGPTを使って実践できる具体的な活用例を7つ紹介します。
それぞれの場面でChatGPTがどのように役立つのか、ポイントと併せて見ていきましょう。
1. 求人広告の作成
魅力的な求人広告(求人票や募集要項)を作成するには、媒体ごとのフォーマットやターゲット人材に合わせた表現を考える必要があり、大きな労力がかかります。
ChatGPTを活用すれば、必要事項を入力するだけで求人原稿のたたき台を素早く生成できます。
例えば自社の事業内容・募集職種・求めるスキルや待遇などをプロンプトで伝えると、それらを盛り込んだ文章を自動で作成してくれます。
ChatGPTが出力した原稿は下書きとして使い、細かなニュアンスや社風のアピールポイントは人間が加筆修正すると良いでしょう(※「生成された文章をそのまま使用しない」ことは後述の注意点で解説します)。
また、ChatGPTはキャッチコピーのアイデア出しや原稿の言い回しの調整にも役立ちます。
例えば「〇〇な魅力を強調したタイトル案を3つ出して」といった指示で複数の見出し案を提案してもらい、その中からベストなものを選ぶといった使い方も可能です。
さらに、多言語で求人を出す場合には英訳・中訳の下書きを生成させることで多言語求人対応も効率化できます。
2. スカウトメールの自動作成
昨今はダイレクトリクルーティングでこちらから候補者にアプローチする「スカウトメール」が普及していますが、一人ひとりに合わせた内容を作るのは手間がかかります。ChatGPTはこのスカウトメール作成にも非常に有効です。
テンプレートとなる文章の下地を作り、そこに候補者固有の情報(経歴やスキルセット、共感しそうなポイント等)を反映させたメール文面を自動生成できます。
例えば、候補者の職種や実績など属性情報を入力すれば、該当人物にマッチした熱意あるスカウトメール案を作成してくれます。
もちろん細かな調整や個別のカスタマイズは最後に必要ですが、叩き台があるだけでも大幅な時短になります。
件名(タイトル)についてもChatGPTに候補を出してもらえば、開封率が高まりそうな魅力的なタイトルを見つける助けになるでしょう。
ChatGPTの活用により、多くの候補者に対して素早く質の高いスカウトメールを送れるようになり、結果的にアプローチ数や返信率の向上が期待できます。
3. 求人広告や採用イベントのタイトル作成
採用活動では、求人広告のタイトルや採用イベントの名前・告知タイトルなど、「ひと目で引き付ける見出し」の重要性が高いです。
ChatGPTはそうしたタイトル案の作成にも力を発揮します。
例えば「新卒向け会社説明会のタイトル案を5つ提案してください」と指示すれば、趣向の異なる複数のタイトル候補が得られます。
自分一人で考えると発想が凝り固まりがちですが、ChatGPTをブレーンストーミングの相手にすることで発想の選択肢を広げることができます。
ChatGPTに「〇〇職募集のスカウトメール用件名を10案ください」といった具合に頼めば、「【社名】×エンジニア募集!○○な方を探しています」など様々な切り口の件名が提案されます。
その中から自社の雰囲気や求める人物像に合ったものを選び、人事担当者は受信者の心に響くフレーズのブラッシュアップに専念できるというわけです。
このようにChatGPTを活用すれば、求人タイトルやイベント名決めの作業効率が上がり、より魅力的な表現を追求しやすくなるでしょう。
4. 面接時の質問のアイデア作成
採用面接では、短い時間で候補者の適性や熱意を見極めるために質問内容の工夫が欠かせません。
ChatGPTは職種や求めるスキルに応じて、効果的な面接質問のアイデア出しにも使えます。
例えば「営業職の中途採用面接で聞くべき質問を5つ考えてください。
応募者の本音を引き出せる内容で。」と指示すると、候補者の志向や価値観を確認できる深い質問や、業務への適合度を探る質問などを提案してくれます。
実際、ChatGPTに対して「〇〇職の面接で聞くべき質問を〇個挙げて」と依頼すれば、指定した個数分の質問リストが得られます。
例えばエンジニア職であれば「これまでに直面した最大の技術的課題とそれをどう克服したか教えてください」といった具合に、具体的で答え甲斐のある質問例が生成されます。
これにより、面接官が一人で考えるよりも網羅的で質の高い質問集を短時間で準備でき、面接の抜け漏れを防ぐことができます。
さらに、ChatGPTの提案した質問をベースに自社流にアレンジすれば、候補者に自社への志望動機やカルチャーフィットをより深掘りする質問へと発展させることも可能です。
5. 書類選考の評価基準の策定
履歴書・職務経歴書やエントリーシートの書類選考において、公平かつ一貫性のある評価基準を設けることは重要です。
しかしゼロから評価項目を洗い出すのは容易ではありません。
そこでChatGPTを使って一般的な書類選考の評価基準を尋ねれば、過去の蓄積データに基づいた標準的な評価項目のリストを提示してくれます。
例えば「新卒採用の履歴書を評価する基準を教えてください」と質問すると、「学業成績」「学生時代の活動実績」「志望動機の一貫性」「コミュニケーション能力」といった項目が例示されるイメージです。
自社の採用方針に合わせてそれらを取捨選択・カスタマイズすれば、自社なりの評価基準が短時間で策定できます。
また、ChatGPTに応募者の志望動機文などを入力し、評価基準に照らした分析・比較をさせるといった応用も可能です。
ChatGPTの活用によって、客観的で明確な書類選考基準を作成しやすくなり、選考のばらつきを減らす一助となるでしょう。
6. 理想の候補者像(ペルソナ)を明確に
採用成功のカギの一つに「どんな人材を求めているか」を明確にすることがあります。
そこで有効なのが採用ペルソナの策定です。
ChatGPTは理想の候補者像を描く作業にも活用できます。
自社の事業内容や採用ニーズ、現在抱えている課題などを詳しくChatGPTに説明した上で「当社にマッチする理想の営業職人材のペルソナを作成してください」と依頼すると、年齢層・スキル・性格・価値観・経験など盛り込んだ詳細な人物像を提案してくれます。
例えば「ベンチャー企業で即戦力となる営業職」を想定した場合、「20代後半~30代前半でIT業界の営業経験5年以上。新規開拓に強く、変化を楽しめるチャレンジ精神旺盛な性格。
チームプレーを重視しリーダー経験あり…」といった具合に、具体的なペルソナ例が得られるでしょう。
ChatGPTが提示した人物像を叩き台に、人事担当者や現場社員の意見を加えてブラッシュアップすれば、短時間で社内合意の取れた理想人材像を共有できます。
ペルソナが明確になることで、面接官ごとの評価基準のブレを防ぎ、一貫性のある選考が可能になります。
7. 多言語の翻訳
グローバル採用や外国籍人材の応募対応など、多言語コミュニケーションの場面でもChatGPTは力を発揮します。
例えば日本語で作成した求人票を英語や中国語に翻訳する場合、ChatGPTに原文を与えて「英文に翻訳してください」「中国語に翻訳してください」と指示すれば、瞬時にそれぞれの言語の文章を生成してくれます。
専門の翻訳者に依頼する前のドラフト作成として使えばスピードアップになりますし、予算削減にも寄与します。
また、海外からの応募者とのやり取りメールを英文で書くのが苦手な場合にも、ChatGPTが下書きを作成する支援をしてくれます。
「応募いただきありがとうございます。一次面接の日程調整のお願い」といったビジネスメールを英訳させたり、候補者からの英文メールを和訳させたりすることで、言語の壁を低くできます。
こうした多言語対応力もChatGPTの強みであり、国際的な人材獲得競争において大いに役立つでしょう。
ただし、最終的なニュアンスの確認や誤訳チェックは人間が行うようにし、重要なコミュニケーションはプロの翻訳やネイティブによるレビューを経るのが安心です。
ChatGPTを使った採用のメリット
次に、ChatGPTを採用プロセスに取り入れることで得られる主なメリットを3つ紹介します。
効率化からコスト面まで、企業の採用担当者に嬉しい効果が期待できます。
採用業務の効率化
ChatGPT最大の強みは業務処理のスピードと効率化にあります。
人間が何時間もかけて行う作業でも、ChatGPTなら短時間でこなせる場合があります。
例えば、膨大な応募書類に目を通して候補者をピックアップする作業は、人事にとって負担の大きい仕事です。
ChatGPTに条件を与えて履歴書の要点をまとめさせたり、自動でスクリーニングさせたりすることで、書類選考の自動化すら実現可能です。
また、よくある問い合わせへの回答生成や日程調整メールのドラフト作成など、これまで手作業で行っていた事務的業務もChatGPTが代替できます。
こうして単純作業に費やす時間を大幅に削減できれば、採用担当者はより戦略的な業務—例えば採用ブランディングや面接での見極め、内定者フォローといった人間にしかできない部分に集中できるようになります。
24時間稼働できるAIですので、人手が足りない時間帯の候補者対応なども可能です。
総じて、ChatGPTの活用は採用プロセス全体のスピードアップと人的リソースの有効活用に繋がり、生産性向上のメリットが得られるでしょう。
採用コストの削減
効率化と並んで無視できないのがコスト削減効果です。
人材採用には求人広告掲載費、人材紹介手数料、面接にかかる人件費など様々なコストが発生しますが、ChatGPTの導入によって一部コストの圧縮が期待できます。
例えば、これまで外部のコピーライターに依頼していた求人原稿の作成をChatGPTで代替できれば、その分の費用が浮くでしょう。
また、採用担当者が深夜残業して対応していた候補者からのメール返信をChatGPTで自動化すれば、残業代削減や人件費の抑制にもつながります。
さらには、初期段階の書類選考をAIに任せて効率化することで、採用にかかる時間当たりのコストを下げることも可能です。
ChatGPT自体は基本無料で使えますし、有料版(ChatGPT Plus)も月20ドル程度と比較的安価です。
もちろんChatGPTの活用にあたって新たなシステム導入や教育コストが発生する場合もありますが、それを差し引いても全体最適でコスト減につながるケースが多いでしょう。
採用コストを圧縮できれば、その分を従業員の育成や福利厚生に回すこともでき、企業経営的にもプラスです。
客観的な判断が可能
人間の判断にはどうしても主観や感情が入り込みますが、ChatGPTを上手に使えば採用シーンにおいてより客観的な判断材料を得ることができます。
例えば前述の「書類選考の評価基準策定」でChatGPTが提示した基準は、広範なデータに裏打ちされた汎用的なものです。
これをもとに選考を行えば、面接官個々の経験や勘に頼るよりも一貫した評価がしやすくなります。
また、ChatGPT自体には人間のような好き嫌いの感情はありません。
例えば学歴や性別にとらわれず、スキルや経験内容だけで初期スクリーニングさせるといった使い方をすれば、公平性の向上につながるでしょう。
さらに、複数の候補者プロフィールをChatGPTに要約させて客観比較することで、定量評価では見えにくい違いを浮かび上がらせることもできます。
もちろんAIにも学習データ由来のバイアスが存在する可能性は指摘されていますが、少なくとも判断基準を透明化できる点は利点です。
ChatGPTに「なぜその提案をしたのか」を尋ねれば理由を答えさせることもできます。
総じて、ChatGPTは採用担当者の意思決定を支援し、より客観的で納得感のある判断プロセスを築く一助となるでしょう。
ChatGPTを使った採用のデメリット
便利なChatGPTにも留意すべきデメリットやリスクがあります。
ここでは採用業務でChatGPTを活用する際に注意したいポイントを3つ解説します。
必ずしも正しい情報ではない
ChatGPTの回答は一見もっともらしく見えても、その内容の正確性は保証されていません。
たとえば求人市場の最新動向について尋ねた場合でも、学習データに古い情報しかなければ的外れな回答をする可能性があります。
実際に2024年時点のGPT-4モデルでも、学習データの範囲は2023年4月頃までに限られており、それ以降の出来事は知らないと公表されています。
さらに厄介なのは、ChatGPTが自信ありげに誤った回答(幻覚)をする場合です。
こちらが気付かずにそのまま内容を信用すると、間違った情報に基づいて候補者に連絡したり社内意思決定をしたりするリスクがあります。
また、生成された文章に第三者の著作物からの引用が混ざってしまうケースや、不適切な表現が紛れ込む可能性もゼロではありません。
そのため、ChatGPTから得られた回答や文章案は必ず人間の目で検証・校正する必要があります。
特に応募者向けの案内メールや求人内容などは、事実と異なる記載がないか、誤解を招く表現になっていないか十分確認しましょう。
ChatGPTはあくまで参考や補助として活用し、最終判断や責任は人間が負う姿勢が重要です。
情報漏洩のリスクがある
ChatGPTを業務で使う際に最も注意すべきは機密情報の取り扱いです。
ChatGPTに入力した内容は外部のサーバー(OpenAIのサーバー)に送信され、サービス向上のため学習に利用される可能性があります。
そのため、例えば応募者の個人情報や社内の秘密情報をうっかり入力してしまうと、それが第三者に漏洩してしまうリスクがあります。
実際に韓国のサムスン電子では、社員が業務上の機密データをChatGPTに入力した結果、その情報が外部に流出して問題になった事例があります。
また、米大手銀行のJPモルガンやアップルなども社内機密保護の観点から社員のChatGPT利用を禁止・制限する動きが報じられています。
このように情報漏えいの懸念は現実のものとなっており、特に個人データや企業戦略に関わる内容は絶対にそのまま入力すべきではありません。
対策としては、ChatGPTには公開して問題ない一般情報や匿名化したデータのみを入力する、あるいは社内に導入したセキュリティ強化版のAIツール(オンプレミス型の大規模言語モデルなど)を活用することが挙げられます。
応募者への情報提供が不十分になることがある
ChatGPTに頼りすぎることで、候補者へのコミュニケーションが画一的・機械的になる恐れもあります。
例えば、求人情報や選考案内文をChatGPTが生成したテンプレート文で済ませてしまうと、細かなニュアンスや企業独自の魅力が十分に伝わらない可能性があります。
応募者からの問い合わせに対してChatGPTが回答するような場合でも、質問の内容によっては的確に答えきれず不十分な情報提供に終わってしまうことも考えられます。
また、ChatGPTの回答はあくまで与えられた情報に依存するため、自社に関する公開情報が少ない場合は中身の薄い返答になりがちです。
その結果、候補者にとって必要な情報(会社のカルチャーや具体的な業務内容など)が十分伝わらず、ミスマッチを招いてしまうリスクもあります。
実際のところChatGPTが生成した文章か人間が書いたものか区別はつきにくいですが、機械的な定型文ばかりだと受け手に違和感を与えるかもしれません。
以上のように、ChatGPT任せにしすぎることで候補者体験の質が下がる恐れがある点には注意しましょう。
対策として、AIの出力内容には必ず人間の目を通し必要に応じて肉付けする、人間味や企業らしさを感じられる表現を盛り込む、といった工夫が欠かせません。
ChatGPTは便利ですが、あくまで補助ツールであり、最終的な候補者対応の品質は人事担当者がコントロールするという意識を持つことが重要です。
ChatGPTでの採用活動で注意すること
上記デメリットも踏まえ、採用業務でChatGPTを活用する際に押さえておきたい注意点やルールをまとめます。
以下のポイントに気を付ければ、リスクを低減しつつChatGPTを有効活用できるでしょう。
個人情報の取り扱いに細心の注意を払う
前述の通り、ChatGPTに入力したデータは外部に送信されます。
応募者の氏名・連絡先・履歴書の詳細など個人情報や、社内の機密事項は絶対にそのまま入力しないよう徹底しましょう。
どうしてもAIに解析させたい場合は、匿名化・要約するなど直接個人を特定できない形に加工する工夫が必要です。
例えば履歴書の内容を評価してほしい場合、「25歳・営業職・IT業界経験3年・実績◯◯」といった抽象化した情報だけを渡すようにします。
また、利用規約や法令を守ることは大前提です。ChatGPTの利用がプライバシー侵害や第三者への提供扱いとならないように、社内規程を定め社員に共有することも大切です。
大手企業ではすでに社としてChatGPT利用禁止の例もありますが、そこまで厳格にせずとも、「機密事項はAIに入力しない」という共通認識だけは必ず持つようにしてください。
生成された文章をそのまま使用しない
ChatGPTから得られた回答や文章案は、鵜呑みにせず必ずチェックしてから使うようにしましょう。
AIが書いた文章は一見自然ですが、前述のように事実誤認や不適切な表現が含まれる可能性があります。
そのままコピー&ペーストで社外に送ったり公開したりするのはリスクが高いです。
したがって、ChatGPTが作成した求人票やメール文面は下書き・素案と位置付け、人事担当者が内容を精査した上で自社の伝えたいメッセージに沿うよう修正を加えるのが理想です。
特に応募者とのコミュニケーション文章では、少しの言い回しで印象が変わります。
機械的な文章になっていないか、人間らしい温かみや会社の個性が感じられるか、といった観点でも見直してみましょう。
また、他社のウェブサイトから収集された情報がAI回答に混ざっているケースも考えられるため、著作権侵害などにも注意が必要です。
最終的な文章は自分の言葉で書き直すくらいの気持ちでいると安心です。
ChatGPTはあくまでアシスタントであり、最終アウトプットの責任は自分にあることを忘れないようにしましょう。
適切な情報を提供しないと精度が低下する
ChatGPTの性能を十分に発揮させるには、ユーザー側からの入力(プロンプト)が極めて重要です。
曖昧な指示しか与えないと、当然ながら返ってくる回答も漠然としたものになります。
逆に必要な情報を具体的に与えれば、その文脈を考慮した精度の高い応答が得られます。
例えば「良いエンジニアを採用するにはどうすればいい?」と尋ねるよりも、「当社は従業員50名のスタートアップ企業。初のデータサイエンティスト採用に挑戦中。
知名度が低く応募が集まらない状況。
限られたリソースで優秀な人材を採用するための施策を3つ提案してください。」といった具体的な情報を盛り込んだ方が、実情に即した実用的な提案が返ってきやすくなります。
このように、ChatGPTにこちらの意図を正しく理解させるための情報提供を惜しまないようにしましょう。
忙しいとつい一文で雑に聞いてしまいがちですが、最終的には丁寧に入力した方が時短にもつながります。
なお、一度で満足いく回答が得られなくても追加で「○○の観点でもっと具体的に説明してください」「△△の場合はどうなりますか?」と質問を重ねることで精度を高めることも可能です。
ChatGPTに固執しすぎない
便利なChatGPTですが、万能ではないことを常に肝に銘じておきましょう。
あくまで人間の能力を補助するツールであり、採用業務すべてを任せられるわけではありません。
ChatGPTにできること・できないことを見極め、使うべきところでは使い、そうでない部分は従来通り人間が担うというバランス感が大切です。
例えば、最終面接での評価や内定者フォローなど、人間同士の信頼関係構築が必要なフェーズはAIに代替できません。
また、ChatGPTの回答がどうも要領を得ない場合は、それ以上深追いするより自分で考えた方が早いこともあります。「魔法の箱」扱いせず過信しないことが重要です。
特に採用のように人に関わる領域では、AIの提案は参考程度にとどめ、最終判断は経験豊富な人事や現場責任者が下すべきでしょう。
さらに、ChatGPTばかりに頼っていると自らのスキル向上の機会を失う側面もあります。
要は「ほどほどに付き合う」のがコツです。
ChatGPTを採用担当者の強力な相棒とはしつつも、主体性と人間らしさを忘れずに運用しましょう。
採用活動でChatGPTを効果的に活用するポイント
では実際にChatGPTを使うにあたり、より良い結果を引き出すためのテクニックや工夫を3つご紹介します。
ちょっとしたポイントを押さえるだけで、ChatGPTから得られるアウトプットの質が格段に向上します。
具体的な情報を入力する
先ほどの注意点でも触れましたが、プロンプト(入力文)の具体性が質の高い回答を得るカギです。
ChatGPTに何か依頼するときは、背景情報や求める回答の条件をできるだけ明示しましょう。
例えば求人票の作成をお願いするなら、「会社概要」「募集ポジション」「求める人物像」「アピールポイント」などを箇条書きで伝えた上で「以上を踏まえて求職者が魅力を感じる求人原稿を書いてください」のように依頼します。
こうすることで、ChatGPTは提供された情報を盛り込みながら的確な文章を構成してくれます。
また、出力してほしい形式を指定するのも有効です。
例えば「箇条書きで5つ挙げてください」「200文字程度で要約してください」と指示すれば、回答の体裁も整いやすくなります。
初回は抽象的な回答しか得られなくても、「では2番の点をもう少し具体的に説明してください」のように追加質問をすることで、より深掘りした内容を引き出すことも可能です。
このようにコミュニケーションを重ねて調整するイメージで、逐次ChatGPTにフィードバックを与えると精度が高まります。
繰り返し活用し精度を高める
ChatGPTとの付き合い方は、一度きりの使い捨てではなく継続利用で育てる感覚が大事です。
使えば使うほど自分がChatGPTへの指示のコツを掴めるようになりますし、ChatGPT側も対話の流れの中でこちらの意図を学習していきます。
例えば最初は大まかなアイデア出しをしてもらい、その回答に対して「もっと○○な方向で別の案もください」とお願いすると、より要望にマッチした追加案が出てくる、といった具合です。
こうして対話を重ねていくことで回答の多様性や精度が増すのがChatGPTの利点です。
一問一答で終わらせず、「ではこの案を具体的に実行するステップも教えて」といった風に切り口を変えた質問を投げかけるのも良いでしょう。
継続利用する中で、自分なりのChatGPT活用パターンや有効なプロンプトのテンプレートも蓄積されていきます。
そうなればしめたもので、もはやChatGPTは自分専用の優秀な部下 or アシスタントのように感じられるはずです。
日頃から業務の中にChatGPTを取り入れ、小さなことでも質問してみるクセをつけると、次第に使いこなせるようになるでしょう。
ChatGPTに適切な役割を持たせる
ChatGPTの出力内容をコントロールするテクニックとして有名なのが、ロールプレイ指示(役割の明示)です。
つまり「あなたは〇〇の専門家です」「〇〇の立場で考えて答えてください」とあらかじめChatGPTに役割を与える方法です。
これを行うことで、回答に専門的な視点や論調を反映させることができます。
例えば「あなたは採用コンサルタントです。〇〇の課題を解決する採用戦略を提案してください。」と指示すれば、専門家の口調で具体的かつ実践的なアドバイスが得られやすくなります。
他にも「優秀なコピーライターとして求人広告のキャッチコピーを考えて」とか「人事部長の視点で新卒研修計画を立ててください」といった具合に様々なロールプレイを試せます。
これはChatGPTが持つ知識の特定部分を強調して使う効果があり、回答の質を高めるのに有効です。
役割を指定することで回答のトーンや重点が変わるため、自社に足りない視点を補うことにもなります。
「自分一人では思いつかなかったけど、マーケティング目線だとこういうアプローチがあるのか」と新たな発見が得られることもあるでしょう。
ぜひChatGPTに様々な役を演じさせて、有効な示唆を引き出してください。
なお、役割を与える際も具体的に描写すると効果的です(例:「10年間の採用経験がある人事マネージャーとして…」など)。
ChatGPTと相性の良い採用サービス
ChatGPT単体でも採用業務の効率化に役立ちますが、他の採用関連サービスと組み合わせることで相乗効果を発揮するケースがあります。
ここではChatGPTとの親和性が高い主な採用サービスを4つピックアップし、それぞれどのように協働させると良いかを解説します。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングとは、求人を待つのではなく企業側からスカウトメール等で候補者に直接アプローチする採用手法です。
この分野では前述したようにChatGPTがスカウトメールの作成で非常に有効に機能します。
数多くの候補者に対して一人ひとり内容を変えたメールを送る場合でも、ChatGPTを使えばテンプレートをベースに各人の経歴に合わせた文面を自動生成できるため、大量送信時の労力を劇的に減らせます。
さらに、ChatGPTは自社で活躍する社員の共通点を分析し、そこから抽出したキーワードやスキルセットを基に「狙うべき候補者像」を言語化するのにも役立ちます。
たとえば「当社の優秀なエンジニア社員10名の経歴から共通点を見つけ、それに当てはまる人材の特徴を挙げてください」といった使い方です。
これによりスカウト対象者の精度を高めることができ、無闇なアプローチを減らして効率的な攻めの採用が可能になります。
適性検査
応募者の性格や能力の傾向を測る適性検査(筆記テストやWebテスト)も、ChatGPTと組み合わせることで新たな活用ができます。
具体的には、適性検査の結果データをChatGPTに要約・分析させて、採用判断の参考にするというものです。
例えば「この候補者の適性検査結果から読み取れる強みと課題を教えてください」と質問すれば、数値データから定性的な解釈を引き出すことができます。
また、複数候補者の結果をまとめてChatGPTに渡し、「自社で活躍しそうな順に並べて理由を説明してください」と依頼すれば、データに基づく一つの見解を提示してくれるでしょう。
ただし、ChatGPTの分析は万能ではないため専門サービスとの併用が推奨されます。
適性検査そのものはこれまで通り信頼できる外部ツールで実施し、ChatGPTはあくまで結果の解釈補助や説明資料作成に使うイメージです。
人材紹介サービス
人材紹介会社(エージェント)を利用して採用する場合、企業側はエージェントに提出する求人票(求人情報シート)を作成する必要があります。
ここでもChatGPTが役立ちます。
自社の事業内容・募集ポジション・求める経験スキルなどを入力すれば、フォーマットに沿った求人票のドラフトを素早く作成できます。
特に急な増員で早く採用を進めたい場合、ChatGPTでさっと求人票を作ってエージェント各社に展開できれば、準備に時間を取られずスピーディーに母集団形成に移れます。
また、エージェント経由の採用では複数のポジションを同時並行で進めることもありますが、ChatGPTを使えば各ポジションの求人票作成作業を並列処理的に進められます。
担当者の負荷軽減と時間短縮に寄与するでしょう。
求人広告媒体
自社で直接求人を出す場合、リクナビやマイナビなどの求人広告媒体に掲載する原稿を用意しなければなりません。
これもChatGPTの得意分野です。
募集職種や求める人物像、待遇など必要事項を入力すれば、それらを盛り込んだ募集要項文を簡単に作成できます。
媒体ごとの文字数制限やフォーマットにも注意しつつ、「○○文字以内で求人広告用の文章を作ってください」と指示すれば体裁を整えてくれるでしょう。
さらに、ChatGPTの言い回し調整能力を活かして、媒体の想定読者層に響く表現に最適化することも可能です。
例えば20代向けの転職サイト用なら「若い求職者に親しみやすいカジュアルな口調で書いてください」、ハイクラス求人なら「専門性と品位を感じさせる文体で」などと伝えることで、ターゲット層にマッチしたトーンのコンテンツが生成できます。
これにより応募者の興味を惹きつける魅力的な求人情報を発信でき、結果的に応募数の増加につながるでしょう。
以上、ChatGPTと相性の良いサービスを見てきました。
うまく組み合わせて、採用活動の質と効率を同時に高めていきましょう。
ChatGPTを活用する採用活動に関してよくある質問
最後に、ChatGPTの活用について採用担当者から寄せられることが多い疑問や不安点をQ&A形式でまとめました。
これらのポイントを理解しておけば、安心してChatGPTを使いこなすことができるはずです。
Q1. ChatGPTは営利目的で使えますか?
A. はい、ChatGPTは営利目的での利用が可能です。
OpenAIの提供するChatGPTは、利用規約の範囲内であれば商用利用が認められています。
実際、世界中の企業が業務効率化やサービス開発にChatGPTを活用していますし、日本国内でも多くの企業が自社の採用業務やマーケティングに取り入れ始めています。
ただし、商用利用時の注意点もいくつかあります。
まず、ChatGPTが生成したコンテンツの著作権や内容の責任は利用者側にあることを認識しましょう。
AIが出力した文章であっても、それを利用して発生した問題(誤情報や権利侵害など)は利用者が対処する必要があります。
また、OpenAIの規約では機密情報や個人情報の扱い、API利用時の制限事項などが定められていますので、ビジネスで本格的に活用する際は最新の利用規約を確認し順守することが大切です。
要するに、ChatGPTそのものは商用・非商用を問わず利用できますが、「使い方」によっては規約違反になる可能性があるので注意しましょう。
適切に使えばChatGPTは企業の強い味方となります。
実際に人事領域に限らず、カスタマーサポートへの導入や資料作成の自動化など、様々な営利目的に活用が広がっています。
ぜひ社内のガイドラインを整備した上で有効活用してください。
Q2. ChatGPTで禁止されている行為は?
A. OpenAIの利用規約で定められた違反行為があります。
| 主な禁止事項 | 詳細 |
|---|---|
| 違法行為への利用 | 犯罪の手助けや法律に反する目的での利用は禁止されています。例えば、ハッキングツールの作成や暴力的な計画の立案などは許可されていません。 |
| 有害なコンテンツの生成 | 児童虐待や差別、誹謗中傷などの内容の生成は禁止されています。これらのプロンプトにはChatGPTは回答しません。 |
| スパム・詐欺行為 | 無差別なスパムメールやフィッシング詐欺の文面作成、人を騙す用途は禁止です。また、偽情報の拡散や選挙工作など社会秩序を乱す行為も認められていません。 |
| プライバシー侵害 | 個人情報の違法な収集・開示は禁止です。他人の情報を勝手に調べたり、守秘義務のあるデータを公開することは避けてください。 |
| 専門分野での無責任な助言 | 医療・法律・金融など、専門家のチェックが必要な分野での助言は制限されています。「○○病の治療法を教えて」といった質問には注意文が表示されたり、回答が制限されたりします。 |
これらはOpenAIが定める利用ポリシーの一部ですが、要するに「悪用厳禁」ということです。
通常の範囲でビジネスに使う分にはまず問題ありませんが、明らかに倫理や法律に反する指示を出してもChatGPTは応じないようにできていますし、最悪アカウント停止の措置を取られる可能性もあります。
コンプライアンスを守って健全に活用している限り、特に恐れる必要はありません。
Q3. ChatGPTに対する質問の仕方のコツは?
A. 具体的に指示し、段階的に深掘りすることです。
前述の「効果的に活用するポイント」と重複しますが、ChatGPTから良い回答を引き出すにはプロンプト(質問文)の工夫が欠かせません。コツをいくつか挙げます。
| プロンプト(質問文)のコツ | 詳細 |
|---|---|
| 背景情報や前提条件を伝える | 「採用を成功させる方法は?」と聞くより、「未経験エンジニアを5名採用したいが応募が少ない。予算◯◯でできる施策は?」のように具体的な状況を伝えると、条件に合った現実的な回答が得られます。 |
| ChatGPTに役割を与える | 「あなたは経験10年の採用コンサルタントです」といった役割指定をすると、専門家の視点で回答してくれます。 |
| 具体的なアウトプット形式を指定 | 「3つのポイントに絞って提案してください」や「箇条書きで回答してください」といった形式や項目数を指定すると、読みやすく的確な回答が得られます。 |
| 段階的に質問を深める | 一度の質問で完璧な回答を求めず、まず大枠の答えをもらい、その後「では○○について詳しく教えて」と追加で尋ねると良いです。 |
| 曖昧さを避ける | 主語や聞きたいポイントが不明確だと誤解を招きます。「それ」や「あの件」など指示語だけではなく、質問ごとに必要な固有名詞や項目を明示しましょう。 |
例えば、良くない例:「あの候補者どう思う?」→良い例:「先日応募のあった○○さん(経歴△△)について、当社にマッチする点と懸念点を教えてください。」このように具体性を高めるだけで、ChatGPTの回答精度は格段に上がります。
Q4. ChatGPTで履歴書の志望動機を書いたらバレますか?
A. 工夫すればまずバレないでしょう。
求職者側の視点ですが、ChatGPTを使って志望動機や自己PR文を作成する人も増えてきました。
この場合、「企業の採用担当者に見抜かれるのでは?」と心配になるかもしれません。
しかし結論として、適切に使えばAIが書いたと見破るのは困難です。
ChatGPTが生成する文章は、その場で一から作られたオリジナル文です。
現状、人間の書いた文章かAIの書いた文章かを完璧に判定できるツールは存在しないと言われています(特に日本語では精度が低いです)。
従って、提出された志望動機文を見て採用担当者が「これはChatGPT産だな」と断定するのはまず不可能でしょう。
ただし、使い方によっては間接的にバレる可能性もあります。
例えばAIが書いた文章をそのまま使い、自分の実体験や熱意が全く込められていないと、面接で深掘りされた際に具体的に語れず不自然になる恐れがあります。
また、他の応募者と酷似したテンプレート的な表現ばかりだと違和感を持たれるかもしれません。
企業によっては試しにAI検出ツールにかけてみるところもあるようですが、信憑性は高くないので参考程度でしょう。
ポイントは、ChatGPTをあくまで補助として使い、自分の言葉で肉付けすることです。
実際の経験や志望理由を具体的に盛り込み、AIっぽさ(一般論だけで具体例がない、妙に整いすぎて個性がない等)を打ち消せば、見破られる心配はほとんどありません。
事実、現在の採用現場でも志望動機文がAI利用かどうかを判定する確実な方法はなく、採用担当者も深く追及はしないのが実状です。
むしろ文章の内容そのものより、面接での受け答えや仕事に対する熱意のほうが重視されます。
以上を踏まえると、ChatGPTで志望動機を書いて提出しても大丈夫か?という問いには「適切に使えばまず大丈夫」といえます。
ただし提出後はその内容に一貫性を持って語れるよう、しっかり自己分析しておくことをお勧めします。
採用担当者としては、仮にAI生成だと感じても即不合格とすることはなく、「この応募者は文章作成にAIを活用できる合理的な人だ」と前向きに捉えるケースもあるかもしれません。
まとめ
ChatGPTは採用担当者にとって強力な助っ人となり得るツールです。
求人文章の作成やアイデア出しなど煩雑な作業を効率化しつつ、客観的なデータ分析や24時間対応といった人間には難しい芸当もこなしてくれます。
日本ではまだ採用業務への本格導入例は多くありませんが、技術の進歩に伴い今後活用が進むと考えられます。
採用競争が激化し人事担当者の負担が増す中、ChatGPTの活用は業務効率化や精度向上に大きく貢献する可能性があります。
ただし、過度な期待は禁物です。
ChatGPTに完璧な回答を求めすぎないこと、そしてGoogleのような従来の検索エンジンとは異なるものだと理解することが重要です。
あくまで自らの判断をサポートしてくれる存在として上手に付き合うのがコツと言えます。



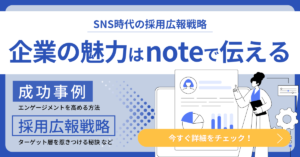
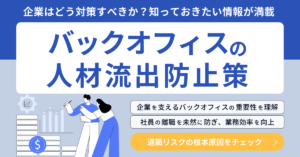
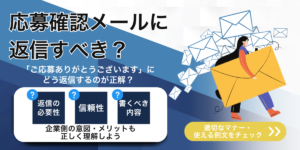
コメント