バックオフィス(経理・労務・総務など)の社員が突然退職してしまうと、企業運営に大きな支障をきたします。
本記事では、バックオフィス社員の重要性や退職理由、退職によるリスクとその対策、さらにバックオフィス業務の外注メリットまで幅広く解説します。
最新の統計データや事例を交え、退職リスクを未然に防ぐ具体策を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 企業を支えるバックオフィスの重要性
バックオフィスとは、企業の「縁の下の力持ち」として営業などフロント業務を支援する部門です。
直接収益を生む部署ではありませんが、バックオフィスがしっかり機能することでフロント部門が安心して業務に専念でき、安定した企業活動が実現します。
特に以下の職種はバックオフィスの代表例で、それぞれ企業運営に不可欠な役割と影響力を持っています。
経理
経理部門は企業の財務状況を正確に記録・管理し、資金の流れを見える化する役割を担います。
日々の入出金管理から決算業務まで、一連の経営管理に直結する重要業務です。
経理が適切に機能しないと、企業の資金繰りや財務健全性に悪影響が出るため、経理担当者は企業経営に必要不可欠な存在です。
労務
労務(人事労務)部門は、社員の雇用管理や給与計算、社会保険手続きなど従業員に関するサポート業務を担当します。
法令遵守の下で適切な労務管理を行うことで社員が安心して働ける環境を整備し、企業全体の生産性向上を陰から支えています。
総務
総務部門は会社全体の庶務・管理業務を担当し、他部署がスムーズに業務を進められる環境作りを行います。
具体的には備品管理や社内行事運営、設備維持管理など多岐にわたります。
総務がしっかり機能することで社内の円滑なコミュニケーションと業務環境が維持され、社員のモチベーション向上にもつながります。
バックオフィスの社員は企業運営の土台を支える要となる人材です。
その専門知識と経験は簡単に代替できるものではなく、各担当者の存在が企業の安定稼働に直結しています。
2. バックオフィス担当社員の退職する7つの理由
そんな重要なバックオフィス社員ですが、近年は転職市場の活発化もあり、短いサイクルでの退職も珍しくありません。
ここではバックオフィス社員が退職を決意する主な理由を7つ紹介します。
理由を理解することで効果的な退職防止策を講じるヒントになります。
1. 業務の多さによる疲労
バックオフィスは最小限の人数で業務を回す傾向が強く、一人ひとりの業務量が多くなりがちです。
常に残業続きで業務量が過重になると心身ともに疲弊し、「過度なプレッシャーやストレス」を感じて退職に至るケースもあります。
また、「忙しいのに十分に評価されない」という不満を抱え、モチベーション低下につながることもあります。
2. 人間関係における悩み
職場の人間関係の悩みは退職理由の中で非常に多いものの一つです。
バックオフィスは少人数で特定のメンバーと密に働くため、合わない人がいると逃げ場がなくストレスが蓄積しがちです。
実際、厚生労働省の調査でも「人間関係の悩み・不満」が退職理由となった割合は男性8.3%、女性10.4%にのぼります。
3. 評価や激務への不満
バックオフィス業務は成果が見えにくく、評価されにくい傾向があります。
どれだけ業務を効率的にこなしても「できて当たり前」と見なされ、十分な報酬や評価が得られないと感じる人も少なくありません。
特に責任感が強く真面目な人ほど、「自分の努力が正当に評価されていない」と感じると不満を募らせてしまいます。
激務にも関わらず評価や待遇が改善しない状況が続けば、優秀な人材ほど見切りをつけて退職を選択してしまうでしょう。
4. 作業が単調でやりがいがない
バックオフィス業務は月次・年次など決まったサイクルで同じ作業の繰り返しが多く、変化に乏しい面があります。
そのため、向上心のある人にとっては「成長や達成感が得られない」状態に陥りがちです。
特に意欲的な社員ほど現状維持に退屈し、「もっと刺激的で成長できる場」を求めてしまいます。
5. キャリアパスが見えない
現在の会社で将来的なキャリアアップの道筋が描けないことも、退職を考える大きな要因です。
長期間同じ役割のままでは将来に不安を感じ、「この会社で学ぶことはもうない」と悲観的になることがあります。
特にバックオフィスは昇進枠が限られていたり、管理職ポストが少ないケースも多いため、野心のある社員ほど社内に成長の機会を見出せず転職に踏み切りがちです。
「キャリアアップが見込めない」環境では優秀な人材ほど離職リスクが高まります。
6. ジョブローテーションの機会がない
中途採用や新卒でも、様々な部署を経験してスキルを広げたいと考える社員は多くいます。
しかしバックオフィス担当者は専門特化して配置されることが多く、他部署へのジョブローテーション機会が少ない傾向があります。
その結果、社内で新しい経験を積む場がなくマンネリ化し、「このままでは成長できない」と感じてしまいます。
異動や配置転換がない環境では視野が広がらず、キャリア停滞への不安から退職を選ぶ社員も出てきます。
7. 資格取得・スキルアップのため
自身のスキルアップを目的に退職するケースもあります。
例えば経理担当者が更なる専門資格(税理士や公認会計士など)の勉強に専念するために一度退職する場合です。
あるいは現在の会社では経験できない業務範囲を求めて、より規模の大きな企業や成長フェーズの異なる企業へ転職する例も見られます。
このように前向きな理由でバックオフィス社員が退職することもあり、会社としては引き止めが難しいケースと言えるでしょう。
3. バックオフィス社員が突然退職することでのリスク
バックオフィス担当者が予告なく辞めてしまうと、企業には様々なリスクと悪影響が生じます。
ここでは主なリスクを4つ取り上げます。日頃からこのようなリスクを認識し、備えておくことが重要です。
1. 経理業務がストップ・滞ってしまう
経理や労務など専門知識が必要な業務は、担当者以外では対応が難しい場合が多いです。
そのため一人が突然抜けると、給与計算や請求支払い、決算処理など重要業務が即座にストップしてしまいます。
引継ぎが不十分なままだと復旧までに時間がかかり、最悪の場合、納税や支払いの遅延といった法的トラブルに発展するリスクもあります。
2. 業務ブラックボックス化による負荷
バックオフィス業務は「売上に直接つながらないから」と最小人数で回しがちで、その人だけが仕事の内容を把握している状況(いわゆる業務の属人化)が起こりやすいです。
その担当者が抜けると残された社員には何をどう処理すれば良いか分からない「ブラックボックス化」となり、周囲に大きな負荷がかかります。
例えば経理処理の手順や各種契約の管理方法などが共有されていないと、他の社員は対応に苦慮し、通常業務まで滞る連鎖が起こりえます。
属人化した状態での突然の退職は、残された組織にとって非常に大きなリスクです。
3. 業務の引き継ぎ不足
担当者が急に辞めた場合、充分な業務引き継ぎが行われないまま退職日を迎えてしまうケースもあります。
資料やデータの所在、取引先とのやり取りの履歴、各種手続きの締切などが共有されていないと、後任者や周囲の社員は手探りで業務を進める羽目になります。
引き継ぎ不足によるミスや漏れが発生すれば、取引先からの信頼低下や社内混乱にもつながります。
4. 後任者の採用が難しい
専門性の高いバックオフィス人材は、市場でも慢性的に不足しており人材の補充が難しい傾向があります。
特に中小企業の場合、経理や労務の経験者を急募してもすぐに見つからないケースが珍しくありません。
採用できたとしても新任者の育成に時間がかかり、その間は他の社員が兼務で負担を強いられることになります。
結果として、既存社員に過重労働がのしかかりさらなる離職を招く悪循環に陥る恐れもあります。
後任不在の期間が長引けば、業務品質の低下やミスの増加といったリスクも高まります。
4. バックオフィス社員の突然の退職リスクへの6つの対策
以上のようなリスクを軽減するために、企業側で取れる具体的な対策を6つ紹介します。
日頃から備えを講じておくことで、万一退職者が出てもダメージを最小限に抑えられます。
1. 業務の仕組み化やマニュアルを作成する
業務フローを見える化し、マニュアル化しておくことは最重要対策の一つです。
手順書やチェックリストを整備することで、担当者以外でも業務を引き継ぎやすくなります
マニュアル化は退職リスクに備えるだけでなく、属人化の防止やチームによるバックオフィス業務の分担を可能にし、結果的に業務効率の改善にもつながります。
たとえば経理処理のマニュアルや労務手続きのガイドを用意し、定期的に更新しておけば、突然の担当交代でも業務継続がスムーズに行えるでしょう。
2. 働きやすい職場環境を整える
バックオフィス社員が過度なストレスを感じず長く働ける環境づくりも退職防止には欠かせません。
具体的には適切な人員配置で一人に業務が集中しないようにしたり、残業を減らす業務改善を行ったりします。
加えて、日頃から上司や同僚とのコミュニケーションを円滑にし、相談や意見を言いやすい職場風土を育むことも重要です。
定期的に1on1ミーティングやキャリア面談を実施し、社員の悩みや要望を早期に把握・対処する仕組みを作りましょう。
3. 複数の担当者で経理業務を行う
経理・労務など一人の担当者に頼り切りになっている場合、チーム体制への移行を検討します。
可能であれば2名以上で業務を分担し、お互いの仕事を把握しておく仕組みを作りましょう。
たとえば振込業務はダブルチェック体制にし、月次決算も複数人でクロスチェックするようにすると、一人抜けても残ったメンバーで対応できます。
人員に余裕がない場合でも、他部署から定期的に応援をもらい業務を共有化する工夫も有効です。
複数担当制にすることで属人化を防ぎ、急な退職時も業務が止まらない体制を構築できます。
4. 定期的なチェックとフィードバックをする
バックオフィス社員に対して、上司が定期的に業務状況をチェックしフィードバックを行うことも大切です。
仕事量や負担が偏っていないか、困っていることはないかなどを確認し、早めに対処すれば不満の蓄積を防げます。
加えて成果や貢献をきちんと評価し、感謝や称賛のフィードバックを伝えることでモチベーションアップにつなげましょう。
評価制度が不透明だと感じさせないために、バックオフィスの成果を見える化して表彰する仕組みを取り入れる企業もあります。
定期的なコミュニケーションとフィードバックによって社員の不安や不満を解消し、退職したい気持ちを未然に防ぐことが可能です。
5. 引継ぎ事項をまとめておく
日頃から引継ぎ資料や業務引継ぎノートを作成し更新しておくことも有効です。
担当業務の進捗状況、毎月・毎年の重要スケジュール、取引先や関係各所の連絡先、使用している帳票類やシステムのログイン情報など、いざという時に必要となる情報を一覧化しておきます。
こうした引継ぎ事項のドキュメントを用意し定期的に整理しておけば、突然の退職時でも新任者への情報共有がスピーディーに行えます。
「見える化ボード」や共有フォルダに最新情報をストックする運用を取り入れ、誰でもアクセスできる状態にしておくと安心です。
6. 経理代行サービスの導入を検討する
人手不足が深刻な場合や専門知識を補完したい場合、バックオフィス代行サービス(アウトソーシング)の活用も有力な対策です。
経理や労務のプロフェッショナルに一部業務を委託することで、担当者の負担を減らし退職リスクを軽減できます。
実際に代行サービスを併用すると、一人ひとりの業務キャパに余裕が生まれ、有給取得や長期休暇も取りやすくなるなど働きやすさが向上します。
さらに、万一社内担当者が退職してもアウトソーシング先が業務を継続できるため、「人がいなくて仕事が回らない」事態を回避できます。
自社の状況に応じて、信頼できる外部サービスの導入も検討すると良いでしょう。
5. バックオフィス業務を外注するメリット
上記対策の一つとして触れたバックオフィス業務の外注(アウトソーシング)には、多くのメリットがあります。
ここでは外注化によって得られる主な利点を紹介します。
- コスト削減が可能: 専門業務を外注することで、正社員を雇うよりも人件費や教育コストを抑えられます。特に経理などの業務を外注すれば、固定費の変動費化も可能です。
- コア業務に集中できる: 事務作業を外注すれば、社員は営業や企画などの収益業務に集中できます。結果として企業全体の生産性向上につながります。
- 専門知識を持つプロに任せられる: 外注先には専門知識やノウハウがあるため、高品質な業務遂行が期待できます。法務や労務をプロに任せることでコンプライアンス強化にもなります。
- 業務の属人化を防げる: 外注により業務プロセスが標準化され、特定の社員に依存しない体制を構築できます。担当者が退職しても、業務の継続性が確保されます。
- 法的トラブルのリスクを低減できる: 専門業者に依頼することで、法令違反のリスクを防げます。社労士や税理士がいるアウトソーシング会社なら、法改正への対応漏れも回避できます。
- 業務のスピードと精度が向上する: 外注先は専用ツールやシステムを活用しており、業務を迅速かつ正確に処理できます。経費精算や給与計算なども社内対応より効率的になります。
このように、バックオフィス業務の外注には多くのメリットがあります。
ただし外注先との連携や機密情報の取扱いには注意も必要です。
6. バックオフィス社員の退職に関するよくある質問
最後に、バックオフィスに関して採用担当者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめます。
現場で疑問に感じやすいポイントをQ&A形式で解説します。
Q1. バックオフィスに向いている人は?
A. バックオフィスに向いている人の特徴としては、まず地道な事務作業をコツコツと継続できる人が挙げられます。
同じような事務処理の繰り返しでも飽きずに正確に取り組めることは重要です。
また、人をサポートするのが好きな人も適任です。
他部署を支える裏方役に喜びを感じられるタイプはバックオフィス業務にやりがいを見出せます。
さらにコミュニケーション能力が高い人も向いています。
社内外の様々な人とやり取りし調整する場面が多いため、円滑なコミュニケーション力は欠かせません。
Q2. エース社員が辞める理由は何ですか?
A. 業績優秀な「エース社員」であっても、辞めてしまうことはあります。
主な理由の一つは自分が正当に評価されていないと感じることです。
「どんなに成果を出しても報われない」と失望すれば、強い愛社精神を持つ人でも退職を考えます。
もう一つは成長のチャンスがないことです。
現状に満足せず常に高みを目指す優秀な人ほど、会社にこれ以上の成長機会が無いと判断すると見切りをつけてしまいます。
さらに「他社の方が高い評価や待遇を提示してくれた」「会社の将来性に不安を感じた」などの理由も共通して見られます。
Q3. バックオフィスの年収はいくらですか?
A. バックオフィス職種の年収は職種や経験、企業規模によって幅がありますが、一般的な企業では平均年収はおおよそ400万~500万円台と言われます。
ある調査によれば、全国の給与所得者の平均年収(443万円)に対し、バックオフィスの平均年収は約511万円とやや高めでした。
例えば経理・人事・総務などスタッフ層の平均が500万円前後で、専門性の高い法務やIT部門ではさらに高くなる傾向があります。
またマネージャークラスになると年収1,000万円以上も十分目指せる領域です。
一方、中小企業や未経験層では300万円台からのスタートもあり得ます。
このようにバックオフィスの年収は一概に言えませんが、平均すると中堅クラスで500万円前後と考えておくとよいでしょう。
Q4. バックオフィスと一般事務の違いは何ですか?
A. 「一般事務」はバックオフィス業務の一部であり、バックオフィスの方が含まれる業務範囲が広いという違いがあります。
一般事務は主に各部署で発生する庶務・事務処理全般(電話対応、データ入力、書類ファイリングなど)を行う職種です。
一方でバックオフィスは、一般事務に加えて経理・人事労務・総務・法務・情報システムなど専門性を持った管理部門の業務も含む広い概念です
言い換えれば、一般事務は特定の部署に属さず社内の雑多な事務を担うケースが多く、バックオフィスは企業運営に必要な各管理部門の総称と言えます。
なお企業によって「事務職」の定義は異なることもありますが、一般事務=バックオフィスの一部であり、バックオフィス全体にはより専門的・戦略的な業務も含まれる点が大きな違いです。
7. まとめ
バックオフィス社員は企業を陰で支える重要な存在であり、その退職は会社にとって看過できない大きなリスクです。
業務過多や人間関係、評価への不満など様々な退職理由がある中で、企業側としては
- 業務の仕組み化
- 職場環境の改善
- 複数担当制の導入
- 定期面談の実施
- 引継ぎ準備の徹底
などできる限りの対策を講じていく必要があります。
近年はバックオフィス業務のアウトソーシングサービスも充実しており、外部の力を借りてリスク分散と効率化を図る選択肢も有効です。
大切なのは、平時から「もし明日キーパーソンが辞めても業務が回るか?」を念頭に組織体制を見直しておくことです。
備えあれば憂いなし――万全の対策でバックオフィス社員の退職リスクを減らし、企業運営の安定性を高めていきましょう。

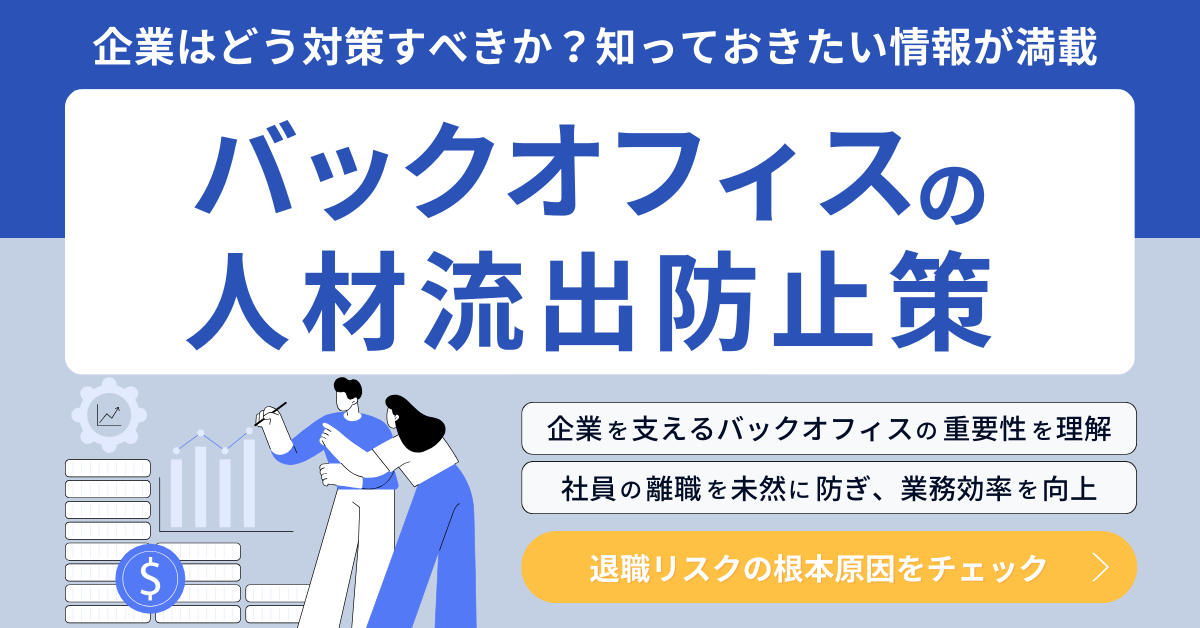

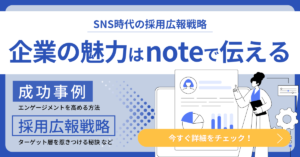
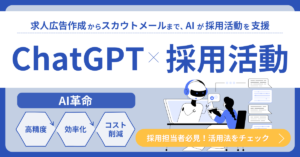
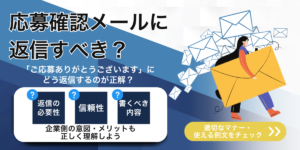
コメント