デジタル給与払い(給与デジタル払い)とは、企業が従業員の給与を銀行口座を介さずに、PayPayなどのスマホ決済アプリや電子マネー口座を通じて支払う新たな賃金支払方法です
2023年の法改正によって解禁された制度であり、従来の現金払い・銀行振込に加えて「資金移動業者」の口座への送金が公式に認められました
本記事では、中小企業の人事担当者向けに、デジタル給与払いはいつから可能になったのか(開始時期)、利用できる資金移動業者の一覧、企業・従業員それぞれのメリットとデメリット、導入・申請方法と手続きの流れ、注意点や審査の有無、さらによくある質問への回答まで、最新情報を踏まえて解説します。
ビジネスにおけるキャッシュレス化が進む中、本制度は給与支払いの選択肢を広げるものとして注目されています。
本記事の情報は厚生労働省など公式発表に基づいており、競合サイト以上に最新かつ公的な情報を盛り込んでいます。
「デジタル給与払い いつから?」といった疑問に答えながら、制度の概要とポイントを網羅します。
デジタル給与払いはいつから始まったのか?
デジタル給与払いが正式に可能になったのは、2023年4月1日からです.。
この日付は、労働基準法施行規則の改正が施行された日であり、賃金の支払手段に資金移動業者(電子マネー口座等)への振込が追加されました。
審査には数ヶ月を要する見込みとされ、実際にサービスが使えるようになるには対象業者の指定完了を待つ必要がありました。
初の指定業者が誕生したのは2024年8月です。
厚生労働省は2024年8月9日付で、QRコード決済大手のPayPay株式会社を初めて指定したと発表しました。
これは2023年の制度解禁から約1年越しでの初指定であり、デジタル給与払い実現に向けた大きな一歩となりました。その後、2024年12月13日付で2社目の指定も行われています。
以下で詳しく指定業者を紹介しますが、実際に従業員がデジタル給与を受け取れるようになったのは2024年末以降であり、2023年4月の解禁当初は制度準備期間と位置づけられていました。
なお、PayPay給与受取サービスは2024年9月からソフトバンクグループ社員を対象に先行提供され、同年11月以降は他企業の従業員にも利用対象が拡大されています。
これは指定完了後の段階的な展開で、年内に全てのPayPayユーザー(約6,400万人)へ広げる計画が進められたものです。
つまり、多くの企業にとって2024年後半~2025年にかけてがデジタル給与払い実用化のタイミングになります。
制度そのものは2023年から存在しますが、「いつから使えるか」という観点では指定業者のサービス開始時期が重要であり、2024年末にかけてようやく一般の従業員が利用できる環境が整ってきたと言えます。
デジタル給与払いに対応可能な「指定資金移動業者」一覧
デジタル給与払いを行うには、厚生労働大臣が指定した資金移動業者を利用する必要があります。
2023年4月の制度開始以降、複数の事業者が名乗りを上げ、所定の審査を経て順次指定されています。
2024年12月時点で指定済みの業者は以下の2社です。
(今後も追加指定があり次第、厚労省HPの「指定資金移動業者一覧」に掲載予定)
指定番号: 厚生労働大臣第00001号(初号)
指定年月日: 令和6年8月9日(2024年8月9日)
受取口座残高の上限額: 20万円まで(超過時は自動的に代替口座へ送金)
特徴: QRコード決済最大手のPayPayによるサービス。従業員は自身のPayPayアプリ内に「給与受取用口座」を開設し、そこに給与が振り込まれます。企業側は銀行振込とほぼ同様の手続きで給与を送金可能とされ、追加のシステム開発や新たな契約無しで導入できる利便性が特徴です。万一PayPayが破綻した場合でも、保証機関(三井住友海上火災保険)による残高全額の補償が予定されており、6営業日以内に代替口座へ振り込みが行われる想定です。
指定番号: 厚生労働大臣第00002号
指定年月日: 令和6年12月13日(2024年12月13日)
受取口座残高の上限額: 30万円まで
特徴: リクルートと三菱UFJ銀行の合弁会社によるサービスで、「Airワーク給与支払」という給与支払いプラットフォームを通じて提供されます。従業員は専用アプリ「Airウォレット」を利用し、COIN+口座で給与を受け取ります。働いた分を最短10分で即時に受け取れる「給与即払い」機能を打ち出しており、月末・月一払いの慣行に捉われない柔軟な支払いも可能になる点が特徴です。保証については三菱UFJ銀行が保証機関となっており、残高は銀行口座連携により保全されます。銀行との密な連携により、入金・出金手数料が何度でも無料(連携銀行の場合)など利便性も高めています。
これら2社以外にも複数の資金移動業者が現在審査中または申請準備中です。
2024年8月時点でPayPay以外に3社が審査待ちとの報道があり、2024年12月時点の厚労省発表では累計4社が申請し、2社が審査中となっています。
今後指定業者が増えれば、利用できるサービスの選択肢も拡大する見込みです。
最新の指定状況は厚生労働省の公式サイトに随時更新されるため、導入検討時には必ず最新情報を確認してください。
各指定業者ごとにサービス仕様(口座残高上限や手数料体系、保証スキーム)が異なります。
例えば上記のように残高上限額はPayPayで20万円、COIN+で30万円と差があります。
また従業員・企業が負担する手数料の有無(引き出し時の料金等)や、企業がサービス利用にあたり個別契約を結ぶ必要があるかといった点も業者により異なります。
導入に当たっては、これら仕様を比較検討し、自社のニーズに合ったサービスを選定することが重要です。
デジタル給与払いのメリット
デジタル給与払いを導入することで、企業側・従業員側それぞれに以下のようなメリットが考えられます。
- 給与振込手数料の削減の可能性: デジタル給与払いを導入すると、銀行振込手数料を削減できる可能性があります。資金移動業者を利用することで、企業の送金コストが低減するケースもあります。
- 業務効率化・支払いプロセスの簡便化: デジタル給与払いは給与支払い業務を自動化・簡略化し、振込作業の負担を軽減します。現金払いを行っていた企業にとっては、管理コストやリスクの削減にもつながります。
- 企業イメージの向上: デジタル給与払いの導入は先進的な企業としての印象を与え、若い世代の採用にも有利です。従業員の要望に応じた対応ができることで、満足度向上にも寄与します。
- 雇用機会の拡大: 銀行口座を持たない外国人労働者や若年層にも給与支払いが可能になり、人材確保の選択肢が広がります。特に技能実習生への支払い利便性向上が期待されています。
- キャッシュレス派にとって利便性向上:スマホ決済や電子マネーを利用する人にとって、給与を直接チャージできるのは便利です。銀行からの入金手間が省け、すぐに決済に使えるため、キャッシュレス生活がさらに快適になります。
- 給与の一部だけデジタルで受け取れる柔軟性: 給与の一部を電子マネーで受け取り、残りを銀行振込にするなど柔軟な運用が可能です。日常の支出と貯蓄を分けて管理しやすく、家計管理のしやすさが向上します。
- 早期・柔軟な給与受け取り: 給与即時払いサービスを利用すれば、給料日前でも働いた分を受け取れる可能性があります。特にギグワーカーやアルバイトにとって、急な出費に対応しやすい仕組みです。
- 安全性の担保: 資金移動業者には保証制度があり、万が一の破綻時も一定額までは保護されます。残高上限を超えた分は自動で銀行口座へ送金されるため、安心して利用できます。
デジタル給与払いのデメリット・注意点
一方で、デジタル給与払いには導入・利用にあたって注意すべきデメリットや課題も存在します。
企業側・従業員側の双方から見た懸念点を整理します。
- 導入手続きの手間(労使協定の締結等): デジタル給与払いを導入するには、労使協定の締結や就業規則の改定が必要です。労働基準監督署への届出や社内調整も求められ、準備に時間と労力がかかります。
- 既存システムとの連携・対応: 給与計算システムが資金移動業者に対応しているか確認が必要で、場合によっては改修が発生します。複数の支払方法を併用する場合、処理が複雑になり、コストや技術的課題も考慮すべき点です。
- 運用管理の煩雑化:銀行振込とデジタル払いが混在することで、給与データの作成や処理が複雑になります。振込エラー時の対応も含め、運用管理の負担が増える可能性があります。
- 強制は禁止(労基法違反のリスク):デジタル給与払いは従業員の同意が必須であり、企業が強制すると労基法違反となる恐れがあります。同意撤回にも対応できる運用を整える必要があります。
- 限定された選択肢: 利用できる資金移動業者が限られており、従業員の希望する電子マネーに対応できない場合があります。新たな業者を利用する際には、労使協定の再締結が必要になる可能性もあります。
- 現金化や他行への振込に手数料がかかる場合がある: 電子マネー口座の給与を現金化したり銀行へ移す際に手数料が発生する場合があります。無料で受け取れていた銀行振込と比べると、コスト負担が増える可能性があります。
- 慣れない人にとっては不安・不便: 高齢者やスマホを持たない人にとっては、操作ミスや残高管理の不安が生じる可能性があります。企業側も銀行振込など他の選択肢を提示する必要があります。
- 資金移動業者の選択が限定される:勤務先が導入した業者に依存するため、自分の希望する電子マネーが使えない可能性があります。給与の受け取り方法を自由に選べない点はデメリットです。
- 制度への理解が必要: デジタル給与払いは預金ではなく支払い用の口座であるため、未使用による失効リスクなどを理解する必要があります。将来的な制度変更にも対応が求められます。
- 現時点でメリットを感じない人も多い: 導入企業が少なく、銀行振込で十分と考える人も多いため、普及には時間がかかる可能性があります。社内で少数派になることで不便を感じる場面もあるかもしれません。
デジタル給与払いの導入手続きと申請方法
企業がデジタル給与払いを導入するには、所定の手順を踏む必要があります。
ここでは企業側と従業員側、それぞれの申請・同意手続きの流れを解説します。
なお、デジタル給与払いの利用自体に企業が行政許可を得る必要はありません(後述のとおり審査の対象は資金移動業者のみ)が、労働基準法上の手続きを適切に行うことが求められます。
- 指定資金移動業者の選定: 厚生労働大臣の指定業者から、自社のニーズに合ったサービスを選定。手数料や保証内容を比較し、方針を決定する。
- 就業規則の改定: 給与支払い方法に資金移動業者口座振込を追加。従業員10名以上の企業は労基署へ変更届を提出する。
- 労使協定の締結: 労働者代表と協定を締結し、対象範囲や利用業者を明記。労働組合があれば協議の上締結し、社内掲示で周知。
- 従業員への周知と説明: 制度導入を通知し、希望者へ詳細を説明。他の選択肢(銀行振込等)があることも明示し、強制しない。
- 同意書の提出・収集: デジタル払いを希望する従業員からは、書面(または電子)の同意書を提出してもらいます。同意書には以下の事項を記載する必要があります。
- 資金移動業者名とサービス名(例:PayPay給与受取)
- 受取人である労働者自身の資金移動業者口座識別情報(口座番号やアカウントIDなど)
- デジタル払いで受け取る金額(または割合)
- 代替口座の情報(労働者名義の銀行預貯金口座。残高上限超過時や保証金受取先となる口座)
- 同意日および支払開始希望時期(例:「○年○月給与より適用」)
- 社内給与支払事務の整備: システム設定や振込方法を確認し、処理スケジュールを調整。テスト送金を行い、従業員の受取確認を実施。
- 振込方法: 企業がサービス提供元に開設する送金用口座から各従業員口座へ振り込む方式か、あるいは現行の銀行振込と同様に業者側が指定する受入口座(銀行経由)へ送金する方式か。銀行振込に比べて早めに処理が必要な場合(前営業日までに振込など)もあり得るため、社内の給与計算スケジュールを調整します。
- 給与支払いの実行: 支給日に送金処理を実施し、給与明細に支払方法を明記。残高上限超過分は代替口座へ送金し、周知を徹底する。
従業員の立場でデジタル給与払いを利用したい場合、基本的には勤務先企業の案内に従って同意手続きを行うことになります。一般的な流れは次のとおりです。
- 社内アンケート等で希望を表明: 会社からデジタル給与払い導入の案内があったら、利用を希望する旨を人事担当者に伝えます。会社によっては事前アンケートや希望調査を実施することがあります。
- 資金移動業者のアカウント準備: 給与を受け取るために、自分が希望する資金移動業者のアカウント(例えばPayPayやCOIN+)を開設します。口座情報や本人確認を済ませ、必要な情報を最新の状態に更新しておきます。
- 会社へ同意書を提出: 会社指定の同意書に必要な情報(氏名、口座情報、希望金額等)を記入し、提出します。期限内に提出し、不明点は人事担当者に確認して、手続きを進めます。
- サービス利用開始と確認: 給与支給日に自分の電子マネー口座に給与が振り込まれているか確認します。初回は金額を確認し、異常があればすぐに会社に連絡します。
- 日常的な管理: 受け取った電子マネー残高はそのまま使えますが、銀行口座に移す場合の手数料や処理日数を把握しておきます。また、サービスに不具合が発生した場合のサポート窓口も確認しておきます。
- 同意の撤回や変更: デジタル給与払いの利用を続けたくない場合や、別のサービスに変更したい場合は、会社に申し出て同意を撤回または変更できます。銀行振込に戻したい場合は再度手続きが必要です。
審査・許可の必要性について
企業や従業員がデジタル給与払いを利用すること自体に、国の審査や許可は不要です。
前述のとおり審査の対象となるのは資金移動業者であり、厚生労働省が各業者を事前に審査・指定しています。
企業は指定済み業者を使いさえすれば、追加の行政認可手続きなく制度を導入できます。
したがって、「○○会社はデジタル給与払いを導入するために国に申請書を提出し承認を得る」といったプロセスはありません。
労働基準監督署は各企業の就業規則や労使協定を確認できますし、万一違法な運用(強制導入など)があれば指導や是正勧告の対象となります。
適切な手続きを踏んでいる限り、特段の審査はありませんが、導入後も法令順守に留意することが重要です。
また、資金移動業者側で企業向けに利用申込や審査(反社チェック等の観点)がある場合も考えられますので、各サービスの利用規約に従って手続きを進めましょう。
よくある質問と回答(FAQ)
最後に、デジタル給与払いに関して中小企業の人事担当者や従業員から寄せられがちな質問と、その公式な回答をQ&A形式でまとめます。
Q1: デジタル給与払いにすると、従業員は必ず電子マネーで受け取らなければならないのですか?銀行振込はもう選べないのでしょうか。
A1: いいえ。デジタル給与払いは給与受取方法の選択肢の一つに過ぎません。
従業員が希望しない場合は、これまで通り銀行口座で受け取ることができます。
企業側も希望しない従業員に対してデジタル払いを強制してはならず、あくまで本人の同意がある場合に限り実施されます。
Q2: 従業員から「給与をデジタル払いにしてほしい」と希望された場合、企業は必ず応じないといけませんか?
A2: いいえ。デジタル給与払いの導入自体、企業側にも義務ではありません。
労働者が希望しても、企業が導入しない選択も許されています。
実際に導入するかどうかは各企業の判断であり、導入する場合でも労使協定の締結と従業員個別の同意が必要です。
制度上、企業・従業員双方に強制するものではなく、双方の希望が合致した場合に初めて実施される仕組みです。
Q3: デジタル給与払いでは、ポイントや仮想通貨で給与を支払うこともできますか?
A3: いいえ。現金に替えられないポイントや仮想通貨での給与支払いは認められていません。
あくまで厚生労働大臣が指定した「資金移動業者」の提供する口座(電子マネー口座等)への振込みに限られます。
法制度上も賃金は通貨で支払うのが原則であり(労基法24条)、デジタル払いも実質的に円貨をデジタル移転しているに過ぎません。
したがってポイント付与などは給与支払いとは別のインセンティブとして扱う必要があります。
Q4: デジタル給与払いはいつから可能になりましたか?
A4: 2023年4月1日から制度上解禁されました。
この日以降、制度整備が進められ、実際のサービス提供開始は2024年から順次始まっています。
最初の指定資金移動業者であるPayPayが実際に給与払いサービスを開始したのは2024年9月頃(ソフトバンクグループ社内向け)で、同年11月から他社にも開放されました。
つまり、法律上は2023年から可能になり、実務上は2024年後半から利用が現実化した形です。
Q5: どのサービス(資金移動業者)ならデジタル給与払いに使えますか?
A5: 現在(2024年末時点)では、厚生労働大臣に指定された資金移動業者は2社のみです。
具体的には、PayPay株式会社(PayPay給与受取)と株式会社リクルートMUFGビジネス(COIN+)になります。
これら以外の業者はまだ指定を受けていないため、制度上利用できません。
導入企業はその中から利用するサービスを選択する必要があります。
また企業ごとに利用を許可するサービスが異なり得るため、自社がどのサービスに対応しているかを従業員は確認してください。
Q6: 給与全額を電子マネーで受け取った場合、預金保険のような保護はないのでしょうか?万が一、サービス提供会社が倒産したら残高は消えてしまいますか?
A6: 指定資金移動業者が破綻した場合でも、賃金受取口座の残高は提携する保証機関から速やかに弁済されます。
各サービスごとに異なる保証スキームが用意されていますが、例えばPayPayの場合は三井住友海上が保険によって残高を補償し、COIN+の場合は三菱UFJ銀行が保証を行います。
ただし資金移動業者ごとに具体的な弁済方法や所要日数は異なるため、利用開始時に企業やサービス提供元から説明を受けておくとよいでしょう。
なお、残高上限額(PayPayで20万円等)が設定されているのも、万一の場合の被害を限定する観点からです。
上限を超えた金額は自動的に代替銀行口座に送金され保全されます。
Q7: 給与の一部だけをデジタル払いにして、残りは銀行振込ということも可能ですか?
A7: はい、可能です。
デジタル給与払いは部分的な利用も認められており、同意書に記載する金額次第で一部のみ電子マネー口座振込とし、残額は従来通り銀行口座へ振込むことができます。
多くの企業では希望者でも全額を電子マネーにすることは少なく、「毎月○万円までを電子マネー、残りは銀行」といった形で運用されています。
この場合、会社の給与計算上も二本立てで振込処理を行います。
Q8: デジタル給与払いを導入すると税金や社会保険の扱いは変わりますか?
A8: いいえ、税金(源泉所得税)や社会保険料の計算・控除方法は従来と全く変わりません。
賃金そのものの性質が変わるわけではなく、支払経路が変わるだけなので、課税・保険料算定上も同様に扱われます。
給与明細にも総支給額や控除額を記載し、年末調整や源泉徴収票の作成も通常どおり行います。
電子マネーで受け取った給与も現金給与と同様に所得税の課税対象ですし、社会保険上の標準報酬月額にも含めます。
したがって、人事労務担当者が行うべき事務手続き(税・社保)に変更はなく、従業員側も受取方法によって税制上不利益を被ることはありません。
以上が、デジタル給与払いに関する主要なポイントとFAQです。
まとめ
制度は始まったばかりであり、現時点では慎重な企業姿勢も多く見られますが、キャッシュレス化の流れや労働力の多様化(ギグワーカーの増加等)に伴い、今後ニーズが高まる可能性があります。
中小企業の人事担当者の方は、本記事の情報や公式ガイドラインを参考に、自社にとって有益かどうかを見極めつつ、導入検討を進めてみてください。
制度の趣旨に沿って適切に運用すれば、従業員の利便性向上につながる新しい選択肢となり得るでしょう。

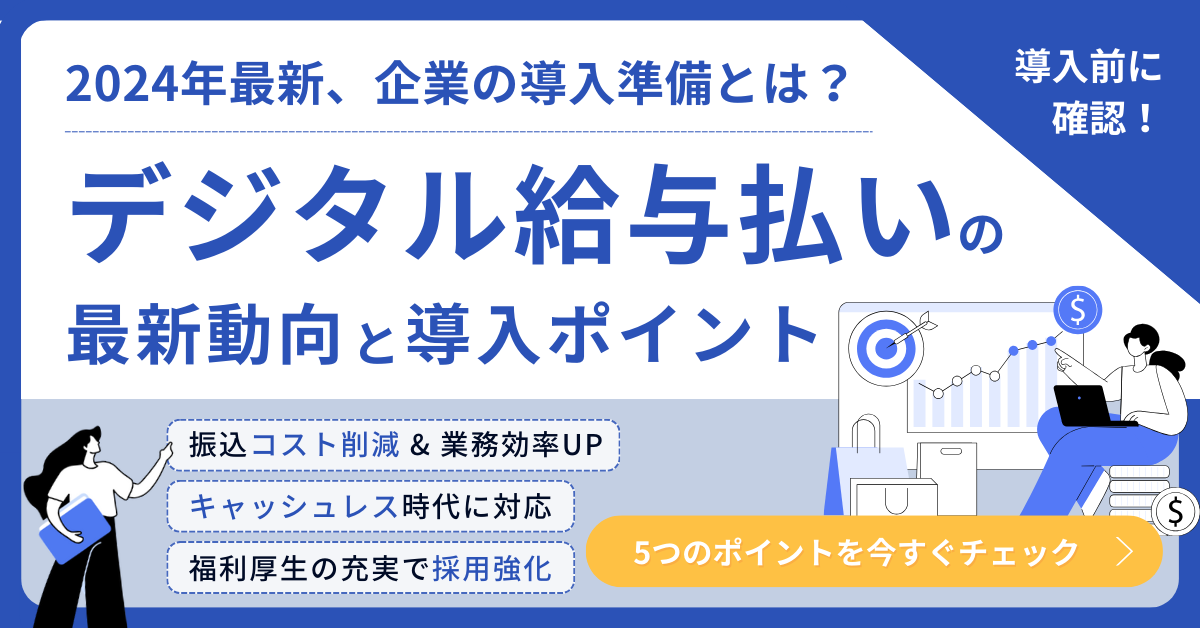
コメント