令和6年(2024年)4月から労働条件の明示ルールが改正され、中小企業の採用担当者も雇用契約書の内容を見直す必要があります。
適切な雇用契約書を整備することは、法令遵守はもちろん、労使間のトラブル防止や信頼関係構築にも不可欠です。
本記事では「雇用契約書」とは何か、その目的や労働条件通知書との違い、令和6年改正で追加された労働条件明示のポイント、そして雇用契約書の作成方法や注意点について解説します。
雇用契約書と令和6年に施行された新ルールへの対応ポイントを押さえ、安心して採用業務を進めましょう。
雇用契約書とは?
雇用契約書の定義と目的
雇用契約書とは、企業(雇用主)と労働者が雇用条件に合意したことを証明する文書です。
賃金や勤務時間など労働条件の詳細を明記し、双方が署名捺印することで正式に契約が成立します。
雇用契約書を取り交わす目的は、後々の認識違いやトラブルを防ぐために労働条件を明文化し、証拠として残すことにあります。
口頭や求人票で提示した条件でも契約は成立しますが、書面に残さなければ証明が難しく、万一争いになった場合に不利になりかねません。
雇用契約書があれば労働条件や待遇に関する認識の相違が生じた際も契約内容に沿って迅速に解決を図ることができます。
労働条件通知書との違いとは?
新入社員を採用する際には通常、「労働条件通知書」または「雇用契約書」を交付します。
一見すると同じ内容を記載しますが、両者には大きな違いがあります。
労働条件通知書は企業側が労働者に労働条件を提示・通知するための書類であり、法律上その交付が義務付けられています。
一方、雇用契約書は労働条件に労使双方が合意した証拠となる書類で、必ずしも法律で作成が義務付けられているわけではありません。
また、労働条件通知書には法定の記載事項や交付方法(書面またはメール等)に決まりがありますが、雇用契約書の様式や記載項目には決まった形式がなく、双方の署名があれば最低限の契約は成立します。
なお、労働条件通知書と雇用契約書を兼用することも可能です。
実務上は、一つの書類を「労働条件通知書兼雇用契約書」として作成し、必要な労働条件を明示したうえで従業員の署名捺印をもらうケースが多く見られます。
この方法なら法定の通知義務を果たしつつ、双方の合意を証明する契約書としても機能し、一石二鳥です。
重要なのは、どの形式であれ労働条件を明示すること自体は企業の義務である点です。
名称が通知書であっても契約書であっても構いませんが、法律で定められた事項を漏れなく伝えることが求められます。
なぜ雇用契約書が必要なのか?
雇用契約書の作成は法的義務ではありませんが、それでも用意しておくことが強く推奨されるのには理由があります。
まず、トラブル防止の効果です。
雇用条件通知書で一方的に条件を示すだけでは、従業員が本当にその条件に納得したか不明なままです。
しかし雇用契約書として署名をもらっておけば、労働者本人が条件に同意した証拠が残ります。
例えば未払い残業代の請求や、配属・待遇に関する認識のズレが生じた場合でも、契約書に立ち戻って解決できます。
雇用契約書がないと、提示した労働条件と実際の待遇が異なると従業員から主張された際に会社側が反証しづらくなり、紛争に発展しやすくなります。
また、信頼関係の構築という観点も重要です。
特に最近は働く側の権利意識も高まっており、「契約書を交わさない会社」に不安を感じる求職者もいます。
雇用契約書を交付することは、従業員に安心感を与え入社後のミスマッチを減らす効果も期待できます。
さらに、契約書を整備しておけば社内の労務管理体制のチェックにもなり、就業規則や給与体系の再点検につながるでしょう。
以上のように、雇用契約書は法的な防御策であると同時に、円滑な人材定着のための信頼の礎となるものなのです。
労働条件明示のルールで追加される4つ改正内容
令和6年4月施行の改正により、労働条件通知の際に新たに明示が必要となった4項目があります。
中小企業においても採用時や契約更新時に確実に対応しなければならないポイントです。
ここではその4つの改正内容について具体的に解説します。
1.就業場所・業務内容の変更範囲を具体的に記載する
まず追加されたのが、「就業場所・業務の変更の範囲」の明示です。
これはすべての労働者(有期・無期を問わず)について、労働契約の締結時に書面で示すことが新たに義務付けられました。
従来も「就業場所」「担当業務」は明示事項でしたが、今回さらに将来的に配置転換によって変更されうる範囲まで示す必要があります。
例えば、「当初の就業場所は東京本社だが、将来的に国内支店へ異動の可能性がある」や「業務内容は経理事務だが、将来的に関連する総務業務を担当する可能性がある」といった具合に、配置や職務の変更範囲をできるだけ具体的に記載します。
しかし、特に正社員など長期雇用を前提とする場合、将来の異動範囲を最初から明確に限定することは難しいケースもあります。
現時点で想定し得る範囲を記載しても、実際にはそれを超える異動の必要が生じる可能性もあるでしょう。
そのため、想定が困難な場合は変更範囲を広めに記載しておくことが望まれます。
例えば「全国の事業所への配置転換の可能性がある」など包括的に示す方法です。
同時に、就業規則に配置転換に関する規定を置き、企業が業務上の必要に応じて人事異動を命じる権利があることを明文化しておくと安心です。
これにより、後日「聞いていない勤務地への異動」を命じる際にも、事前に説明した範囲内であることを示せるため労使双方の認識差を減らせます。
2.契約更新の上限を明確に提示する
次に、有期雇用契約者に対する「契約更新の上限」の明示が義務化されました。
更新上限とは、有期契約を何年まで(通算契約期間)または何回まで(更新回数)更新する可能性があるか、その上限の有無と内容を指します。
たとえば「契約更新は通算3年まで」「更新回数は最大2回まで」といった情報です。
令和6年4月以降は、有期労働契約の締結時および更新時に、この更新上限の有無と具体的な内容を必ず書面で示さなければなりません。
さらに、契約締結後に企業側が更新上限を新設または短縮する場合には注意が必要です。
今回の改正では、最初の契約時に定めていなかった更新上限を途中で設ける場合や、当初定めた上限をさらに短く変更する場合には、その理由を事前に労働者へ丁寧に説明する義務も課されました。
例えば、事業計画の変更で当初5年可能としていた更新期間を3年に短縮するようなケースでは、「業績悪化に伴い長期契約が困難となったため」等、合理的な理由を本人に事前説明し納得を得る必要があります。
このように更新上限の設定・変更に関して透明性を高めることで、契約満了時の雇い止めトラブルを防ぐ狙いがあります。
3.無期転換を申し込めるタイミングの明示する
3つ目の改正ポイントは、有期契約労働者に対する「無期転換を申し込めるタイミング」の明示です。
いわゆる無期転換ルール(労働契約法第18条)に基づき、有期契約が一定期間継続した場合に労働者が期間の定めのない契約への転換を申請できることは以前から定められていました。
この無期転換申込権が発生する具体的な時期について、今回の改正後は書面で明確に知らせることが義務となりました。
簡単に言えば、契約期間の合計が5年を超えたタイミングで「無期雇用にしてください」と申し出る権利が発生し、申し出があれば雇用主は拒否できず無期契約へ移行する制度です。
この権利発生のタイミングを労働者に知らせるのが今回の改正趣旨です。
具体的には、例えば契約期間1年の有期契約社員であれば5回目の更新(通算契約期間が5年を超える時点)の契約更新時に申込権が発生します。
契約期間3年の場合は1回目の更新(通算6年)で発生します。
同様に2年契約なら2回目更新後、6ヶ月契約なら11回目更新後…という具合です。
申込権が発生する契約更新時には、その場で無期転換申込が可能であることを必ず書面で通知しなければなりません。
4.無期転換後の労働条件を事前に通知する
4つ目の改正点は、「無期転換後の労働条件」の事前明示です。
有期から無期への転換申込権が発生するタイミングごとに、転換後に適用される労働条件を労働者に通知することが求められます。
無期転換後に労働条件がどう変わるのか不透明だと、労働者は転換申し込みをためらうかもしれません。
そこで事前に「無期になった後は契約社員から正社員待遇に変更」「賃金形態は月給制に変更(〇〇手当を新設)」など具体的な条件を提示しておくのです。
無期転換後の労働条件を決定するにあたっては、近年重要視されている同一労働同一賃金の理念(正社員と非正規社員の不合理な待遇差禁止)を踏まえ、公正な設定を行う必要があります。
今回の改正でも、無期転換後の労働条件を定める際には正社員とのバランスを考慮した事項について説明するよう努めることが求められています。
例えば無期転換社員に昇給制度や退職金制度を適用しない場合でも、その理由(職務内容や責任範囲の違い等)を本人に説明し納得を得る努力が必要です。
以上の4項目が令和6年改正で新たに明示すべき事項として追加されました。
まとめると
- 将来の就業場所・職務変更の範囲
- 有期契約の更新上限の有無と内容
- 無期転換申込権が発生するタイミング
- 無期転換後の待遇内容
を労働契約締結時または更新時に必ず書面で知らせる必要があります。
労働条件通知書と就業規則の違い
労働条件を明示する際に関連する文書として就業規則がありますが、労働条件通知書(雇用契約書)とは目的や適用範囲が異なります。
就業規則は企業内の労働条件や服務規律を包括的に定めた社内規程であり、常時10人以上の労働者を使用する場合は作成・届け出が法律で義務付けられています。
一方、労働条件通知書は各従業員ごとの個別の労働条件を示す書面です。
両者の大きな違いは、適用範囲と詳細度です。
就業規則は従業員全体に共通の一般的なルール(賃金テーブルや勤務時間区分、休職制度など)を網羅的に定めるものです。
一方で労働条件通知書は個々の従業員に対し、その人固有の賃金額や勤務場所など具体的条件を通知するものです。
したがって、労働条件通知書では各人ごとの大枠の条件を示し、細部の共通ルールは「詳細は就業規則による」などと参照させることも可能です。
例えば「退職手当:就業規則の定めによる」「育児休業制度:就業規則のとおり」と通知書に記載すれば、個別に長々と説明を書く代わりに就業規則を参照させる形で明示したことになります。
ただしこの場合
- 就業規則を従業員がいつでも閲覧できるようにしておくか
- コピーを労働条件通知書と一緒に交付するか
上記の必要があります。
就業規則に委ねる形で条件明示をするなら、その規則の存在と入手方法を周知させることが法律上求められるからです。
また、就業規則と雇用契約書(通知書)のどちらが優先されるかも押さえておきたいポイントです。
一般的に、個々の雇用契約書の内容が就業規則より労働者に有利であれば契約書が優先し、不利であればその部分は無効となり就業規則の定めが適用される、とされています(労働契約法第12条)。
例えば就業規則上の有給休暇日数より契約書で多く与えれば契約書が優先しますが、逆に規則より少ない有給日数しか契約書に書かれていない場合、その部分は無効となり就業規則どおりの有給日数が保証されます。
このように、就業規則は労働条件の最低基準を示す役割も果たします。
労働条件通知書を作成する際は、必ず就業規則との整合性を確認し、矛盾や不利変更がないように注意しましょう。
もし自社が就業規則をまだ整備していない場合でも、社員数が増えれば整備義務が発生しますし、トラブル防止のため自主的に作成しておくことをおすすめします。
労働条件通知書の書き方
次に、実際に労働条件通知書(雇用契約書)を作成する際に押さえておくべき項目と書き方のポイントを解説します。
労働条件通知書には法律で定められた必須記載事項があり、令和6年の改正に対応した新たな項目も含め、漏れなく記載することが大切です。
以下に主な記載事項を挙げます。
労働条件通知書に必須の記載事項
労働基準法施行規則第5条では、労働条件通知書に明示すべき事項を定めています。
一般的に以下の項目は必ず書面で明示しなければならないとされています。
- 雇用契約の期間(期間の定めの有無。有期契約の場合は契約期間の始期・終期および更新の有無や基準)
例:契約期間は2024年4月1日から2025年3月31日まで。契約更新あり(最長通算3年まで、更新の判断基準:勤務成績・会社の業務量による)と記載。 - 就業場所と従事すべき業務の内容(初めに勤務する勤務地と仕事内容)
例:就業場所は本社(〇〇県〇〇市…)で、総務部一般事務に従事。将来的に人事業務へ配置転換の可能性あり。 - 始業・終業時刻、休憩時間、所定労働時間(1日の労働開始・終了時刻、休憩時間、所定労働日/時間)
例:始業時刻9:00、終業時刻18:00(所定労働時間8時間)。休憩60分(12:00〜13:00)。残業が発生する場合あり(36協定に基づき月○時間以内)。 - 休日・休暇(休日の曜日や日数、年次有給休暇など)年次有給休暇は法定どおり付与(初年度10日)。会社規定による夏季休暇3日あり。
- 賃金の決定方法・計算方法・支払日(基本給額、各種手当、計算方法、締日・支払日)
例:基本給月額20万円、職務手当2万円。時間外手当は法定割増率で支給。賃金締切日毎月末日、支払日翌月25日(銀行振込)。昇給は年1回4月に業績・評価により実施。 - 退職に関する事項(退職の事由・手続、解雇の事由、定年など)
例:自己都合退職する場合は原則として1ヶ月前までに届出。定年60歳(継続雇用制度あり)。懲戒解雇事由は就業規則の定めによる。
以上が基本的な必須記載事項です。
(短時間労働者の待遇に関する項目)。自社の雇用形態に応じ、必要な事項を漏れなく記入しましょう。
令和6年改正に対応した追加記載事項
前述した令和6年の改正に伴い、労働条件通知書(雇用契約書)には以下の項目も新たに記載する必要があります。
- 就業場所・業務内容の変更範囲 – 将来の配置転換によって変更され得る勤務地や職務の範囲を具体的に示すこと
(例:「将来的に全国の支店への転勤の可能性があります」など。) - 有期契約の更新上限 – 有期雇用の場合、通算契約期間または更新回数の上限があるか、その有無と内容
(例:「契約更新は最大○回まで、通算雇用期間は最長○年まで」など。) - 無期転換の申し込み機会と手続き – 有期契約から無期契約への転換申込権が発生する時期と、その申込方法
(例:「通算契約期間が5年を超える契約更新時に無期転換の申請が可能。希望する場合は人事部に書面で申請してください」など。) - 無期転換後の労働条件 – 無期契約に転換した後に適用される賃金・待遇などの条件
(例:「無期転換後の雇用形態:嘱託社員、基本給:月◯◯円、その他待遇は正社員と同等」など。)
これら4点は改正により新たに追加された明示事項であり、特に有期雇用者を採用・契約更新する際には必ず書面で通知しましょう
自社のひな形を更新していない場合は早急に追記し、現行の法律に適合したフォーマットにすることが重要です。
雇用契約書を作成時に押さえておくべきポイント
労働条件通知書および雇用契約書を作成する際には、以下のポイントを意識すると漏れや不備を防げます。
必ず記載すべき項目をチェックする
まず基本中の基本ですが、前述の必須記載事項がすべて盛り込まれているかチェックリストで確認しましょう。
契約期間、勤務地、勤務時間、給与、休日、退職条件など一つでも欠けると法令違反となる可能性があります
特に中小企業ではひな形が古いまま使われ、改正で追加された項目が抜け落ちているケースもあります。
厚生労働省が公開している最新のモデル様式や信頼できる雛形を参照し、自社のフォーマットをアップデートしてください。
労働時間・職務内容を明確にする
勤務時間帯や休憩、休日、職務範囲は労使トラブルになりやすい点なので、契約書上で具体的かつ明確に定めます。
始業・終業時刻だけでなく残業の有無や上限、シフト勤務の場合はシフト決定方法も記載すると親切です。
職務内容も「総合職」など曖昧にせず、当初の担当業務や役職を特定し、必要に応じて「将来的に異なる業務を担当する可能性あり」と付記します。
曖昧な記載は後から「聞いていた仕事内容と違う」といった不満につながりかねません。
就業場所・業務内容の変更範囲を記載する
今回の改正でも強調されたように、配転の範囲は明示が求められます。
特に総合職採用の場合は全国転勤や職種変更の可能性があるでしょうから、契約書に「将来、会社が業務上必要と認める場合は配置転換・転勤を命じることがある」旨を記載しましょう
一方、地域限定職や職種限定社員の場合は「〇〇地域内で異動の可能性」など範囲を限定して記載します。
変更範囲を明確に記すことで、後日労働者から配置転換を拒否された際にも「契約時に合意済みの範囲内である」と説明しやすくなります。
万一、契約書に明示がなく労働者の同意も得ていない勤務地変更を命じた場合、労働者に拒否され法的トラブルに発展する恐れがあります
そうしたリスクを避けるためにも、就業場所・業務変更の可能性は予め合意を得ておくことが大切です。
賃金・手当の設定と支払い方法を明記する
賃金条件については、金額や計算方法だけでなく内訳や支給形態も具体的に書きます。
基本給と各種手当を分けて明示し、みなし残業代(固定残業代)が含まれる場合はその旨と時間数・金額を正確に記載します。
固定残業代制を採用しているのにそれを書かないと、後で残業代の未払いを主張されトラブルになる典型例です
また賞与・昇給についても、「業績および勤務成績により支給/昇給することがある」等、支給有無や基準を記載しましょう(完全に支給しない場合も「賞与・昇給なし」と明示)。賃金の締日・支払日、支払い方法(銀行振込先など)も忘れずに書き込みます。
試用期間や転勤の条件を適切に設定する
試用期間を設ける企業は多いですが、その有無や期間、試用中の労働条件(本採用時との待遇差など)も契約書に明記しましょう
例えば「試用期間3ヶ月(本採用と同条件)」や「試用期間中は基本給〇〇円(本採用後△△円)」のように書きます。試用期間満了前に本採用可否を判断するプロセスも社内で決めて通知しておくとベターです。
また転勤の可能性がある職種では、その条件を明示しておきます。
前述の就業場所の変更範囲とも関連しますが、例えば転勤者には社宅提供や引越費用補助などの制度があるなら契約書または就業規則に規定しておき、通知書には「転勤命令により転居する場合、会社は転居費用を負担します(就業規則◯条)」といった注記を入れておくと親切です。
転勤や出向、昇格要件など契約期間中に発生し得るイベントについても可能な範囲で情報提供しておくことで、後々の誤解・不満を防げます。
退職・解雇に関するルールを明確にする
退職(雇用契約の終了)に関する取り決めも重要ポイントです。
契約期間の定めがある場合、「契約期間満了をもって退職とする」「更新しない場合は◯日前までに通知」等を記載します。
期間の定めがない正社員については、民法上は2週間前の意思表示で退職可能ですが、自社ルールとして引継期間確保のため「退職の申し出は1ヶ月前までに」と定めることが多いです(強制はできませんが周知は可能)。
解雇事由については就業規則に詳細を定めるのが一般的ですが、契約書にも「懲戒解雇・普通解雇は就業規則の定めによる」などとしておくと従業員も認識しやすいでしょう。
曖昧なままだと、いざ解雇しようとしたときに「聞いていない」と争いになる危険があります。
契約終了や解除に関する取り決めを事前に共有しておくことが、お互いの安心につながります。
労働条件の不一致が引き起こすトラブル
雇用契約書や労働条件通知書の不備・不明確さは、後々のトラブルの火種になります。
労働条件の認識不一致から発生しがちな典型的トラブルを押さえておきましょう。
未払い賃金や残業代請求
労働条件の不備によるトラブルで特に多いのが、賃金トラブルです。
契約時に給与計算方法や残業代支給ルールを明確にしていないと、「基本給に◯時間分の残業代が含まれているなんて聞いていない」「○○手当を支払ってもらっていない」などといった不満・請求につながります。
例えば固定残業代制度を導入している場合、契約書にその旨と内訳を記載しなかったがために「残業代の未払い」として追加請求されるケースも少なくありません。
賃金面の取り決めは一番シビアな問題だけに、曖昧な表現や口頭説明で済ませることは避け、契約書上で詳細に取り決めておく必要があります。
万一トラブルになれば、未払い賃金や残業代の清算に加え、会社の信用失墜や罰則(労基法違反)につながる恐れもあります。
業務内容や職務範囲の不一致
仕事内容に関する食い違いもトラブルの種になります。
採用時に説明していた業務内容と、実際に配属された後の業務内容が異なると労働者の不満を招きます。
「聞いていた話と違う部署に配属された」「営業職で採用されたのに雑務ばかりさせられる」といったケースです。
これは契約書や求人票で職務範囲を十分に説明していなかったことが原因の場合もあります。
また、本人のスキルや適性により業務変更が必要になった際も、契約上の職務記載と大きく逸脱する配置転換は拒否・紛争の火種となります。
職務内容や役職の変更は就業規則の定めに基づき会社が命じる権利はありますが、やはり契約時の合意範囲内であることが重要です。
解決策として、契約書で業務内容を特定しすぎず将来の変更可能性を盛り込んでおくか、逆に職種限定契約ならその旨明記することが考えられます。
いずれにせよ、事前の説明と合意なく仕事内容を変えることは避け、必要な場合は本人と十分話し合うことがトラブル防止につながります。
解雇・退職条件に関するトラブル
退職・解雇をめぐるトラブルも契約内容の不明確さから起こりがちです。
例えば、従業員が突然「今日で辞めます」と言い出した場合、就業規則や契約書に退職のルールが記載されていなければ会社として引き留める法的手段はなく、業務運営に支障が出るかもしれません。
逆に会社側が労働者を解雇しようとした際、契約上・規則上の根拠や手続きを踏まなければ不当解雇と争われる可能性があります。
特に有期契約社員の場合、契約期間満了前に一方的に契約を打ち切れば契約違反となりうるため注意が必要です。
更新上限や評価不足時の雇止め基準を示していないと、「期待して働いていたのに急に更新終了と言われた」とトラブルになるケースもあります。
したがって、契約段階で退職・解雇に関する取り決めを共有し、問題発生時は労基法や就業規則に則った対応を取ることが肝要です。
会社と従業員の信頼関係の悪化
契約時の約束と入社後の実態が食い違う状況が続けば、労使間の信頼関係は大きく損なわれます。
例えば「残業はほとんどない」と聞いていたのに実際は毎日残業続きだった、待遇面で聞いていた話より悪かった、といったことがあれば従業員のモチベーションは下がり早期離職にもつながりかねません。
信頼関係の悪化は職場環境の悪化を招き、ひいては企業の業績や評判にも影響を及ぼします。
逆に言えば、最初に約束した労働条件をしっかり守り、万一変更が必要な場合も労働者と協議して合意の上で行えば、良好な関係を維持できます。
法的トラブルや訴訟
最終的に深刻なのは、労働条件トラブルが解決せず法的紛争に発展するケースです。
- 未払い残業代の請求訴訟
- 地位確認(解雇無効)訴訟
- パワハラや契約不履行に関する損害賠償請求
など、労働問題は訴訟沙汰になれば企業側の負担(時間・費用・社会的信用の低下)は計り知れません。
労働基準監督署や労働審判・訴訟に持ち込まれた場合、基本となるのは書面による証拠です。
雇用契約書や労働条件通知書にきちんと労働条件が明示され、労使双方がその内容を認識・合意していたかどうかが争点となります。
適切な契約書が用意されていなかった企業は反証が難しく、裁判でも不利になりがちです。
そうした事態を避けるためにも、平時から契約書類を整備し法的に問題ない運用をしておくことが重要です。
雇用契約書作成を効率的に行う方法
ここまで見てきたように、雇用契約書には記載すべき事項が多岐にわたります。
一つ一つ手作業で作成・管理するのは中小企業のご担当者にとって負担かもしれません。
そこで、雇用契約書の作成を効率化するための方法をいくつかご紹介します。
契約書作成ツールを活用する
最近では、人事労務管理のクラウドシステムや電子契約サービスなど、契約書作成をサポートするツールが多数登場しています。
社員情報を入力すると雛形に自動反映して個別契約書を生成できたり、Web上で契約書を送信・電子署名して回収できるサービスもあります。
例えば「〇〇クラウドサイン」など電子契約サービスでは、ひな形を登録しておけば社員ごとに契約書を自動作成し、オンライン上で従業員と契約締結することも可能です。
紙の契約書を印刷・押印・郵送する手間が省け、作成状況も一元管理できるためミスや漏れ防止につながります。
また、複数の担当者で同時に大量の契約書処理を行うニーズにも対応したシステムがあり人事担当者の負担軽減に役立ちます。
こうしたITツールを上手に活用し、煩雑になりがちな契約書作成業務を効率化しましょう。
テンプレートを活用する
自社に契約書作成ツールを導入していなくても、ひな形(テンプレート)を活用するだけで効率は大幅に上がります。厚生労働省も令和6年改正対応の「モデル労働条件通知書」を公開しています。
これは一般的な正社員用、有期契約社員用などに分かれたフォーマットで、必要事項が網羅されています。
まずはこの公式テンプレートをダウンロードし、自社の実態に合わせて項目を追加・修正するとよいでしょう。
自社独自のフォーマットをゼロから作るよりも、公式の様式をベースにすることで記載漏れ防止にもなります。
また、民間の信頼できるサイトでも契約書の無料テンプレートが提供されています。
注意点として、いずれのテンプレートも最新の法改正に対応済みかを確認しましょう。
契約内容の自動更新機能を導入する
有期雇用契約者が多い企業では、契約更新のたびに新しい契約書を作成する手間もばかになりません。
そこで、契約内容の自動更新(オートリニューアル)機能を活用する方法もあります。
例えば人事システム上で契約の有効期限を管理し、更新時期が近づくとアラートが出たり、前回契約書の内容をコピーして新規契約書を作成する仕組みです。
これにより、いちいち一から書類を作り直す必要がなくなります。
契約更新時に昇給や勤務地変更など変更点がなければ、基本情報を引き継いで日付だけ変更すれば良いため大幅な時間短縮になります。
また、無期転換権が発生する5年目の更新者をシステムで事前に把握し、必要な案内を自動で行うよう設定しておくことも可能です。
このように、繰り返し業務はできるだけシステムに任せ、人事担当者は内容確認など本質的な業務に注力できる環境を整えると良いでしょう。
雇用契約書に関するよくある質問
最後に、雇用契約書にまつわる素朴な疑問やトラブルについて、Q&A形式で整理します。
採用担当者として把握しておけば、求職者や従業員から問合せがあった際にも適切に対応できるでしょう。
Q1. 雇用契約書はどこで・いつもらえる?
A: 雇用契約書(または労働条件通知書)は、通常入社が決まった段階で企業から交付されます。
多くの企業では入社手続きの際に人事担当者から直接手渡されるか、事前に郵送・メール送付されます。
正社員であれば内定後~入社日までに契約書を取り交わすケースが一般的です。アルバイトやパートの場合、初出勤日にその場で雇用契約書(労働条件通知書)を渡すこともあります。
いずれにせよ労働基準法では雇い入れの際に書面で労働条件を明示する義務がありますので、本来は入社日までに従業員が入手できるようになっているはずです。
昨今はペーパーレス化に伴い、電子データで契約書を交付する企業も増えています。
その場合、社員専用のWebシステムやメール添付で契約書PDFが送られ、労働者は内容を確認して電子承諾または紙に署名返送する、といった方法がとられます。
いずれの形でも「いつまでに」「どのように」契約書が交付されるかを企業から案内してもらえるはずです。
不明な場合は遠慮なく問い合わせましょう。
Q2. 雇用誓約書がもらえないのはなぜ?
A: ここでいう「雇用誓約書」が「雇用契約書」や「労働条件通知書」を指すのであれば、企業が書面交付を怠っている可能性があります。
法律上、労働条件の明示は義務ですが、雇用契約書自体の交付義務はありません。
そのため一部企業では労働条件通知書(会社からの一方的通知)だけ渡し、労働者の署名する契約書は用意しない場合があります。
また、小規模事業所では口頭やメールで条件説明して契約書を交わさない慣行のところもあります。
しかし労働条件通知書の交付は必須なので、「何ももらっていない」のは本来あってはならないことです。
考えられるのは、会社側が交付時期を忘れているか、既に渡したと認識しているケースです。
例えば内定通知書に労働条件が書いてありそれで済ませている可能性もあります。
雇用契約書というタイトルの書類でなくとも、労働条件が明示された書面を受け取れるはずです。
それでももらえない場合、法令違反の恐れがありますので、労働者側は最寄りの労働基準監督署に相談するといった方法もあります。
いずれにせよ入社時に書面をもらえないのは不安な状況ですので、早めに確認することをおすすめします。
Q3. 雇用契約書が交わされていない会社を辞めるには?
A: 仮に雇用契約書を交わしていない(書面にサインしていない)状態でも、実際に働いて給与を受け取っていれば雇用契約関係は成立しています。
そのため退職する際は、通常のルールに従って手続きを行う必要があります。
ただ現実的には会社の就業規則で「退職は1ヶ月前までに申し出ること」などの取り決めがある場合が多いので、それに沿ってできるだけ早めに退職の意思を伝えるのが円満です。
一方、有期契約社員の場合は契約期間満了をもって退職となるのが原則です。
期間途中で辞めたい場合、やむを得ない理由がない限り契約期間中の一方的な退職(中途解約)は認められにくい点に注意が必要です。
会社と話し合い合意できれば途中退職も可能ですが、無断で辞めれば債務不履行となる恐れもあります。
いずれの場合も、書面がないから好きに辞めて良いというわけではないことを認識しましょう。
契約書がなくても、労使間の約束(口頭やメールでの合意、あるいは働き始めた事実)が契約として機能しています。
したがって退職するには、在籍中の他の社員と同様にしかるべき手順を踏む必要があります。
具体的には直属上司や人事に退職意思を伝え、退職願を提出し、引継ぎなど会社の指示に従いましょう。
契約書の有無に関わらず誠実に手続きを行うことが、自分の信頼を守ることにもなります。
Q4. 雇用契約書はパートやアルバイトでももらえる?
A: はい、パートタイマーやアルバイトであっても労働条件通知書(雇用契約書)をもらえます。
むしろ企業側は交付しなければなりません。雇用形態に関わらず、労働基準法は全ての労働者に対して労働条件の明示を義務付けています。
正社員ほど厳密に契約書を交わさない会社も一部ありますが、それでも最低限の労働条件を書面で通知する義務はあります。
一般的には、アルバイト・パート採用時には「労働条件通知書」を渡し、希望すれば労働者側も署名して一部返してもらう(契約書として保管)という形を取る会社が多いです。
「アルバイトだから口頭説明だけで書面は渡さない」というのは法的に不適切ですので、もしそういった対応をされた場合は書面交付をお願いすると良いでしょう。
なお、パートタイム労働法の規定で、パート・有期雇用労働者には昇給・賞与・退職金の有無などフルタイム正社員との差異も説明する義務があります。
そうした点も含めて通知された書面を受領しているか確認しましょう。
Q5. 雇用契約書にサインしない場合、退職はどうなる?
A: 従業員が雇用契約書へのサインを拒んだ場合、法的には契約が未締結の状態です。
しかし実際に働き始めているなら、暗黙の了解で契約関係が成立しているとみなされます。
そのため、サインしていなくても退職する権利自体はもちろん有します。
退職意思を伝えることなく勝手に辞めれば無断欠勤となり得ますし、サインしていないことを理由に無条件で即時辞められるわけではありません。
一方で、もし雇用契約書に同意できない事項がありサインしなかった場合には、その点を会社と話し合って解決するのが先決です。
例えば契約書の中の特定の条項(競業避止義務や固定残業代等)に納得できず署名を保留しているのであれば、会社に修正を求めるか、それが難しければその労働条件を受け入れずに辞退(退職)する選択肢もあります。
ただし、働き始めてから長期間サインしないまま勤務を続けていると、労働者が事実上その条件を受け入れて働いていると解釈されかねません。
サインしない状態で曖昧に勤務を続けるのはリスクがあります。
退職を考えるなら早めに意思表示し、書面にサインしていなくても実態としてある雇用関係を円満に解消するよう努めましょう。
具体的には、上司や人事に契約書へ署名できなかった理由を伝えつつ、退職の意思を正式に伝達し、会社の指示に沿って退職手続きを進めるのが望ましいです。
まとめ
令和6年の労働条件明示ルール改正により、雇用契約書(労働条件通知書)に盛り込むべき事項が拡充されました。
中小企業の採用担当者の皆様は、自社の雇用契約書の内容を今一度チェックし、「就業場所・業務変更の範囲」「更新上限」「無期転換のタイミング・条件」など新たな必須事項が漏れていないか確認しましょう。
しっかりと作成・交付することで法律を遵守できるのはもちろん、従業員の安心感や会社への信頼度も高まります。
逆に不備や曖昧さがあると、未払い残業代請求や配転拒否など様々なトラブルを招き、企業にとって大きな損失となりえます。
契約書作成の手間はテンプレート活用やITツール導入で軽減できますし、厚労省から公式のモデル書式も提供されています。
これらも上手に活用しながら、効率的かつ漏れのない雇用契約書の整備を進めましょう。
契約時にしっかり取り決めを交わしておけば、後はその約束を守って雇用関係を運営していくだけです。
明確な労働条件の提示は、従業員との良好な関係構築と定着率向上にもつながります。
ぜひ最新ルールを踏まえた雇用契約書を作成し、安心して働ける職場環境づくりに役立ててください。
「雇用契約書」「令和6年改正」への適切な対応で、貴社の労務管理を一段と充実させていきましょう。

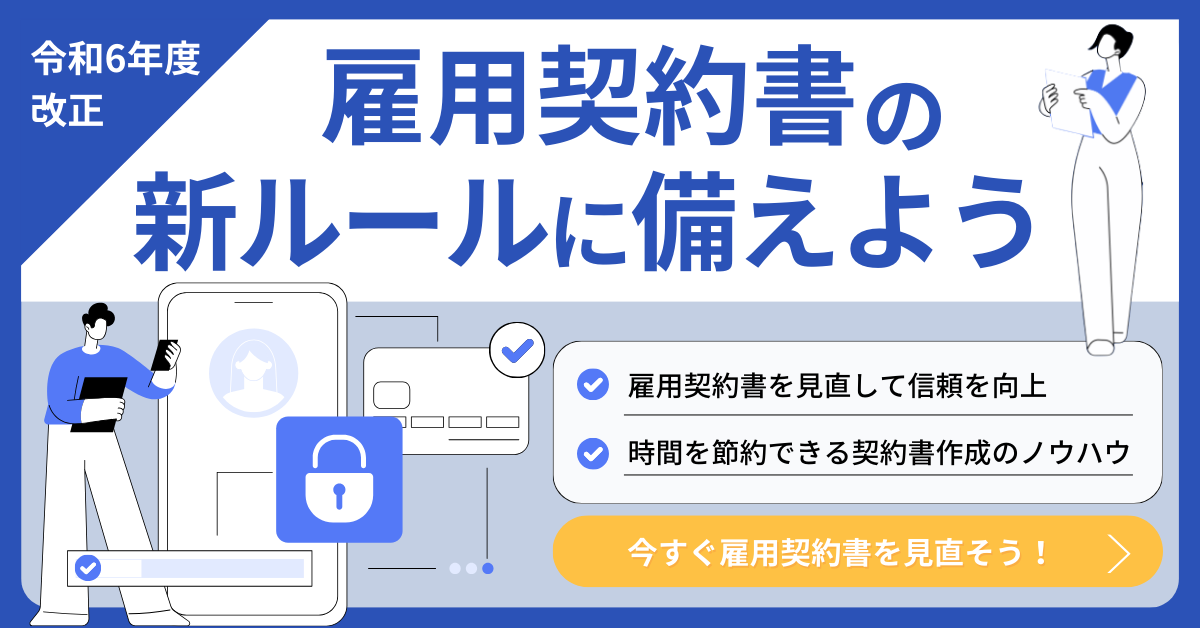
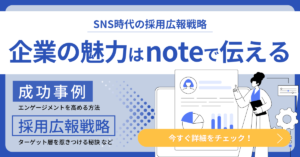
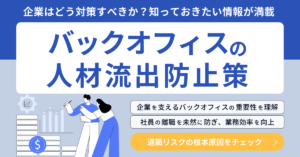
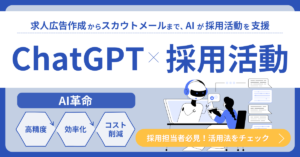
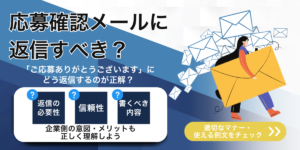
コメント