採用面接は、企業にとって最適な人材を見極めるための重要なプロセスです。
「採用面接 質問」ひとつで候補者の印象が決まったり、採用の成否を左右することもあります。
中小企業では特に一人ひとりの採用が企業全体に与える影響が大きいため、面接官は面接の質問内容に細心の注意を払う必要があります。
本記事では、中小企業の採用担当者向けに、採用面接で活用できる質問例やNG質問、面接官として押さえておきたいコツを専門的に解説します。
面接の導入で役立つアイスブレイクの質問から、人材を見抜く深掘り質問、オンライン面接ならではの注意点まで網羅しています。
採用面接の質を高め、優秀な人材の見極めに役立ててください。
面接をする目的とは
企業が採用面接を行う主な目的は、大きく分けて2つあります。それは「人材を見極めて採用のミスマッチを防ぐ」ことと、「自社の魅力を応募者に伝える」ことです
面接官はこの2つの役割を意識して面接に臨む必要があります。
面接官が担うべき役割
面接官には、短時間の面接で応募者のスキルや適性、価値観が自社に合っているかどうかを見極める重大な責務があります
履歴書や職務経歴書では分からない部分を質問を通して確認し、早期離職や戦力にならない人材の採用といったミスマッチを防ぐことが求められます。
例えば以下の観点で応募者を評価します。
- 経験・スキルの活かしやすさ:自社の業務で応募者の経験やスキルが役立ちそうか
- カルチャーフィット:自社の社風や価値観と合いそうか、求める人物像にマッチするか
- 意欲の高さ:志望動機が明確で入社意欲が高いか、長く活躍してくれそうか
- 条件の合致:給与や勤務条件などが応募者の希望と折り合うか
これらを総合的に判断し、自社に適した人材かを見極めます。
もし面接で適切に評価できなければ、採用後のミスマッチにつながり、早期離職や採用コストの無駄にもなりかねません
一方で、面接官は単に応募者を評価するだけでなく、自社に興味を持ってもらうPR役でもあります
応募者は面接で受けた印象を元に入社の意思決定をします。面接官自身が「会社の顔」であることを意識し、誠実で好印象な対応を心がけましょう
「この会社で働きたい」と思ってもらえるよう、自社代表として丁寧に向き合うことが大切です。
人材を見抜く採用面接質問一覧!
ここからは、面接官が候補者を見極めるために有効な質問をカテゴリ別に紹介します。
面接の序盤から深掘り質問まで、目的に応じた質問例を把握しておくことで、計画的に面接を進めることができます。
それぞれの質問の意図を理解し、適宜使い分けましょう。
アイスブレイクとしての質問
面接の冒頭では、応募者の緊張をほぐしリラックスしてもらうためにアイスブレイク(緊張緩和)の質問を活用します。
最初から本題に入るよりも、まずは世間話に近い簡単な質問で場の雰囲気を和らげると良いでしょう。
例えば次のような質問があります。
- 「本日は当社まで迷わずに来られましたか?」
- 「外は暑いですね。体調など大丈夫ですか?」
- 「今日はお休みとのことですが、朝はゆっくりできましたか?」
- 「オンライン面接は今回が初めてですか?」
これらははい・いいえで答えられるシンプルな質問から始めると効果的です
例えば「今日は電車で来ましたか?」と聞き、「はい」と答えたら「混み具合はいかがでしたか?」と続けることで、会話が弾みやすくなります
アイスブレイクでは基本的に選考評価には直結しない無難な話題に留め、応募者が安心して話せる空気づくりに徹しましょう
なお、緊張をほぐそうとするあまりプライベートに踏み込みすぎる質問(出身地や家族構成、休日の過ごし方など)は控えてください
雑談とはいえ、受け取り方によっては不快に感じられる可能性もあるため注意が必要です。
自己理解を深める質問
応募者自身の強みや弱み、性格傾向を把握するためには、自己分析や自己理解に関する質問が有効です。
こうした質問で、応募者が自分をどれだけ客観的に理解しているかを探り、人柄や価値観を評価します。
たとえば以下のような質問があります。
- 「あなたの長所と短所を教えてください。」
- 「周囲の人からはどのような人だと言われますか?」
- 「仕事で挫折した経験はありますか?どのように乗り越えましたか?」
- 「3年後(5年後)の目標やビジョンを教えてください。」
- 「どんな時にモチベーションが上がりますか?」
これらの質問を通じて、応募者の価値観や人柄が浮き彫りになります。
長所・短所の質問では自己認識の深さが分かり、挫折経験やモチベーションの源泉に関する質問からは、その人が何を大切にし、どう成長してきたかが見えてきます。
回答次第ではセクハラ・モラハラと取られかねない繊細なテーマでもあるため、聞き方には注意しつつ、仕事に関連づけて答えてもらうよう促すと良いでしょう。
たとえば「趣味やプライベートで打ち込んでいることは?」ではなく「これまで何かに熱中した経験はありますか?
それは仕事にどう活きていますか?」といった形で質問すると、より仕事観や価値観に結びつけた回答を引き出せます。
過去の経験と成果に関する質問
応募者のこれまでの職務経歴や実績を確認する質問です。
履歴書や職務経歴書に書かれている内容を踏まえて具体的に掘り下げることで、能力やスキルの裏付けを取ります。
重要なのは、何を聞き出したいのか明確にした上で質問することです。
専門用語を避け、誰でも理解できる言葉で尋ねるよう心がけます。
質問例としては次のようなものがあります。
- 「(自己紹介を兼ねて)これまでの経歴を簡単に教えてください。」
- 「前職で担当されていた具体的な業務内容は何ですか?」
- 「これまでで最も大きな成果を上げた経験と、その際に努力したことを教えてください。」
- 「業務でミスをしたことはありますか?そのときどのように対処しましたか?」
- 「仕事をする上でストレスを感じたのはどんな時ですか?」
こうした質問によって、応募者の実務能力や問題解決力を具体的なエピソードとともに把握できます。
例えば「成果を上げた経験」は、目標達成能力や主体性を知る手がかりになりますし、「ミスへの対処」は、失敗から学ぶ姿勢やリカバリー力を測る材料になります。
質問を投げかける際は、「○○の知識はどの程度お持ちですか?」「○○の経験は何年ありますか?」のように事実確認のクローズド質問も組み合わせると、客観的なスキルレベルも把握しやすいでしょう。
企業理解と意欲を測る質問
応募者の志望動機や自社への理解度、入社意欲を確認する質問です。
自社を選んだ理由や業界への関心度を尋ねることで、「なぜ当社なのか」を見極めます。
優秀な人材ほど複数社の選考を受けているため、志望度の高さは採用の重要な判断基準になります。
質問例をいくつか挙げます。
- 「数ある会社の中で、なぜ当社を志望されたのですか?」
- 「当社の商品(サービス)についてどう思われますか?」
- 「入社後に実現したいことや挑戦したい仕事は何ですか?」
- 「他社ではなく当社を選ぶことで得られるものは何だと考えますか?」
志望動機に関する回答からは、応募者の入社意欲の高さや企業研究の深さが読み取れます。
例えば「御社の○○というビジョンに共感した」「これまで培った△△のスキルを活かして御社の新規事業に貢献したい」といった具体的な回答であれば、しっかりと企業理解・自己分析ができている証拠です。
一方で抽象的な志望理由や他社でも当てはまるような回答だと志望度は高くないかもしれません。
面接官としては、「当社でなければならない理由」を掘り下げて聞くことで、応募者の本気度を測りましょう。
また、志望動機だけでなく「10年後、業界や当社はどうなっていると思いますか?」と未来志向の質問をすることで、業界への見識や当社で実現したいキャリアプランを持っているかも確認できます。
人間性とチームワークに関する質問
仕事はチームで進めることが多いため、応募者の協調性や対人スキルも重要な評価ポイントです。
そこで、人柄やチームワークに関する質問を通じて、職場での対人関係への適応力やコミュニケーション力を探ります。
ただしプライベートに過度に踏み込むとハラスメントと捉えられる可能性があるため、質問の仕方には配慮が必要です。
以下のような質問例があります。
- 「チームで協力して何かを成し遂げた経験はありますか?具体的に教えてください。」
- 「前職の上司や同僚から、あなたはどのように評価されていたと思いますか?」
- 「苦手なタイプの人はいますか?それはどんな人ですか?」
- 「チームで仕事をする上で心がけていることは何ですか?」
- 「職場で意見が対立したとき、どのように対処しますか?」
これらの質問から、応募者の対人姿勢や協調性が見えてきます。
例えば「チームで協力した経験」からはリーダーシップやフォロワーシップの傾向がわかりますし、「苦手なタイプ」への回答からは人間関係の許容範囲が伺えます。
上司・同僚からの評価について尋ねるのも有効で、自己評価とのギャップや客観的な人物像を知るヒントになります
なお、このような質問は答えにくいため、面接官の表情や口調を柔らかくするなど雰囲気作りに気を配り、答えやすい環境を整えることが大切です。
仕事に対する姿勢と適応力を見抜く質問
応募者が仕事観をどのように持ち、変化や困難にどう対応するかを確認する質問です。
入社後に活躍できる人材かどうかを見極めるため、働く上で大切にしていることやモチベーション維持の方法、変化への適応力などを質問します。
例えば次のような質問があります。
- 「仕事をする上で、大切にしている価値観は何ですか?」
- 「どんな時にやりがいを感じますか?」
- 「新しいことに直面したとき、どのように学習して乗り越えますか?」
- 「仕事で困難な課題にぶつかったとき、まず何を考えどう行動しますか?」
- 「変化の速い環境についていくために心がけていることはありますか?」
これらの質問は応募者の仕事に対する姿勢や適応力を評価する材料となります。
また、「困難への対処」についての質問からは、問題解決志向や粘り強さ、あるいは周囲への相談姿勢などが見えてきます。
変化への適応力については、「最近の業務で学んだ新しいスキルはありますか?」などと問うのも良いでしょう。
応募者の回答を深掘りする際は、「なぜそう思うのか?」「具体的には?」と理由や背景を尋ねるフォロー質問を入れることで、思考過程や感情の動きに着目できます。
これにより応募者の内面にある仕事観をより正確に把握し、自社にフィットする人材かを多角的に判断できます。
マネジメント能力についての質問
応募ポジションによっては、応募者のマネジメントスキルやリーダーシップを評価する必要があります。
特に管理職候補やチームリーダー級の採用では、これまでの部下・後輩指導経験や組織をまとめた経験について質問しましょう。
例えば以下のような質問が考えられます。
- 「チームを率いた経験はありますか?どのようにメンバーをまとめましたか?」
- 「部下や後輩を育成する際に心がけていることは何ですか?」
- 「目標に届かない部下がいた場合、どのように動機付けしますか?」
- 「チーム内でトラブルや対立が起きた時、リーダーとしてどう対処しましたか?」
- 「あなたの考える理想のマネジメントスタイルを教えてください。」
この種の質問では、応募者のリーダーシップ像や問題解決能力が浮き彫りになります。
例えば「チームを率いた経験」に対して「〇〇人のチームでプロジェクトを担当し、目標達成のために定期ミーティングと個別フォローを行いました」など具体的な回答があれば、計画性や統率力が感じられるでしょう。
「部下の育成」についての質問では、相手の目線に立って指導できるか、人材開発に意欲的かを見極めます。
マネジメント経験が浅い応募者であれば、「上司だったらどんな働きかけがあると自分のパフォーマンスが上がりますか?」と逆の立場から質問する方法もあります
この質問は自己の最適なマネジメント方法を聞くものですが、応募者がどんな環境で力を発揮できるかを知る手がかりになると同時に、将来マネジメントする際のヒントにもなります
管理職候補の場合、これらの回答から組織を牽引する力や課題対応力を評価しましょう。
転職理由や退職理由に関する質問
中途採用の面接では、応募者が前職を辞めた理由や転職を決意した理由を必ず確認します。
これは、入社後に同じような状況が起きた際にまた退職してしまうリスクがないか見極めるためです。
質問例として次のようなものがあります。
- 「前職を退職した理由は何ですか?」
- 「今回、転職を決意したきっかけは何でしたか?」
- 「これまで転職回数が多いようですが、その理由を教えてください。」
- 「次の職場に求める条件や重視している点を教えてください。」
これらの質問を通じて、応募者がどんな環境で不満を感じやすいか、仕事に対して何を重視しているかが分かります
たとえば「残業が多かった」「上司と合わなかった」「給与が低かった」など前職の不満点ばかりを挙げる場合、ネガティブな視点が強い可能性があります。
もちろん本音として否定的な理由があること自体は問題ではありませんが、あまりにも不平不満ばかりだと、入社後も同じように不満を抱えやすいかもしれません。
面接官としては、応募者が退職理由を語った後に、「では次の職場では何を実現したいですか?」とポジティブな展望も尋ねてみましょう。
前向きなキャリア目標や実現したいことを語れる応募者であれば、単なる不満退職ではなく成長のための転職である可能性が高まります。
また、転職理由を聞く際には表面的な回答だけでなく、「なぜそれが問題だと感じたのか?」など背景にも耳を傾けると、その人の価値観(例えばワークライフバランス重視、承認欲求の高さ等)が見えてきます。
いずれにせよ、退職理由・転職理由の質問では応募者の職業観や職場に対する期待を把握し、自社でそのニーズを満たせるかを判断することが重要です。
面接官が採用面接で活用する状況別質問例
応募者の属性や経歴によって、効果的な質問内容は変わります。ここでは応募者の状況別に、面接官が活用できる質問例を紹介します。
新卒採用と中途採用では聞くべき内容が異なりますし、未経験業界への転職やキャリアブランクがある場合には配慮すべきポイントがあります。
それぞれのケースでどのような質問が適切か見ていきましょう。
新卒の採用面接の場合
新卒採用では応募者はまだ学生であり、社会人経験がないため具体的な職務実績を問うことはできません。
代わりに、学生時代の経験や人となりが分かる質問を中心に据えます。
新卒向け面接での質問例は次の通りです。
- 「学生時代に力を入れて取り組んだことは何ですか?」
- 「大学(学部)を選んだ理由と、そこで学んだことを教えてください。」
- 「学生生活で苦労した経験はありますか?それをどう乗り越えましたか?」
- 「ゼミや研究テーマについて教えてください。その中で何を学びましたか?」
- 「チームで協力して何か成し遂げた経験はありますか?」
これらの質問により、応募者の人柄やポテンシャルを見極めます
たとえば「学生時代に力を入れたこと(通称:ガクチカ)」への回答からは、努力する姿勢や主体性が感じられます。
また「苦労した経験」は困難への対処法や粘り強さを測る機会です。
新卒の場合、職務経験がないぶん将来性や基本的な素養を評価することになります。
「あなたにとって仕事とは何ですか?」といった質問を投げかけ、仕事観や社会人になる意識を確認するのも良いでしょう。
中途の採用面接の場合
中途採用面接では、前職での経験や退職理由を詳しく確認します。
特に退職・転職理由は必ず聞いておくべき項目です。
なぜなら、前職で退職に至った要因が当社でも起こり得るかを知り、早期離職のリスクを判断するためです。
中途採用の応募者によくある質問例は以下の通りです。
- 「前職を退職した理由は何ですか?」
- 「今回転職しようと思った経緯を教えてください。」
- 「これまでに転職を繰り返した理由があれば教えてください。」
- 「前職での具体的な業務内容を教えてください。」
- 「リーダーやマネジメントの経験はありますか?具体的にどんなチームを率いましたか?」
- 「後輩を育成する立場でしたか?心がけていたことは何ですか?」
- 「あなたの弱みは何で、それをどのように克服してきましたか?」
- 「前職で上司や同僚からどのように評価されていましたか?」
- 「転職先に求める条件や期待することは何ですか?」
中途では、前職に関する質問から応募者の仕事上の価値観や不満要因を探ります。
例えば「退職理由」が「人間関係の悪化」だった場合、どんな状況でそうなったのか深掘りすることで、応募者が苦手とする組織風土が見えるかもしれません。
一方「新しいチャレンジをしたい」という前向きな転職理由であれば、成長意欲が感じられます。また、前職の業務内容や成果を聞くことで即戦力としてのスキル適合を判断できます。
リーダー経験や育成経験の有無も、将来的にマネジメント層として期待できるかを見る指標になります。
中途面接では、応募者が前職についてネガティブな発言ばかりしていないかも注視しましょう。
「残業が多かった」「上司と合わなかった」等の否定的な話だけでなく、「こういうキャリアを実現したい」「新しい分野で挑戦したい」といったポジティブな展望が語られると望ましいです
もちろん本音を引き出すことも大切なので、最初は自由に話してもらい、最後に「では当社でどんなことを達成したいですか?」と転職後の希望を確認するとバランス良く評価できるでしょう。
未経験業界への転職の採用面接の場合
応募者によっては、これまで経験のない業界や職種に挑戦したいというケースもあります。
未経験分野への転職希望者の場合、その決断に至った理由や熱意を確認することが重要です。
加えて、現時点でどれだけ新分野への準備や勉強をしているかも見極めましょう。
- 「これまでと全く異なる仕事を選んだ理由は何ですか?」
- 「なぜこの未経験業界に興味を持ったのですか?きっかけを教えてください。」
- 「異業種に転職するにあたり、不安な点や克服したい課題はありますか?」
- 「前職までの仕事で、誇れる成果は何ですか?それは今後どう活かせると思いますか?」
- 「これまでに大きな課題に直面したことは?どう乗り越えましたか?」
これらの質問では、応募者の向上心や適応力、転職への本気度を探ります。
例えば「異業種を選んだ理由」については、「昔から興味があった」「○○の分野で社会に貢献したい」など明確な動機が語れるかどうかがポイントです。
ただなんとなく待遇が良さそうだから…という程度では、入社後にギャップで辞めてしまう恐れもあります
また、「未経験への不安」について率直に話してもらうことで、こちらも適切なサポート体制を検討できますし、応募者自身がどれだけ現実を見据えているかも分かります。
さらに、「誇れる成果」や「課題の克服経験」を聞くのは、前職までの経験から学んだことを新天地で活かそうとしているかを見るためです
未経験とはいえ、過去の仕事で培った汎用的なスキル(コミュニケーション、課題解決力など)は必ずあります。
逆に未経験ゆえに給与や勤務条件だけに惹かれていないか、漠然とした憧れだけでないかもチェックします
面接官は応募者の熱意を評価しつつ、現実的な適応力と計画性を持っているかどうかを見極めると良いでしょう。
キャリアにブランクがある方の場合
応募者の中には、何らかの事情で職歴に空白期間(ブランク)がある方もいます。
例えば「出産・育児のため数年間仕事を離れていた」「体調面の理由で一時退職していた」など様々なケースがあります。
ブランクがある方への面接では、差し支えない範囲でその理由や期間中の状況を確認し、現在の就業意欲を探りましょう。
- 「前職を辞めてから、しばらくお仕事をされていないようですが、その理由を教えていただけますか?」
- 「ブランクの期間中はどのように過ごされていましたか?」
- 「正社員ではなく非正規(パート・派遣など)を選ばれていた時期がありますが、その理由は何でしょうか?」
- 「現在、また働こうと思ったきっかけやお気持ちについて教えてください。」
- 「今後、身につけたいスキルや挑戦したいことはありますか?」
ブランクの理由について尋ねる際は、デリケートな事情に配慮しつつ必要な情報を得ることが大切です。
直接的に「なぜ働いていなかったのですか?」と詰問調にならないよう、「差し支えなければ」で前置きしたり、「○年間ほどご家庭の事情とのことですが…」と履歴書の記載に沿って聞くと良いでしょう。
また、その期間の過ごし方を聞くことで、ブランク中も何かスキルアップに努めていたか、人脈を維持していたかなどが分かります。
例えば「語学の勉強を続けていました」「資格取得の勉強をしていました」であれば、向上心が感じられますし、「育児に専念していました」でも計画性やマネジメント力(家庭運営も一種のマネジメントです)が培われているかもしれません。
さらに、現在働く意欲がどの程度あるのかも確認します。ブランクの理由だけでなく、「今また働きたいと思ったのはなぜか?」を聞くことで、復職への前向き度が分かります
例えば「子育ても一段落し、キャリアを取り戻したい」「体調も万全になり、再びチャレンジしたい」といった回答なら意欲十分と言えるでしょう。
ブランクがあっても有能な人材は多いので、先入観を持たず意欲とポテンシャルを評価しましょう。
採用面接でやってはいけないNG質問
採用面接では聞いてはいけない質問、いわゆるNG質問が存在します。
それらは応募者のプライバシーや人格権を侵害したり、法的に差別とみなされる恐れがあるものです。
ここでは特に注意すべき質問カテゴリとその理由を解説します。「こんなことまで聞いて良いのだろうか?」と迷ったら、業務上必要な情報かどうかを基準に判断しましょう。
必要性が薄く個人的な内容であれば避けるのが無難です。
個人情報に関する質問
応募者本人の家族構成や資産状況など、仕事の適性に直接関係のない個人的な情報を尋ねるのは不適切です。
例えば「ご両親の職業は?」「ご家族の収入は?」といった質問は、応募者の能力や職務適性とは無関係であり、選考に必要ありません。
最悪の場合、そうした情報によって合否を判断したと受け取られれば差別とみなされる可能性もあります。
家族の職業や家柄などは就職差別の典型例として厚生労働省の指針でも挙げられています。
面接官は応募者の適性・能力のみで評価する姿勢を示すためにも、家族構成や家庭環境、資産状況などプライベートな領域には踏み込まないようにしましょう。
どうしても業務上必要な場合(例:海外赴任があり家族帯同が可能か確認する等)でも、理由を説明した上で慎重に質問することが求められます。
年齢に関する質問
応募者の年齢を直接尋ねることも基本的にはNGです。
日本では雇用対策法により募集・採用で年齢制限を設けることは原則禁止されています。
特に女性に対して年齢を聞くことはセクハラと捉えられる場合もあります。
年齢よりも経験やスキルを重視する姿勢を示し、万一採用基準上どうしても年齢層を気にする場合でも、「〇〇の経験年数」を尋ねるなど間接的な表現に留める配慮が必要です。
一般に、年齢に関連した質問(「ご結婚は何歳で?」「定年まであと何年働けるか知りたいので年齢を…」等)はしないのが無難と言えます。
宗教に関する質問
信教の自由は憲法で保障された権利であり、応募者の宗教や信条に関する質問は厳に慎むべきです。
例えば「何か宗教を信仰していますか?」「宗教上休まなければならない日がありますか?」といった質問は、宗教を理由とする差別につながりかねません。
採用面接で宗教を聞くこと自体が応募者に不安を与え、「宗教によって合否を決めるのか?」という疑念を抱かせてしまいます。
業務上、宗教上の理由で配慮が必要な場合(例えばイスラム教徒なら礼拝の時間確保が必要など)は、「業務上特別な配慮が必要なことはありますか?」と配慮の必要有無だけを確認するに留めましょう。
信仰の詳細を詮索する必要はありません。
面接官個人の興味であっても宗教の話題は避け、政治・宗教・スポーツの「3S」は面接のタブーと覚えておくと良いでしょう。
性別に関する質問
応募者の性別に関連して、差別的と取られる質問は厳禁です。
男女雇用機会均等法の観点からも、性別による待遇差や採用差別は許されません。
これらは将来の妊娠・出産で離職するかを懸念しての質問と受け取られ、明確に差別行為となります。
男性に対しても「男性だから転勤大丈夫ですよね?」など固定観念に基づく質問は避けるべきです。
基本的に、性別にかかわらず同じ基準・質問で評価することが、公平な採用の大前提です。
どうしても確認したい事項(例えば力仕事で体力要件がある場合など)は、「一定の体力が求められますが問題ないですか?」と性別に言及せず質問するようにします。
面接官は自分の中に無意識のバイアスがないか注意し、「男性だから・女性だから」という先入観を排除して接しましょう。
健康状態に関する質問
応募者の健康状態や病歴について深入りする質問もNGとされています。
病歴や持病、メンタルヘルスの状況などは極めてプライベートな情報であり、不用意に聞くことはプライバシー侵害になりかねません。
例えば「過去に大きな病気をしたことがありますか?」「現在通院していますか?」などの質問は、能力と直接関係が無いため避けましょう。
企業が採用前に健康情報を知りたい場合は、内定後に健康診断書を提出してもらうなど正式な手順を踏むのが通例です。
ただし、業務に支障が出る可能性がある場合には限定的な確認は許容されます。
例えば「この仕事は高所作業がありますが、高所恐怖症などは大丈夫でしょうか?」のように、業務遂行上必要な範囲に限って理由を添えて尋ねるのは問題ないとされています。
また、障がいの有無や必要な配慮については、応募者自ら申し出るケースもあります。
その場合も「何か配慮が必要なことがあれば教えてください」という聞き方にとどめ、深堀りしすぎないよう注意します。
いずれにせよ、健康に関する話題は慎重に扱い、応募者が答えたくない情報を無理に引き出さないことが大切です。
ライフスタイルに関する質問
応募者の私生活や価値観に関わる質問で、業務に直結しないものは避けましょう。
例えば「お酒は飲みますか?タバコは吸いますか?」「休日は何をして過ごしていますか?」といった質問は、一見雑談のようですが答えによって偏見を持つ危険があります。
喫煙の有無は社内ルールで禁煙の場合に確認する程度なら良いですが、単なる興味本位で聞くのは控えるべきです。
また、「人生観や座右の銘は?」など一見ポジティブな質問も、思想信条の領域に踏み込むため注意が必要です。
人生観や信条に関する回答を合否判断に使えば差別にあたり得ます。
企業文化とのマッチを見る目的で価値観に触れる質問をしたい場合は、「仕事をする上で大切にしていることは?」程度に留め、個人の信条そのもの(尊敬する人物や好きな言葉などを詮索しないようにしましょう。
さらに、政治の話題や最近の社会問題への意見なども避けるべきです。
これらは応募者の思想を探ることになり、「圧迫面接」と受け取られる可能性も高いです。
基本的に、応募者の私生活は本人の自由であり、職務に関係のない部分については質問しないことがプロの面接官のマナーと言えます。
面接官が知っておくべき質問のコツ6選
効果的な採用面接を行うには、質問内容そのものだけでなく質問の仕方や展開のさせ方にもコツがあります。
ここでは面接官がぜひ意識したい6つのポイントを紹介します。
どんなに良い質問例を用意しても、使い方を誤れば応募者の本音や魅力を引き出せません。
質問のテクニックを磨いて、限られた時間で最大限の情報を得ましょう。
オープンエンドの質問を活用する
質問には「はい/いいえ」で答えられるクローズドクエスチョンと、自由に答えを広げられるオープンクエスチョンがあります。
面接では両方を使い分けることが大切ですが、特に応募者の考えや人柄を深く知りたい場面ではオープンな問いかけを意識しましょう。
例えば「〇〇は可能ですか?」(クローズド)と聞く代わりに、「〇〇についてどう思いますか?」(オープン)と尋ねるだけで、相手は自分の言葉で説明する必要が出てきます。
オープンクエスチョンは「なぜ」「どのように」「何を」のように5W1Hで始まる質問に多く、回答者の考えや感情、行動の理由を掘り下げるのに適しています。
一方、クローズドクエスチョンは事実確認に有効で、「はい/いいえ」や「AかBか」で端的に答えられる質問です。
面接序盤の緊張が高いときはクローズドで答えやすくし、中盤以降はオープンで深掘りする、といった組み合わせが有効です。
例えば志望動機を聞く際、「当社を志望した理由を教えてください(オープン)」→「当社の製品は使ったことがありますか(クローズド)」→「それについてどう感じましたか(オープン)」という流れで質問すれば、応募者の自由な表現を引き出しつつ要点の確認もできます。
オープンエンドの質問を上手に活用し、応募者に存分に語ってもらうことで、表面的でない本音や個性が見えてくるでしょう。
具体的なエピソードを求める
応募者の回答が抽象的な場合や、もっと深く知りたいときは、「具体的には?」とエピソードを求める質問で深掘りしましょう。
一問一答で次々と新しい質問をするより、一つの回答に対して連続で追加質問する方が、応募者の価値観や本音を引き出しやすくなります。
例えば応募者が「私の強みはリーダーシップです」と答えたら、「なぜそう思うのか、具体的な場面を教えてください」と聞くことで、過去のエピソード(部活でキャプテンを務めた経験など)を話してもらえます。
「なぜ?」「具体的には?」「どう感じましたか?」といった切り口でさらに一歩踏み込んで尋ねることで応募者の思考プロセスや感情の動きが見えてきます。
この深掘りによって、単なる表面的な受け答えではなく、応募者の価値観や人柄が浮かび上がります。
また、具体的なエピソードを聞くことは事実確認と裏付けにもなります。
時間に限りがある面接ですが、重要なポイントについては腰を据えて深掘りすることで、応募者理解の精度が上がり、採用ミスマッチの防止につながるでしょう。
行動ベースの質問をする
応募者の本当の姿を知るには、過去の行動に基づく質問(コンピテンシー面接の手法)が有効です。
人は具体的な行動を語るときに自分の考え方や価値観が表れます。
例えば「もし〇〇な状況ならどうしますか?」という仮定の質問より、「過去に〇〇な状況でどう行動しましたか?」と聞く方が、その人の実際の行動特性が分かります。
これを体系化したのがSTARメソッドと呼ばれる手法で、Situation(状況)→Task(課題)→Action(行動)→Result(結果)の順にエピソードを掘り下げる質問フレームワークです。
たとえば「直近のプロジェクトで一番苦労したことは?」(Situation)→「その時あなたの役割は何で、何が課題でしたか?」(Task)→「具体的にどんな行動を取りましたか?」(Action)→「結果どうなりましたか?」(Result)のように順を追って質問します。
このように行動ベースの質問をすると、応募者は経験を振り返り深く考える必要があり、その過程で思考の背景や意図が見えてきます。
従来の面接が主観的な印象評価に陥りがちなのに対し、コンピテンシー面接は事実に基づき客観的に評価できるメリットがあります。
具体例として、「目標達成が難しいと感じたとき、何が課題で、どう解決しようとしましたか?」と聞けば、課題分析力や粘り強さが判断できますし、「リーダーとしてチームをまとめた経験は?」と聞けば、リーダーシップスタイルや対人スキルが見えてきます。
行動ベースの質問は少し高度ですが、応募者の本質を客観的に評価しやすくなるため、是非取り入れてみてください。
ポジティブな視点で質問する
面接では応募者の弱みや失敗経験を聞く場面もありますが、できるだけポジティブな切り口で質問することを心がけましょう。
これは応募者に答えやすくして本音を引き出す効果もあります。
例えば「これまでの失敗で一番ダメージを受けたのは何ですか?」とネガティブ一点張りで聞くのではなく、「失敗から何を学びましたか?」と学びや成長にフォーカスした聞き方をすると、応募者も前向きに語りやすくなります。
弱みの質問でも「弱みを教えてください」だけでなく、「それを今後どう克服しようとしていますか?」と付け加えると、単にネガティブ要素を暴くだけでなく前向きな姿勢も評価できます
また、質問のトーンも重要です。同じ内容でも、責めるような口調ではなく穏やかで励ますような口調で聞けば、応募者は安心して率直に話せます。
ポジティブな視点とは、応募者の可能性や長所に注目することです。
「なぜ前職を辞めたのか?」だけでなく「次に何を実現したいのか?」も尋ねる、「苦手なことは?」だけでなく「どう工夫して乗り越えているか?」も聞く、といった具合です。
こうすることで、応募者自身も自分の中の前向きな部分に気づき、アピールしやすくなります。
面接官は評価者ではありますが、敵対的な質問で追い詰める必要はありません。
むしろ応募者の持ち味をうまく引き出すサポーター的な姿勢で、建設的な質問を投げかけましょう。
その方が結果的に人物評価もしやすくなり、お互いにとって有意義な面接になります。
候補者の価値観や文化適応力を確認する
会社ごとに社風や求める人物像は異なります。そこで、応募者の価値観や企業文化への適応力を探る質問も重要です。
具体的には、「働く上で大切にしている価値観は?」「理想の職場環境とは?」などの質問で、応募者の仕事観や職場観を引き出します。
たとえば「仕事で最もやりがいを感じるのはどんな時ですか?」という質問から、その人が重視する価値観(達成感なのか、人の役に立つことなのか、学びなのかetc)が分かります。
また、「どんな職場だと力を発揮できますか?」と尋ねれば、応募者が合う文化や上司像、チームの雰囲気などが見えてきます。
回答内容を自社の環境と照らし合わせて、カルチャーフィットの度合いを判断しましょう。
たとえば応募者が「自主性を重んじて任せてもらえる環境が良い」と言えば、自社がトップダウン文化の場合ミスマッチになるかもしれません。
逆に「チームワークを大切にしています」という人なら、協調性が求められる社風には合うでしょう。
価値観の質問は答えに優劣はありませんが、自社との相性を見極める材料になります。
さらに、「多様な人がいる職場についてどう思うか?」などダイバーシティへの考え方を問うのも、最近では重要な視点です。候補者が偏見なく柔軟に対応できるかを見るためです。
いずれにしても、これらの質問で得た回答をもとに、「この人はうちの会社で活躍できそうか?長く働いてくれそうか?」を判断しましょう。
スキルや経験だけでなく、価値観のマッチ度は定着や活躍に直結するため、面接官が必ず確認しておきたいポイントです。
アイスブレイクのための質問でリラックスさせる
緊張して実力を発揮できない応募者が出ないよう、アイスブレイク質問の活用は面接官の重要な役割です。
冒頭で紹介したように、簡単な世間話や答えやすい質問から入り、場の空気を和らげましょう。
したがって、面接官は意図的に笑顔で挨拶し、「今日はお越しいただきありがとうございます。少しリラックスしてお話ししましょうね」と声をかけるなどして、良い雰囲気づくりを意識します。
アイスブレイク質問自体は先述の通り天気や道順など些細な内容で構いません。
大事なのは応募者が「評価される場だ」と構えている心をほぐし、自然体で話せる状態にもっていくことです。
このため、面接官は相槌や頷きを多めにし、穏やかな口調で進めます。決して威圧的な態度をとったり、圧迫面接のような手法に走ってはいけません。
昨今は面接での評判がSNS等ですぐ拡散し企業イメージに影響する時代ですから、圧迫面接は百害あって一利なしです。
むしろ「自分を出せた」「話しやすかった」と応募者に感じてもらえれば、会社への志望度が上がる効果すら期待できます
アイスブレイクは面接の最初だけでなく、途中で応募者が極度に緊張している様子なら適宜雑談を挟むなど柔軟に活用してください。
リラックスした雰囲気の中でこそ、応募者の本当の人柄や考えが聞き出せるものです。
オンライン面接で面接官が注意するポイント
近年はZoomやTeamsなどを使ったオンライン面接も一般的になりました
対面の面接と比べて勝手が違う部分も多いため、面接官は事前に注意点を押さえておきましょう。
オンラインだからこそ気を付けたいポイントとスムーズに進行するコツを以下にまとめます。
環境の整備
オンライン面接ではまず、面接環境を整えることが基本です。
面接官自身はできるだけ静かで明るい個室や会議室から参加し、周囲に人が出入りしたり騒音が入ったりしない環境を確保しましょう。
オフィスの自席などで行うと、後ろを他の社員が通ったりホワイトボードの機密情報が映り込んだりするリスクがあります。
また通信環境も重要です。
Wi-Fiの電波が弱い場所は避け、可能なら有線LAN接続にして通信を安定させます。
面接開始前にマイクとカメラ、音声のチェックを行い、スムーズに接続できるよう準備しましょう。
応募者への案内も早めに行うことが大切です。
アクセスURLや使用ツール、必要なインストール手順などは余裕をもって伝え、不安なく面接に臨めるよう配慮します。
オンライン面接は手軽な反面、直前案内だと応募者が戸惑うこともあるので注意しましょう。
面接官も開始5分前にはログインして待機し、時間になったらすぐ入室するなど、対面以上に時間厳守で臨むことが信頼につながります。
時間を守りスムーズに進行する
オンライン面接ではお互いの距離感が掴みにくいため、時間配分と進行管理を普段以上に意識します。
まず指定した開始時間は必ず守り、遅れないようにしましょう。
仮に通信トラブルなどで遅れる場合は、すぐにメールや電話で連絡を入れます。
対面と違い、待合室で様子を見ることができないため、時間通りに始まらないと応募者は不安になります。
ですから、事前に大まかな質問リストや流れを決めておき、滞りなく話題を切り替えていくことが重要です。
必要以上の間(沈黙)が続くとオンラインでは対面以上に気まずく感じるものです。
メモを取る際もあまり長時間沈黙しないよう、「少々メモを書き留めますね」と断ってから手短に書くなど工夫します。
時間管理として、面接の冒頭に「本日の面接は〇〇分程度を予定しております」と伝えると応募者もペース配分しやすくなります。
予定時間が迫っている場合は、「お時間も残り◯分ほどですので、最後の質問に移ります」といった声かけをして、時間内に面接を終えられるようコントロールしましょう。
オンラインでは次の予定(別の会議など)が詰まっているケースも多いため、対面以上に時間厳守とスムーズな進行が求められます。
カメラと目線の位置を調整する
オンライン面接ではカメラ映りと目線にも注意が必要です。
対面では目が合っているか自然に分かりますが、オンラインではつい画面上の相手の映像を見てしまい、カメラ目線から外れてしまいがちです。
そこで、カメラの位置は目線の高さに合わせ、できるだけカメラを見るよう心がけましょう。
ノートPCの場合、PCを台などで少し持ち上げてカメラを顔の正面にもってくると効果的です。また、複数モニターを使用している場合は注意が必要です。
資料を見るために別画面に視線を移すと、応募者からは横を向いているように見えてしまいます。話すときだけでも必ずカメラのあるモニターを見るように意識してください。
さらに、マイクの位置も確認します。
マイクから遠かったり指向性マイクが自分の声を拾えていないと、応募者に声が届きづらくなります。
カメラ映りに関しては、照明も大切です。逆光にならないよう明るい光を顔に当て、表情が見えやすいようにします。
笑顔や頷きなど非言語のリアクションはオンラインでは伝わりにくいため、はっきり映る環境を整えましょう。
こうした工夫により、対面に近いアイコンタクトや臨場感を出すことができます。
リアクションは大きめにする
オンラインではお互いの表情や仕草が伝わりにくいため、面接官のリアクションを普段より大きめにすることを意識しましょう。
対面であれば細かな相槌や微笑みでも相手に伝わりますが、画面越しだと気づかれないことがあります。
そこで、頷く動作は少しオーバーに、笑顔もいつも以上にハッキリと、声のトーンも明るめに心がけるとちょうど良いくらいです。
例えば応募者の発言に共感した時は、画面に向かってはっきり頷き、「なるほど」「おっしゃる通りですね」と声に出して反応すると良いでしょう。
沈黙で頷くだけだと相手には伝わらず、不安にさせてしまう場合があります。オンラインではお互いに表情が見えづらいため、言葉で合いの手を入れることも効果的です。
「はい」「ええ」「そうですよね」と適度に相槌を打ち、しっかり聞いていることを伝えます。
また、カメラ目線で笑顔を見せると、応募者からはアイコンタクトされているように感じ安心します。
逆に無表情で聞いていると、画面越しでは冷たく映り「反応がなくて怖い」と感じさせてしまうかもしれません。
多少誇張してでも豊かなリアクションを示すことで、オンライン面接の無機質さを和らげ、応募者に安心感を与えることができます。
注意深くメモを取る
面接中にメモを取ること自体は必要ですが、オンラインではメモの取り方にも配慮しましょう。
キーボードでタイピングしてメモを取る場合、その音が相手に聞こえてしまうことがあります。
カチャカチャという打鍵音は、応募者に「ちゃんと聞いているのかな?」という不安を与えかねません。
ペンで書く音はさほど気になりませんし、タイピングほど相手の注意を削ぎません。
どうしてもPCでメモを取りたい場合は、静音キーボードを使うか、ミュートにして一気に打つなどの工夫をします。
また、メモに集中しすぎて無言の時間が長くならないよう注意が必要です。対面なら書いている様子が見えるので伝わりますが、オンラインではただ下を向いて黙っているだけに映りかねません。
「少々メモしていますのでお待ちください」と一言断りを入れるだけでも随分印象が違います。
さらに、カメラから顔を外して書く場合は、終了後に「先ほどメモを取っていました」と伝えると丁寧です。
オンライン面接では画面に映らない手元の状況が相手に伝わらないため、何をしているか分からない時間をなるべく作らないことがポイントです。
適宜「メモしています」と説明しながら、応募者の話を遮らないタイミングで手短にメモを取るよう心がけましょう。
音声等のトラブルがないか適宜確認する
オンライン面接では、音声や映像のトラブルが発生していないか、面接官側がリードして確認することも大切です。
開始時に「映像と音声、大丈夫でしょうか?」とお互いにチェックするのはもちろん、面接中も違和感を覚えたら遠慮なく確認しましょう。
例えば応募者の声が急に聞こえにくくなったり、自分の話に相手が反応しなくなった場合、通信が乱れている可能性があります。
そのまま進めずに「少し音声が途切れているようです。聞こえていますか?」と声をかけます。
万一途中で接続が切れてしまったら、すぐに電話やメールでフォローしてください。「ただいま接続が切れたようです。
事前に電話番号を共有し、何かあれば電話でやり取りする段取りを決めておくと安心です。
また、画面共有を使う場合もうまく表示できているか確認します。「資料は見えていますでしょうか?」と尋ねて問題ないことを確かめてから説明に入ります。
オンライン面接では技術的トラブルが付きものと考え、慌てず対処することが大事です。
面接官が落ち着いて「少しお待ちくださいね」と対応すれば、応募者も落ち着いて対処できます。
逆に何もフォローがないと応募者だけが取り残され、不安と焦りでパフォーマンスを発揮できなくなってしまいます。
面接官はホストとして、音声・映像の状況に気を配りながら進行しましょう。
適宜「はい、大丈夫です」「ありがとうございます、よく聞こえています」とコミュニケーションを補助することで、トラブルを最小化できます。
採用面接を実施する面接官に関するよくある質問
最後に、採用面接を担当する面接官からよく寄せられる疑問や悩みにQ&A形式でお答えします。
初めて面接官を務める方や、面接の進め方に不安がある方はぜひ参考にしてください。
面接でキラー質問とは何ですか?
キラー質問とは、回答次第で採用可否に大きく影響を与える重要な質問のことです。
いわば「決定打」となる問いであり、応募者の本音や核心を引き出す目的で使われます。
例えば「あなたがこの会社に絶対必要な人材だと断言できる理由は何ですか?」といった質問は、答えによって合否が左右される可能性があります。
キラー質問はその名の通り答えによっては“致命傷”となり不採用になることもあるため、面接官にとっては諸刃の剣です。
使い所と使い方に注意が必要でしょう。
効果的なキラー質問としては、「当社で成し遂げたいことは何ですか?それが実現できない場合どうしますか?」など、入社後のビジョンと覚悟を問うものがあります。
回答に説得力がなかったり覚悟が不足していると判断されれば不採用となり得ます。
一方で優秀な応募者であれば熱意のこもった回答が期待でき、見極めに役立ちます。
また、「あなたにとって仕事とは?」のように価値観の本質に迫る質問もキラー質問になり得ます。
いわゆる圧迫的なキラー質問(例:「あなたを動物に例えると?」など意味を図りかねる質問)は、緊張を高めすぎ本来の実力を出させない恐れがあります。
面接官はあくまで応募者の本質を見抜くためにキラー質問を使うのであって、意地悪をする意図で使うべきではありません。
適切な場面で1つか2つ、本質を問う鋭い質問を用意し、公平に評価するようにしましょう。
面接で逆質問すべき質問は?
逆質問とは、面接終了間際に面接官から「何か質問はありますか?」と尋ね、応募者が企業側に質問を返す場面のことです。
逆質問の時間は応募者にとって会社理解を深めるチャンスであり、同時に面接官にとっては応募者の関心度や思考力を測る機会でもあります。
では、応募者にどんな逆質問をしてほしいか(=応募者は何を聞くべきか)という視点でお答えします。
好印象な逆質問の例としては
- 仕事の内容に関する質問:「入社後、まず任されるプロジェクトはどのようなものになりますか?」や「配属先のチームの雰囲気や課題はどのようなものですか?」
- 成長機会に関する質問:「御社で5年後10年後に身につくスキルやキャリアパスを教えてください」や「研修制度や自己啓発支援はどのようなものがありますか?」
- 企業文化に関する質問:「社員の皆さんが大切にしている価値観は何でしょうか?」や「御社で活躍している方に共通する特長はありますか?」
これらは建設的で前向きな質問です。面接官としては、こうした質問が出ると応募者の本気度や事前準備の深さを感じ、好印象を持ちます
逆にNGな逆質問もあります。
例えば「ホームページに書いてある情報」をそのまま質問するのは準備不足の印象になりますし、「残業はありますか?」「有給はどれくらい取れますか?」など待遇面ばかり気にする質問ばかりだと、働く意欲より条件重視かと懸念されます
面接官としては、応募者が逆質問で何を問うかを観察しつつ、真摯に回答することが求められます。
よくある逆質問として、「御社の課題は何だとお考えですか?それに対して新人に期待することは?」といったものもあります。
この場合、会社の現状や展望を率直に伝えつつ、応募者が入社後どんな役割を担えるかを一緒に考える機会にもなります。
総じて、応募者には積極的に逆質問してもらうのが望ましく、その内容から熱意や理解度を感じ取ることができます。
面接官は丁寧に答えることで応募者の不安も解消し、より入社意欲を高めてもらえるでしょう。
採用面接でメンタルに関する質問はだめ?
メンタルに関する質問、具体的には応募者の精神疾患の有無や過去のメンタル不調などを直接尋ねることは、基本的にNGと考えましょう。
これは前述の健康状態の項目と重なりますが、メンタルヘルスは非常にデリケートな個人情報です。
面接の場で「うつ病になったことはありますか?」などと聞くのは、応募者のプライバシー侵害に当たる可能性が高く、差別的とも受け取られかねません。
精神疾患を理由に不採用にすることは職業安定法などに抵触する恐れもあります。
企業としてどうしても知りたい場合は、内定後の健康診断や自己申告で確認する手段がありますし、面接の段階で触れるべきではありません。
もし業務上必要な範囲で確認するなら、「この仕事はストレスの多い場面がありますが、大丈夫ですか?」程度の間接的な聞き方に留めるべきです。
それでも応募者が「現在通院中で…」など答えてきた場合には、それ以上深堀りせず、「必要な配慮があればおっしゃってくださいね」と伝えるくらいにとどめます。
繰り返しになりますが、採用面接では応募者の適性と能力にフォーカスし、メンタルの強さ弱さを推し量るような質問は避けるのが原則です。
「この人はメンタル弱そうだ」などと主観で判断せず、例えばストレス耐性を見るなら「ストレスを感じた仕事はありますか?」と経験を聞く程度にしましょう。
それで十分判断材料は得られますし、それ以上踏み込む必要はありません。万一メンタル面で配慮が必要な場合は、採用後に産業医面談などを設定すれば良い話です。
面接段階では不適切な質問をしないことを最優先に心がけましょう。
採用面接で気になった質問をメールで聞くのはあり?
(質問)面接後に「あのことを聞き忘れた」と思った場合、後日応募者にメールで質問しても良いでしょうか? という趣旨の疑問ですね。
結論から言えば、基本的には避けた方が良いでしょう。面接はあくまでその場で完結する公式の選考プロセスです。
後から個別に質問をメールで送るのは、公平性の観点でも望ましくありません。
もし面接官側が重要な確認事項を聞き忘れた場合は、追加の面接や電話連絡でフォローするのが通常です。
メールで質問すると、応募者によっては慎重に文章を練って回答してくるでしょうし、リアルタイムのコミュニケーションではなくなります。
面接での臨場感をもって答えてもらうという当初の目的から逸れてしまいます。
加えて、応募者に余計な負担や緊張を与えてしまうかもしれません。
採用選考中に突然メールで質問が届けば、「早く答えなければ」「どう回答すれば評価が下がらないか」など気を揉ませてしまうでしょう。
もし面接官として本当に確認が必要な場合(例えば応募者が言及した資格の正式名称や成績データなど事実確認)は、人事担当者を通じて問い合わせてもらうか、次の選考(二次面接等)があるならその場で尋ねれば良いでしょう。
逆に、応募者の側から面接後に質問メールが来るケースもあります。この場合、企業としては誠実に回答すれば問題ありません。
質問への回答自体は丁寧に行いつつ、そうした候補者のコミュニケーションスタイルも参考情報にはなるでしょう。
いずれにせよ、面接時に疑問は解消しておくのがベストです。
面接官は事前準備をしっかり行い、その場で必要な質問を漏れなくするよう心がけましょう。
どうしても終わってから気になる点が出たとしても、メールでの追加質問は最終手段と認識してください。
まとめ
採用面接は短い時間で応募者を評価する難しい場ですが、適切な質問によって相手の本音や能力を最大限引き出すことができます。
中小企業の採用担当者にとって、1回の採用の成功・失敗が企業に与える影響は大きいため、面接での質問事項は事前に入念に検討し準備しておくことが肝要です。
本記事で紹介した質問例やコツをもとに、自社の求める人物像に合わせた質問リストを作成してみてください。
だからこそ、質問の進行や深掘りの技術といった「質問事項以外のスキル」も磨いていく必要があります。
面接官自身も経験を積み重ね、より良い採用面接ができるよう工夫を続けましょう。
適切な質問で応募者の本音を引き出せれば、ミスマッチのない採用につながります。
面接官は企業の「顔」であると同時に「フィルター」でもあります。
公平で的確な質問を通して、自社にフィットする人材を見極め、そしてその人材に「この会社で働きたい」と思ってもらえるような面接を実施しましょう。
のガイドが、皆様の採用面接の質向上に役立てば幸いです。

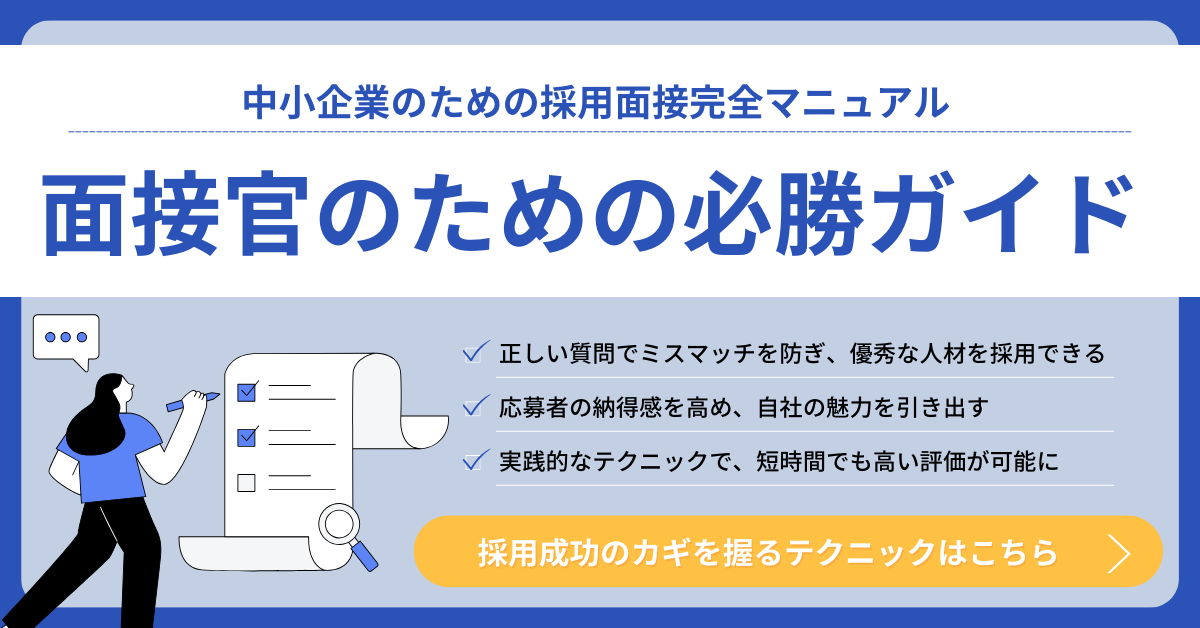
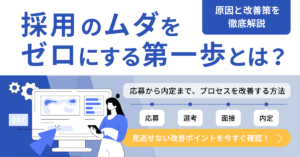






とは?メリット・デメリットや導入ポイントを徹底解説-300x157.png)
コメント