noteを活用しての採用する企業が増えていきます。
noteはGoogleと業務提携したことにより、以前よりもページが見られやすくなっているため、採用広報として利用するにはとても効果的です。
noteを上手に活用している企業の情報や成功事例についてまとめていきます。
noteを活用した採用広報とは?
「採用広報」とは、自社の魅力や価値観を発信し、採用したい人材の応募につなげる戦略的なコミュニケーション手法です。
スタートアップ企業では、自社をよく知らない優秀な人材にもアプローチするために、企業文化や社員の声を積極的に発信することが重要になっています。
noteは、文章・写真・動画など様々なコンテンツを誰でも簡単に投稿できるブログサービスです。
もともとは個人ユーザー向けに人気を博していましたが、近年では企業が公式ブログ的にnoteを活用するケースも増えています。
法人向けの有料プラン「note pro」も提供されており、企業アカウントとしてブランディングしながら情報発信することが可能です。
無料から始められ、操作もシンプルなため、自社サイトにブログ機能がないスタートアップでも手軽にオウンドメディアを立ち上げられるのが魅力です。
noteを活用した採用広報とは、このnote上で企業や社員が記事を発信し、会社のビジョンやカルチャー、働く人々の姿を求職者に伝える取り組みを指します。
スタートアップ企業にとって、まだ世間に知られていない自社の魅力を伝える手段としてnoteは有力です。
例えば、後述する株式会社ベーシックでは2019年からnoteを採用広報に活用し始め、社名の認知度向上と応募者増加に成功しました。
このように、自社のストーリーをnoteで発信することで、採用マーケットでの存在感を高め、必要な人材との接点を生み出すことができるのです。
note採用広報が注目されている理由
ではなぜ、採用広報の手段としてnoteがこれほど注目を集めているのでしょうか。
スタートアップ企業の人事担当者がnoteを活用する主な理由として、以下の5つが挙げられます。
企業のリアルな魅力を伝えやすい
noteは文章量の制限がなく、自由なテーマで記事を書けるため、企業のリアルな魅力を余すところなく伝えることができます。
たとえば、現場社員が自分の言葉で仕事への想いや社風について綴ることで、飾らない「生の声」を届けられます。
広報用に整えられたメッセージだけでなく、嬉しかったことや苦労したこと、学びなど等身大のストーリーを発信できるのがnoteの強みです。
実際、note pro公式ブログでも「マガジン機能を使えば社員のnoteアカウントと連携し、現場のリアルな声を集約できる」と紹介されています。
社内メンバーが書いた記事を一つにまとめて求職者に提示すれば、様々な角度から会社の魅力を伝えられます。
企業の実像や価値観をありのまま表現しやすい点で、noteは採用広報に適した媒体と言えるでしょう。
個人note記事をマガジン化できる
前述のマガジン機能は、noteならではの特徴です。
マガジン機能とは複数の関連する記事をまとめて1つのコンテンツ集にできる機能で、企業公式アカウントが社員個人の投稿をマガジンに収録することも可能です。
スタートアップでは社員一人ひとりが発信者となり、各自のnote記事を会社のマガジンに集めて「社内報」のように活用しているケースがあります。
例えば「入社エントリ」(なぜこの会社に入ったか)や「プロジェクトの振り返り」といったテーマで社員が書いた記事をまとめれば、求職者はそのマガジンを読むだけで企業のカルチャーを多面的に知ることができます。
個人の視点が集約されたマガジンは、会社の公式発信よりも説得力が増し、「働く人たちの生の姿」が伝わるコンテンツ集になります。
ターゲット層への的確なアプローチができる
noteで記事を公開すれば、プラットフォーム上の幅広いユーザー層にリーチできます。
2023年5月時点でnoteの利用者数は663万人を超えており、閲覧者も多岐にわたります。
そのため、転職意欲が高い顕在層だけでなく潜在層にも情報発信が可能です。
例えばエンジニア向けの技術記事を投稿すれば、今すぐ転職を考えていない技術者にも読まれる可能性があり、「この会社面白そうだな」と興味を持ってもらえるきっかけになるでしょう。
また、note上ではタグ機能や他SNSとの連携シェア機能が充実しているため、自社が狙う人材属性に合わせて情報を拡散しやすい利点もあります。
記事に付けるハッシュタグを工夫すれば、特定の関心を持つ読者(例えば「#スタートアップ」「#エンジニア転職」など)にリーチできますし、TwitterやFacebookに記事リンクをシェアすることで該当層に届けることも可能です。
求めるターゲット層へピンポイントで訴求できる柔軟性が、note採用広報の魅力です。
SEO対策としても効果的
作成したコンテンツを検索エンジン経由で見つけてもらいやすいのも、note活用のメリットです。
note上の記事はインターネット上に公開されるため、適切にキーワードを盛り込めばGoogleなどで検索結果に表示されます。
自社サイトに掲載した情報よりも、note記事の方が検索でヒットしやすいケースもあるのです。
例えば「〇〇(自社名) 社員インタビュー」と検索した際に、公式サイト内の採用ページではなく、noteに投稿した社員インタビュー記事が上位に表示されるようなことも起こりえます。
これはSEO対策として非常に有効です。
求職者が企業名や業界キーワードで情報収集する際に、自社のnote記事が目に留まれば、そのまま読み込んでもらい応募への導線を作ることができます。
したがって、noteで良質な記事を蓄積しておくことは、自然検索からの候補者流入増加につながります。
若年層やクリエイティブ人材にアプローチしやすい
noteのユーザー層は比較的20~30代の若年層やクリエイター層が多いと言われています。
実際、noteで発信すると相性が良い職種の例として、ライター・デザイナー・マーケター・エンジニアなどWebを積極的に活用し自身でも情報発信に慣れた層が挙げられます。
これらの職種の人々は日頃からSNSやブログで情報収集する傾向が強く、noteもチェックしている可能性が高いのです。
また、新卒学生や第二新卒など若手層も、note上の企業情報に触れる機会が増えています
特にスタートアップ志望の学生はTwitterやnoteで社長や社員の発信を追っている場合も多く、そうした層にリーチできるのは大きな利点です。
デザインや文章などクリエイティブ感度が高い人材にもnoteは受け入れられやすく、文章で企業カルチャーを深く知って共感を得てもらえるでしょう。
以上のように、noteを使うことで企業の本質的な魅力を伝えつつ、狙った層に情報を届けやすくなるため、多くの企業が採用広報チャネルとして注目しているのです。
note以外の採用広報ツールの種類
もちろん、採用広報の手段はnoteだけではありません。
他にも様々なツールやチャネルを組み合わせて、候補者への情報発信や接点づくりを行う必要があります。
ここでは、note以外で代表的な採用広報ツールの種類について整理します。
求人情報サイト
「求人情報サイト」とは、リクナビNEXTやマイナビ転職、Indeedなど求人広告を掲載する専門サイトです。
これらは募集要項や待遇など求人票形式の情報を掲載し、主に転職希望者が閲覧します。
求人情報サイトは即戦力人材の応募を獲得する上で重要なチャネルですが、掲載できる情報がフォーマット化されており、企業のストーリーやカルチャーまでは十分に伝えにくい側面があります。
求人広告(オンライン/オフライン)
オンライン広告(Web広告)やオフライン広告(紙媒体、交通広告など)を使って採用募集を周知する方法です。
オンラインではリスティング広告やSNS広告、オフラインでは求人雑誌や駅張りポスター、合同企業説明会でのパンフレット配布などが該当します。
これらは不特定多数にリーチできる反面、広告費用がかかりますし、興味を引くクリエイティブ制作も求められます。
特にスタートアップ企業にとって大量出稿はコスト負担が大きいため、ピンポイントで採用ターゲットが集まる媒体に絞って出稿する、あるいは予算に余裕がない場合は無料SNS投稿やnoteのようなオウンドメディアで代替するケースが多いです。
採用専用Webサイト
自社の採用情報専用の公式サイト(採用ページ)を設ける方法です。
会社概要サイトとは別に、採用メッセージや募集職種一覧、社員紹介などをまとめた「採用サイト」を持つ企業も増えています。
スタートアップの場合、リソースの都合で公式サイト内の1ページ程度で簡易的に案内することもありますが、成長に伴い本格的な採用サイトを立ち上げることもあります。
採用サイトとnoteを連携させ、詳細なストーリーはnote記事に誘導するような活用も可能です。
YouTubeなどの動画コンテンツ
近年は採用広報に動画を活用する例も増えています。
YouTubeチャンネルで会社紹介動画や社員インタビュー動画、オフィスツアー映像などを公開し、視覚的に社風を伝える手法です。
動画は文章より訴求力が高く、社内の雰囲気や社員の人柄が直感的に伝わるメリットがあります。
例えばサイバーエージェントでは新卒採用向けに自社で選考対策動画を制作し公開するなど、採用コンテンツのDX(デジタル化)に取り組んでいます。
スタートアップでも工夫次第で低コストの動画配信は可能で、ウェビナー形式で社長や現場社員が語るライブ配信を行うケースもあります。
これら動画コンテンツはnote記事に埋め込んで共有することもでき、テキスト×動画で情報量を増やすことができます。
SNS(Twitter、Facebook、Instagram、LinkedInなど)
Twitter(現X)やFacebook、Instagram、LinkedInといったSNSも採用広報に活用されています。
SNSでは拡散力を活かして自社の最新トピックを発信したり、社員の日常やオフィスの様子を投稿したりできます。
SNSの強みはカジュアルなコミュニケーションが取れる点で、候補者との距離を縮めたり企業のファンを増やしたりしやすいことです。
注意点としては、SNS単体では情報が流れて蓄積しにくいため、詳細な記事はnoteにまとめておき、SNS投稿ではそのハイライトや更新通知を行うといった組み合わせが効果的です。
実際、noteで記事を書いてTwitterで拡散するといった企業も多く、相互補完的に活用されています
社員紹介プログラム(リファラルリクルーティング)
社内の従業員から知人・友人を紹介してもらうリファラル採用も、重要な採用経路です。
社員自身が自社の魅力を伝え、マッチしそうな人材を推薦するため、ミスマッチが少なく定着率が高い傾向があります。
採用広報との関係では、社員が外部の知人に会社を紹介しやすいように、noteの記事を活用することもできます。
例えば「自社がメディアに掲載された記事やnote記事のURLを知人に送る」という形で、社員が自社の魅力を伝えるツールとしてnoteが役立つのです。
スタートアップではリファラル経由の入社割合が高い企業も多いため、社員が誇りを持って紹介したくなるようなコンテンツを発信することが重要です。
以上のように、採用広報には様々な手法があります。
それぞれ強み・弱みが異なるため、自社の採用戦略に合わせて使い分けることが肝心です。
noteはあくまで選択肢の一つではありますが、他にはない特徴を持つため、他ツールと組み合わせて相乗効果を狙うことができます。
企業が採用広報にnoteを活用するメリット5つ
次に、企業がnoteを採用広報で利用することによって得られる具体的なメリットを見ていきましょう。
スタートアップ企業にとって、以下の5つは特に大きな利点となります。
コンテンツ運用をすぐに始められる
noteはアカウントを作成すれば即日から記事投稿を始められる手軽さがあります。
自社サイトでブログ機能を一から構築するとなると時間や費用がかかりますが、noteならその必要はありません。
実際、note公式も「どんな方でも始めやすく続けやすい構成となっている」と述べており、テンプレートを選べば簡単にカスタマイズしたサイトも構築できると紹介しています
このように、思い立ったらすぐにコンテンツ発信をスタートできるのがnoteの魅力です。
スタートアップでは人事広報の専任担当がいない場合も多いですが、noteであれば現場のメンバーが隙間時間に記事を書いて公開することも可能です。
サービス開始のプレスリリースやイベント登壇報告などから気軽に投稿を始め、徐々に採用候補者向けのコンテンツへと展開していくことができます。
初期費用がかからずリスクなく始められる点で、noteはコンテンツマーケティング初心者の企業にも優しいプラットフォームと言えます。
note上で求人情報が閲覧できる
noteは記事本文内に求人情報や募集要項へのリンクを掲載したり、note proの場合は採用ページと連携することもできます。
例えば記事の末尾に「現在○○職種を募集しています。詳しくは採用ページへ」と記載して自社採用サイトや求人票に誘導したり、Wantedlyなど他媒体の募集ページURLを貼ることも自由です。
さらにnote proでは採用管理システムとの連携がしやすく設計されており、求人情報をnote内に埋め込むことも可能です。
これにより、読者がその場で募集要項を確認し応募アクションにつなげやすい環境を作れます。
たとえば、会社のビジョンについて書いた記事を読んで興味を持った人が、同じページ上で募集職種一覧を見つけてそのまま応募フォームに進む、といった導線が実現できます。
実際にnote経由で応募が発生した場合、採用担当者にとってもどの記事から応募が来たか把握しやすく、コンテンツごとの効果測定にも役立つでしょう。
採用のミスマッチ防止に繋がる
noteで丁寧に自社の文化や仕事内容を発信することは、採用時のミスマッチ防止にも効果があります。
応募者が事前に会社のことを深く知った上で応募してくるため、入社後に「イメージと違った」というギャップが生じにくくなるのです。
例えばベーシック社では、自社のカルチャーをnote記事で発信することで文化に合った人材に入社してもらえるようになり、結果的に離職率の低下にもつながったといいます。
具体的には、社員の価値観や職場の雰囲気を赤裸々に書いた記事を読むことで、候補者は入社前に「この会社ではこんな風土の中で働くことになるのだな」と具体的に想像できます。
共感できない人は応募を控えるでしょうし、逆に「自分に合いそうだ」と感じた人だけが応募してくれるため、結果的に採用後のミスマッチが減ります。
note記事を通じて企業と候補者の相互理解を深めておくことは、長期的に見て定着率向上にも寄与するのです。
他のSNSとの相性が良く拡散されやすい
前述の通り、noteはTwitterやFacebookなど外部SNSと非常に相性が良いです。
記事ごとに共有ボタンが用意されており、読者が気軽にSNSに拡散できます。
そのため、一企業の公式発信でありながら、内容次第では個人のフォロワーネットワークを通じて爆発的に広まる可能性も秘めています。
また、企業アカウント自体の認知度やフォロワーが少なくても、note上で「おすすめ記事」に載ったり、ハッシュタグ経由で多くの人の目に留まる仕組みがあります。
質の高いコンテンツであれば、社名を知らないユーザーにも読まれ、結果的に会社の知名度アップや母集団形成につながります。
Twitterなどでシェアされたnote記事がきっかけでフォロワーが増えたり、その後の選考で「note読みました」と話題にしてもらえるなど、波及効果も期待できます。
つまり、noteは単独でも機能しますが、他SNSと連動させることで相乗効果で拡散力を高められるのです。
コストを抑えた採用活動ができる
最後に、note活用の大きなメリットとして採用コスト削減が挙げられます。
基本プランであれば利用料は0円、有料の法人プランnote proを使ったとしても月額数万円程度(最大でも8万円ほど)で利用可能です
これは求人媒体の掲載料や人材紹介会社の手数料と比べると格段に安く、工夫次第ではほぼ無料に近い費用で採用成功を収めることも夢ではありません。
例えばnote経由で1人採用できれば、その採用単価は実質0円(またはnote pro費用のみ)です。
ベーシック株式会社のように無料プランから運用を始め、軌道に乗ったタイミングで有料プランに切り替えるといった段階的な使い方も可能です
また、note記事がきっかけで応募に至れば広告費は不要で、前述のようにリファラル採用やダイレクト応募が増えることで、結果的に人材紹介会社への依存を減らし費用削減につながるケースもあります
このように、noteは低コストで始められて費用対効果の高い採用チャネルとしてスタートアップに適しています。
企業が採用広報にnoteを活用するデメリット5つ
一方で、noteを採用広報に活用する際には注意すべき点や課題もあります。
他の採用活動と比較した場合に感じるデメリットを5つ挙げ、それぞれ解説します。
他の採用活動との連携が必要
note単独で発信しているだけでは、採用活動として完結しない場合があります。
最終的に応募者を採用プロセスに乗せるには、他の採用チャネルとの連携が不可欠です。
例えば、いくらnote記事を読んで興味を持ってもらっても、実際に応募してもらうには求人応募フォームやカジュアル面談への誘導が必要です。
したがって、noteの記事内や周辺でエントリーページへのリンクを貼る、Wantedlyや採用サイトと併用して募集案内を周知する、といった連動が求められます。
また、note経由で接点を持った候補者に後日こちらからスカウトメールを送るなど、ダイレクトリクルーティング施策と組み合わせることも考えられます。
noteは母集団形成や企業理解促進の役割として位置づけ、実際の選考フローは別途走らせるイメージです。
ターゲット層が限られる
前述のメリットで、noteは若年層・クリエイティブ層にリーチしやすいと述べましたが、裏を返せばそれ以外の層には届きにくいという側面もあります。
例えば、ミドルシニア層や現場技能職など、そもそもnoteを見ない層に対しては効果が限定的です。
自社が求める人材像がnoteユーザーとマッチしない場合、いくら頑張って記事を更新しても応募につながらない恐れがあります
実際、HR系の記事では「募集したい職種とターゲット層がnoteと相性が良くなければ、一生懸命に採用広報活動をしても本末転倒」と指摘されています。
そのため、もしターゲット人材がnoteに馴染みのないタイプであれば、別の媒体に注力するか、noteでは別の層向けブランディングと割り切る必要があります。
スタートアップの場合、エンジニアやデザイナー採用には適していても、例えば店舗スタッフ募集などには向かないといったケースがあります。
note活用は万能ではなく、あくまでターゲットに合う場合に効果を発揮する点に留意が必要です。
コンテンツの作成に時間と労力がかかる
noteで成果を出すには継続的なコンテンツ作成が求められます。
文章を書くことに慣れていない社員にとって、記事1本仕上げるのにも相当な時間とエネルギーが必要でしょう。
特に質の高い記事を目指そうとすると、取材や撮影、社内確認などプロセスも増え、負担がかさみます。
また、一度投稿して終わりではなく、コンスタントに記事を出し続けることが大切です。
最初は意気込んで始めてもネタ切れや執筆者のマンネリ化で更新が止まってしまうケースも見受けられます。
社内に文章を書く文化がない場合は定着させるまでが大変で、担当者が孤軍奮闘になりがちです。
こうしたコンテンツ運用の手間はnote活用のハードルの一つであり、「思った以上に大変だった」と感じる企業もあるでしょう。
競合企業との差別化が難しい
多くの企業がnoteに参入してくると、コンテンツの差別化が課題になります。
採用広報の題材として定番の「社員インタビュー」や「働く環境紹介」などは、どの会社も似たフォーマットになりがちです。
結果、読み手からすると「どの会社の記事も同じような内容だな」と映ってしまい、記憶に残らない恐れがあります。
実際、大企業からベンチャーまで様々な企業がnote公式ブログを運営しており、その数は2023年時点で3万件以上にのぼります
情報量が増えるほど目立つのが難しくなるのは避けられません。
特に同業種・同規模の競合スタートアップが軒並みnoteで発信し始めると、自社ならではの個性を出すのに工夫が必要です。
「経営陣が自ら執筆する」「他社が書かないニッチなテーマを扱う」「デザインや語り口に独自性を出す」など、差別化戦略も考えなければ埋もれてしまう可能性があります。
管理・運営の負担
noteを継続運用していくには、管理・運営体制の整備も求められます。
記事ネタの企画出し、執筆スケジュールの管理、内容チェックや校正、反響のモニタリングなど、やるべきことは多岐にわたります。
社内で誰が責任を持つのか決めておかないと更新が滞ったり、質にばらつきが出たりしかねません。
最初は人事担当者が兼務で始めても、投稿数が増えるにつれ編集部的な役割が必要になるでしょう
例えばマネーフォワード社では、採用広報専任だった体制からリクルーター全員で記事作成・発信する体制に変更し、3名のチームで編集方針の策定や原稿チェックを行う「note編集部」を設置したそうです。
このように、組織だった運用をしないと継続が難しいのもnoteの特徴です。
小規模なスタートアップでは人手が限られるため、無理なく運営する方法(例えば四半期に1本ペースにする等)を模索する必要があります。
以上のデメリットを踏まえつつも、それを上回るリターンを得ている企業が多いのも事実です。
次章では、実際にnote採用広報を上手く活用して成果を出している企業の成功事例を見てみましょう。
noteでの採用広報が上手い企業の成功事例
ここからは、noteを使った採用広報で特に成果を上げている5社の具体的事例を深掘りします。
それぞれの企業がどのようにnoteを活用し、どんな効果を得たのかを紹介します。
株式会社ベーシック
マーケティング支援事業などを手がける株式会社ベーシックは、2019年から積極的にnoteを採用広報に活用しています。
同社は自社サービス(Ferret Oneなど)の知名度に比べて運営企業名「ベーシック」の認知度が低く、それが原因で入社後のカルチャーミスマッチも発生していました。
この課題を解決するため、Twitterと組み合わせてnoteで自社の姿を発信し始めたのです。
具体的には、経営陣や社員がそれぞれの視点で会社に関する記事を執筆し、会社公式のマガジン「ベーシック note編集部」に集約しています。
記事の内容は入社エントリー(なぜベーシックに入社したか)、事業への想い、社内制度の紹介、働く中での学びなど多岐にわたります。
社員自身の言葉で綴られたコンテンツは求職者にとってリアルで説得力があり、「この会社のファンになる」と称されるほど高い共感を呼びました。
特に、note開始後は自社採用ページ経由の応募が約3倍に増加し、さらに内定承諾率は9割以上にまで高まったといいます
これはnoteで会社のカルチャーや魅力を正しく伝えられるようになったおかげだと、同社採用広報チームも分析しています
加えて、社員のエンゲージメントも向上し、前述の通り離職率の低下という副次的効果も得られました
ベーシック社の成功ポイントは、経営層から現場まで巻き込んだ全社的な発信と、Twitter連動による拡散で認知度を飛躍的に高めたことにあります。
スタートアップがnote採用広報を始める上で、社名ブランド向上とミスマッチ防止の好例と言えるでしょう。
株式会社サイバーエージェント
インターネット広告やメディア事業で知られる大手IT企業株式会社サイバーエージェントも、採用広報においてnoteを巧みに活用しています。
特に新卒採用の分野で先進的な取り組みを行っており、動画コンテンツや自社メディアを駆使した情報発信で注目されています
サイバーエージェントは新卒向けに「エンジニア採用広報」というnoteアカウントを運営し、技術広報の記事や社内文化、社員インタビューなどを発信しています
また、採用候補者に向けてYouTube上で選考対策動画を公開したり、OB訪問(社員と学生の懇談)をオンライン配信するなど、コンテンツのDXを推進しています
これら動画やイベントのレポートもnoteにまとめられ、テキストと動画双方で会社の魅力を伝える戦略を取っています。
同社は採用広報専任チームがあり、データ分析やアンケートを通じてコンテンツ施策の効果測定を行っている点も特徴です
例えば、どの媒体経由で応募者が増えたか、動画視聴が内定承諾にどう影響したか等を計測し、「量より質」の効果測定に取り組んでいます。
さらに将来的には各候補者に最適化された情報提供、いわば採用コンテンツのパーソナライズを目指しているとのことです
こうした最先端の採用広報によって、サイバーエージェントは就職市場で強力な発信力を維持しています。
具体的な数字は公表されていませんが、新卒応募者数は毎年非常に多く、動画経由で会社への理解を深めた上で選考に臨む学生も増えているようです。
「働くワクワクを最大化する採用広報」というテーマで同社が語っている通り、候補者自身が主体的に情報収集しファンになってもらう仕掛けが随所にあります。
サイバーエージェントの事例は、大手ならではのリソースを活かしつつ、スタートアップにも応用できる「マルチメディア×note」の可能性を示しています。
株式会社マネーフォワード
フィンテック領域のユニコーン企業である株式会社マネーフォワードは、採用広報において社内外から高く評価される取り組みを行っています。
同社はWantedlyなど外部プラットフォームでも積極的に情報発信してきましたが、近年では公式noteアカウント「中途採用@マネーフォワード」を開設し、本格的に自社オウンドメディアでの採用広報を強化しました。
マネーフォワードの特徴は、採用広報専任組織「People Forward本部」を立ち上げ、リクルーター全員が発信に関与する体制を敷いたことです。
以前は専任者が記事作成を担っていましたが、現在は各担当リクルーターが自ら原稿を執筆し、広報・カルチャー担当者を含む3名の編集チームで品質チェックと公式noteへの掲載を管理しています。
実際のコンテンツとしては、各事業部ごとのメンバーインタビューシリーズ「ビジネスカンパニーで働く人の紹介」や、部門ごとの仕事紹介、社員のキャリア振り返り記事などが多数公開されています。
これにより候補者は職種ごとの具体的な業務内容やチームの雰囲気を詳しく知ることができます。また、社員自身も記事執筆を通じて自社への理解や愛着が深まり、社内の協力体制が強固になったといいます。
こうしたnote中心の採用広報強化によって、マネーフォワードはダイレクト応募やリファラル採用の比率を大きく高めることに成功しました。
2020年の中途採用実績では、約100名の正社員採用のうちリファラルが30%、ダイレクトリクルーティング(スカウト応募)が25%を占め、従来エージェント頼みだった状況から大きく転換したそうです。
さらに、採用単価(採用一人あたりのコスト)も100万円を下回る水準に抑えられており、コスト効率の面でも成果が出ています。
加えて、「記事を読んでマネーフォワードを好きになった」という応募者も多く、面接の時点で会社への共感度が高い傾向が見られます。
マネーフォワードの事例から学べるのは、社内巻き込みによる継続運用と、コンテンツ効果の定量評価です。
記事経由で応募した人の割合や入社後の活躍などを追跡し、採用広報が採用KPIに寄与していることを示せれば、経営層からの支持も得やすくなります。
同社は急成長フェーズで社員数を300人から850人へと拡大する中、noteを含む採用広報戦略がエンジンの一つとなりました。
スマートキャンプ株式会社
クラウドサービスの比較サイト「BOXIL」などを運営するスタートアップのスマートキャンプ株式会社は、自社の公式noteマガジン「.tent(テント)」を活用した採用広報で知られています。
スタートアップ企業ながら、体系立てたコンテンツ運用を行い、新卒・中途双方での採用ブランド向上に成功しています。
スマートキャンプのnoteでは、大きく「新卒採用向け」と「中途採用向け」にコンテンツカテゴリを分け、それぞれに適した情報発信をしています。
一方中途向けには、「社員リレー企画」と称して各部署の社員がリレー形式で仕事観や社風について語る連載や、部署ごとの業務内容・やりがいをまとめた記事などを掲載しています。
特徴的なのは、記事数が非常に豊富なことです。社員リレー記事は既にVol.190以上公開されており、多くの現場社員が登場しています。
このように全社的に情報共有・ナレッジ発信する文化が醸成されており、それ自体がスマートキャンプの魅力となっています
「積極的にナレッジや成功事例が共有されている社風」だという声を社員が記事内で語っており、それを読んだ候補者も学習意欲の高い社風に魅力を感じるでしょう。
また、スマートキャンプはnote記事内で募集ポジションの案内や採用イベント告知も行い、読者を直接採用活動へ巻き込んでいます。
例えば「新卒採用エントリー開始しました!」といった記事では、会社が大事にしていることや募集要項を記し、最後にエントリーフォームへのリンクが設置されています
読み物として楽しませながら、きちんと応募につなげる導線を用意している点が秀逸です。
成果として、スマートキャンプは新卒採用市場で人気企業の一つとなり、毎年多くの学生を惹きつけています。
具体的な応募者数は非公開ですが、note等で発信しているビジョンやバリューに共感して入社を決めたという声が多く聞かれます。
また、中途採用でも応募前にnote記事を熟読してくる候補者が増え、面接時のミスマッチ減少につながっているようです。
コンテンツマーケティング的手法を採用にも活用し成功した例として、スマートキャンプはスタートアップ各社から注目されています。
株式会社ミラティブ
スマホゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ」を提供する株式会社ミラティブは、創業間もない頃からnoteでの発信に力を入れてきた企業です。
規模100名ほど(2022年時点)のスタートアップながら、年間50名以上の採用を実現するなど人材確保に成功しており、その背景に強力な採用広報戦略があります
ミラティブ社のnote発信は多岐にわたります。技術ブログ(エンジニア向けの開発知見共有)、組織文化に関する記事、イベント開催報告、採用チームからの振り返り記事など、様々なマガジンを運営しています
例えば「ミラティブログ」という法人マガジンでは、半年で12本の社内イベントを開催しテックブログは年間34本投稿したという2021年の採用広報活動総括記事が公開されており、どれだけ精力的に情報発信してきたかが伺えます。
さらに、人事担当者自らがnoteで採用実績と取り組みを数字で振り返る記事も執筆しています
2022年の振り返り記事によれば、同年に新たに正社員50名を迎え社員数が100名を超えたとのことで、これだけの採用を支えた要因として「全社採用の文化醸成」「リファラル採用の強化」「ひたむきな情報発信」など5つのポイントを挙げています。
特にリファラル(社員紹介)については、紹介件数が前年比333%、紹介による採用決定が前年比214%と飛躍的に伸びたことを明らかにしています。
note記事を通じて社員が自社の魅力を外部に伝えた結果、紹介したいと思える仲間探しが活発化したと分析できます。
ミラティブの採用広報は「語り、わかりあう会社」というスローガンを掲げ、CEO自ら候補者向けのメッセージを発信するなどトップも巻き込んだものです。
note上ではCEOから採用候補者への公開書簡や、新卒入社エンジニアの入社エントリーなども掲載され、会社の透明性と熱量が伝わってきます。
こうしたトップダウンとボトムアップ双方からの発信により、ミラティブは短期間で多数の共感者を集め、結果として採用目標を次々と達成しています。
成功の秘訣は、やはり全社的な巻き込みとPDCAです。
ミラティブ人事は毎年noteでデータを公開しつつ、その経験をもとに翌年の採用戦略をブラッシュアップしています。
スタートアップが急成長する際に、noteを使って組織文化ごと対外発信する好例として、ミラティブの事例は非常に示唆に富みます。
noteでの採用広報を成功させる5つのポイント
成功事例に共通するポイントや、これからnote採用広報を始める企業が押さえておきたいポイントを5つにまとめます。
以下のポイントを意識することで、noteでの情報発信効果を最大化できるでしょう。
ターゲット層を明確に設定する
まず重要なのは、「誰に向けて発信するのか」を明確にすることです。
自社が採用したい人物像や職種を定義し、そのターゲットに響く内容・語り口を意識して記事を作成します。
例えば、新卒向けなら学生目線で会社のミッションや働く環境を紹介し、エンジニア中途向けなら技術的チャレンジや開発文化を詳しく書く、といった具合にです。
闇雲に社内の出来事を発信するのではなく、読み手として想定するペルソナに合わせてネタ選定や表現をチューニングしましょう。
また、ターゲット層がnoteを利用して情報収集しているかも調査が必要です。
もし主要なターゲットがnoteと親和性が低ければ、noteで頑張るより別媒体に注力すべきかもしれません。
誰に読んでほしいかを明確にした上でコンテンツを設計することが、成果に直結します。
具体的な社員ストーリーを紹介する
読み手の共感を呼び、記憶に残るコンテンツにするには、具体的なエピソードや人物を登場させることが効果的です。
単なる会社紹介ではなく、そこで働く「人」にスポットを当てた記事は、採用広報における鉄板とも言えます。
社員一人ひとりのストーリー、入社の動機、やりがい、成長の軌跡、苦労と乗り越えた経験など――を掘り下げて紹介することで、読者は企業をより身近に感じられます。
成功事例の企業も、社員インタビュー記事や社員が自分で執筆する記事を多数用意していました。
例えばミラティブでは新卒入社エンジニアの入社理由を綴った記事、マネーフォワードでは各社員のキャリアパス紹介記事などを掲載しています。
こうした「人を見せる」コンテンツは、「この人と一緒に働きたい」「自分も同じ体験をしてみたい」と感じさせ、応募意欲を刺激します。
実名や顔写真の公開に抵抗がある場合でも、仕事内容や価値観にフォーカスした記事であれば書けるでしょう。
ぜひ自社のキーパーソンや若手ホープなどのストーリーを発信してみてください。
見やすく整理されたコンテンツを作る
どんなに内容が良くても、読みにくい記事では最後まで読んでもらえません。
見やすさ・読みやすさへの配慮も成功には欠かせないポイントです。
具体的には、適切に見出し(タイトル・小見出し)を配置し、文章を短めの段落に分け、箇条書きや太字を用いて要点を強調するといったテクニックがあります。
また、画像や図表を挿入できるなら活用して、視覚的に飽きさせない工夫も重要です。
noteはシンプルなデザインで文章中心のプラットフォームですが、逆に言えばレイアウト次第で大きく印象が変わります。
社内にデザイナーがいればアイキャッチ画像を統一感あるデザインにしてもらうのも良いでしょう。
また、複数の記事が蓄積してきたらマガジン機能でカテゴリ別に整理したり、過去記事同士をハイパーリンクで関連付けたりすると、読者が必要な情報にたどり着きやすくなります。
こうした細やかな配慮が、結果的に滞在時間の延長や応募率向上につながるでしょう。
継続的に更新を行う
採用広報は長期戦です。noteも1本記事を書いて終わりではなく、継続的な更新こそが信頼醸成とファン獲得につながります。
週に1本、月に2本など無理のない頻度でよいので、コンスタントに記事を投稿し続けましょう。
継続的な発信があることで、「この会社は最近どんな情報を出しているかな?」と定期的に見に来てくれるリピーター読者も増えていきます。
現実には業務優先で更新が滞ることもあるでしょう。
その場合でも、最低限のお知らせや短めの記事でも投稿することが大切です。
例えば「今月は採用イベントに出展しました」程度の軽い内容でも更新することで、「活動している」ことを示せます。
逆に長期間放置されたnoteは、候補者に「最近動きがないのかな」と誤解を与えかねません。
先述のマネーフォワードの例では、採用広報初期のKPIとして毎週・毎月の定期発信を掲げていたとのこと。
企業文化や価値観を明確に伝える
最後に、発信する内容の核としてブレてはならないのが企業文化や価値観のメッセージです。
どの記事にも一貫して「この会社は何を大事にしているか」「どんな使命に燃えているか」がにじみ出ていることが理想です。
成功企業のnote記事を読むと、会社ごとのキーワード(バリューやスローガン)が頻繁に登場します。
例えばベーシックなら「問題解決の集団」というミッション、ミラティブなら「語りわかりあう社会を目指す」といったビジョンなど、根底にある思想を繰り返し発信しています。
これは読者に企業のアイデンティティを印象付け、共感を呼ぶために重要です。
採用においてはスキルマッチ以上にカルチャーフィットが重視されますから、自社の文化に共鳴する人を惹きつけるためにも、価値観の発信を恐れないことです。
具体例やエピソードと紐付けて、「我が社では〇〇を大切にしています」というメッセージを様々な角度から伝えていきましょう。
明確な軸が感じられる発信は、読み手にも刺さりやすく、「他ではなく御社に入りたい」という動機付けにつながります。
以上5つのポイントを実践することで、noteでの採用広報を成功にぐっと近づけることができるはずです。
noteでの採用広報に関するよくある質問
最後に、これからnoteを使った採用広報を始めようとする企業担当者が抱きがちな疑問にQ&A形式でお答えします。
Q. noteで採用広報を始めるにはどうすれば良いですか?
A. まずは企業アカウントを作成し、最初の投稿をしてみましょう。
無料の通常プランから始めて問題ありません。
最初の投稿内容としては、簡単な会社紹介や採用広報を始める旨の宣言記事などがおすすめです。
その後、社員の協力を得ながらインタビュー記事や職場レポートなど少しずつコンテンツを増やしていきます。
社内調整としては、どの部署が主導するか(人事 or 広報 or 経営企画など)、記事ネタのアイデア出しや執筆の担当割り振りを決めておくとスムーズです。
小さな会社であれば人事担当が編集者となり、各メンバーに寄稿してもらう形が取り組みやすいでしょう。
また、可能であれば運用方針やペルソナ像を簡単にまとめた企画書を作り、経営陣の承認を得ておくと社内協力も得やすくなります。
Q. noteの記事にどのような内容を含めるべきですか?
A. 基本は「自社の魅力を伝える」ことを目的に、様々な切り口の記事を書いていきましょう。
具体的な内容の例としては
- 社員インタビュー:社員の入社理由、現在の仕事内容、仕事のやりがい、今後の目標など。できれば複数の年代・職種の社員を紹介する。
- 企業理念やバリューの紹介:会社が大切にしている価値観を、具体的なエピソード(バリュー体現者の表彰や日常の一コマ)とともに伝える。
- 社内イベント・制度レポート:全社会議、懇親会、ハッカソン、社員旅行、福利厚生制度の紹介など社風がわかるトピック。
- プロジェクト事例紹介:自社プロダクトやサービス開発の裏側、苦労と達成などを語る。現場社員の生の声が入っているとなお良い。
- 募集ポジションの紹介:特に急募している職種があれば、その仕事内容や期待する人物像を詳しく説明し、求人情報ページへのリンクを貼る。
- 経営陣からのメッセージ:社長や役員が自ら会社のビジョンや今後の戦略、人材に求めるものなどを語る。
これらを織り交ぜながら、読者が「会社のことを立体的に理解できる」ようなラインナップにすると良いでしょう。
Q. noteでの採用広報の効果はどのくらいで現れますか?
A. 効果が実感できるまでの期間は企業の知名度や記事内容、更新頻度によって様々ですが、短期的に爆発的な成果が出るものではなく中長期戦と考えたほうがよいです。
早いケースでは、初めて公開した記事をSNSでシェアしたところ思いのほか話題になり、すぐに何件か応募が来たという例もあります。
ただ一般的には、記事本数が蓄積し検索流入やSNSフォロワーが増えてくる3〜6ヶ月以降で徐々に応募者から反応が出始めることが多いようです。
例えば前述のベーシック社の場合、運用開始から数ヶ月で社名の認知が広がり応募者数が増加し始めたとのことです。
一方、マネーフォワード社のようにnote運用を本格化して1年程度で採用チャネル構成比が大きく変わった例もあります。
このように成果が表れるまでにはある程度の継続と記事蓄積が必要ですが、過去記事が資産として効いてくるため、やればやるほど後々効果が出やすくなる側面があります。
Q. noteの採用広報はどれくらいの頻度が理想的ですか?
A. 理想を言えば月に数本ペース(週1本程度)で更新できると検索エンジン評価や読者エンゲージメント向上の面で望ましいです。
ただし無理をして質の低い記事を量産するよりは、各社のリソースに応じて無理ない頻度で続けることが肝心です。
月1本でも半年続ければ6本溜まりますし、質の高い長文記事を不定期に出す戦略もありです。
更新頻度の目安として、スタートアップ各社の実例では以下のようなケースがあります。
ベーシック社は初年度は毎週のように記事を投入して一気に150本以上蓄積したとの報道がありました
一方、他の企業では月2本ペースでじっくり続けている所もあります。
社内の協力度合いによっても左右されるため、まずはできる範囲で始め、余裕があれば頻度を上げる形で取り組むと良いでしょう。
Q. noteを利用するために費用はかかりますか?
A. 基本的なnoteの利用は無料です。
ユーザー登録をして記事を投稿するだけであれば費用は一切かかりません。
企業で公式アカウントを運用する場合も、無料プランで問題なく始められます。
後々、独自ドメインの使用やデザインカスタマイズ、詳細なアクセス解析など高度な機能が必要になった場合に、法人向け有料プラン「note pro」への契約をご検討ください。
自社サイトにオウンドメディアを構築するコストや、求人広告費と比べれば非常に低コストです。
初めは無料で試し、反応が良く本格運用したくなったらnote proに切り替えるという流れでも遅くありません。
まずは費用ゼロで始められる点もnoteの魅力ですので、金銭的ハードルは気にせずスタートしてみてください。
まとめ
スタートアップ企業にとって、noteを活用した採用広報は「攻めの採用」を実現する有力な手段です。
無料で手軽に始められ、文章主体で自社のリアルな魅力を伝えられるnoteは、従来の求人票や採用ページでは届けにくかった企業の熱量やカルチャーを候補者に届けてくれます。
実際にベーシック社やマネーフォワード社など、多くの企業がnote発信によって応募者の質・量の向上や採用コスト削減という成果を上げています。
もっとも、note活用は魔法の杖ではなく、継続的な取り組みと他チャネルとの組み合わせが必要です。
今回紹介した成功事例の共通点を参考に、自社らしい発信スタイルを模索してみてください。
採用広報は候補者との最初の接点づくりです。
noteで自社のストーリーを発信することは、言わば「こんな未来を一緒に創りませんか?」と呼びかけること。
そのメッセージが真に響けば、まだ見ぬ優秀な仲間がきっとあなたの会社の扉を叩いてくれるでしょう。
ぜひnoteを上手に活用し、スタートアップの魅力を世の中に発信していってください。

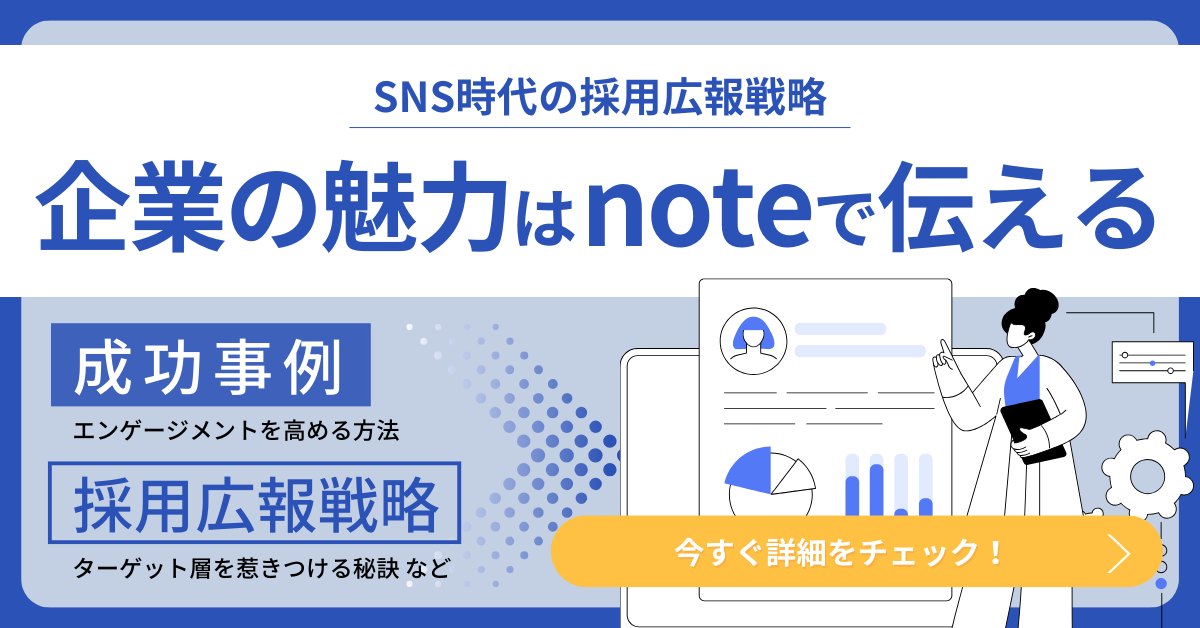

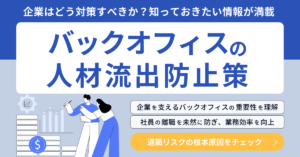
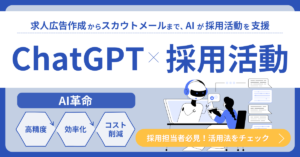
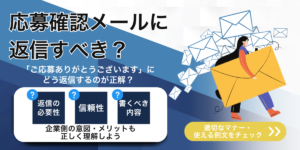
コメント