採用活動に頭を悩ませている人事担当者の皆さん、「採用施策」はうまく活用できていますか?
優秀な人材を獲得するためには、場当たり的に手段を講じるのではなく、計画的で効果的な施策を組み合わせることが大切です。
本記事では、採用成功の鍵となる7つの採用施策を具体例とともに紹介し、あわせて「施策に振り回されないための採用戦略の重要性」や、自社に最適な施策を選び効果を最大化するポイントについて解説します。
採用成功の鍵!効果的な採用施策7選
まずは、採用活動でよく使われる代表的な施策を7つ取り上げます。
それぞれの特徴やメリット・デメリット、活用イメージを押さえておきましょう。
求人広告(Web媒体・求人サイト)|幅広い層へのアプローチが可能
求人広告は、最も基本的な採用施策の一つです。
Web媒体や求人サイトに自社の求人情報を掲載することで、不特定多数の求職者に広くリーチできます。
例えば「リクナビNEXT」「マイナビ転職」「Indeed」といった大手求人サイトや、業界特化型の求人ボード、ハローワークなどが代表的です。
幅広い層へのアプローチが可能なため、応募者の母集団形成(いわゆる母集団集め)に有効です。
この施策のメリットは、短期間で多くの応募を集めやすいことです。
知名度の高い求人サイトに掲載すれば、毎日多数の求職者が閲覧するため、自社を知らない人にも情報を届けられます。
一方で注意点として、応募の量は増えても質の見極めや選考工数の増大に繋がる可能性があります。
応募が殺到すると対応が大変になるため、応募要件の明確化やスクリーニング方法の工夫が必要です。
また、有料媒体への掲載料などコストも発生します。
求人広告を出す媒体は、自社のターゲット層が利用しているものを選ぶことが重要です。
例えば若手層中心ならSNS連動型の求人サービス、専門職なら業界特化サイト、といったように媒体選定しましょう。
人材紹介(エージェント)|効率的なマッチングと成功報酬型
人材紹介会社(エージェント)を活用する採用施策は、効率的に条件に合う人材を獲得したい場合に有効です。
エージェントに依頼すると、自社の求人ニーズにマッチする候補者をプロのコンサルタントが紹介してくれます。
書類選考や日程調整なども仲介してくれるため、採用担当者の負担軽減につながります。
また、一般的に成功報酬型(候補者が入社して初めて費用発生)の料金体系であることが多く、「採用できなければ費用がかからない」のも特徴です。
この施策のメリットは、マッチング精度の高さとスピーディーな採用です。
特に即戦力となる中途採用では、人材紹介会社経由で良い人材を獲得できたという企業も多いでしょう。
ただしデメリットもあります。第一に費用が高額な点です。
人材紹介の手数料相場は採用決定者の年収の約30%程度と言われ、年収が高いポジションほどコスト負担も大きくなります。
例えば年収500万円の人材を採用すると150万円程度の紹介料が発生する計算です。
また、エージェントから多数の候補者を紹介いただいても、社内選考でミスマッチが起きると無駄なコストに繋がりかねません。
効率重視とはいえ、自社の採用基準を明確に伝えることやエージェントとの密なコミュニケーションが成功のポイントです。
ダイレクトリクルーティング|求める人材へ直接アプローチする「攻め」の採用
企業側から候補者に直接コンタクトを取る「ダイレクトリクルーティング」は、近年注目度が上がっている攻めの採用手法です。
ダイレクトリクルーティングとは、企業が自社で活躍できそうな人材に対して直接アプローチする採用手法です。
具体的には、転職サイトのスカウト機能を使って登録者にメッセージを送ったり、ビジネスSNS(LinkedInなど)でプロフィールを見て声をかけたり、自社開催のイベントで出会った人に後日オファーを出す等が一般的です。
この施策の最大の魅力は、こちらから欲しい人材にアプローチできる点です。
求人を出して待つだけでは出会えない転職潜在層(今すぐ転職する気はないが良い話があれば検討したい層)にリーチできるため、採用の母集団を広げられます。
また、応募してくれた人材は最初から自社に興味を持っているため、選考の歩留まりが良いケースも多いです。
一方で、ダイレクトリクルーティングは手間と時間がかかる方法でもあります。
スカウトメッセージを送っても返信率は一部に限られますし、興味を持ってもらうには魅力的なメッセージ作成や企業情報の発信準備が重要です。
また、担当者のコミュニケーションスキルも問われます。
狙った人材を効率よく獲得できれば非常に効果的な手法なので、専門のスカウト担当を置いたり、工数を割ける場合にはぜひ挑戦してみたい施策です。
リファラル採用(社員紹介)|信頼性が高く定着しやすい傾向
リファラル採用(社員紹介)とは、自社の社員から知人・友人を紹介してもらう採用手法です。
近年「友人紹介制度」などの名前で導入する企業も増えています。社員経由で声をかけることで会社への理解・信頼が高い人材を獲得しやすい点が特徴です。
最大のメリットはミスマッチが少なく定着率が高いことです。
実際、ある調査ではリファラル採用者の定着率が35.9%と、人材紹介経由入社者の23.3%を大きく上回ったと報告されています(※定着率=一定期間内で離職せず在籍している割合)。
これは、紹介してくれた社員が事前に会社の雰囲気や仕事内容を伝えてくれることで、入社後のギャップを小さくできるためです。
その結果、早期離職のリスクも低減します。
さらに、リファラル採用はコスト面でも優れています。
エージェント利用のような高額手数料が不要で、社員紹介の謝礼を支払ったとしても割安です。
加えて、優秀な転職潜在層にリーチできる点も魅力です。
社員の友人・知人ネットワークには、今は転職活動をしていないが良い話があれば関心を持つような優秀層が含まれている可能性があります。
注意点としては、社員に紹介を促すための制度設計や社内周知が必要なこと、紹介元社員のバイアスで多様性が損なわれないようにすることです。
例えば内向きなコミュニティばかりから紹介を受けていると人材層が偏る可能性もあります。
制度としては、社員に対して紹介件数や成約に応じたインセンティブ(報奨金)を用意したり、カジュアルに友人を会社に招待できるイベントを開くなど、社員が動きやすい仕組みを作ると良いでしょう。
自社採用サイト(オウンドメディア)|企業の魅力発信とブランディングの拠点
自社の採用サイトや採用ブログなど、自社で運営するオウンドメディアも重要な採用施策です。
求人広告やエージェントとは異なり、企業自らが情報発信する場であり企業の魅力発信とブランディングの拠点となります。
具体的には
- 自社コーポレートサイト内に採用ページを設ける
- 採用に特化したオウンドメディアを立ち上げる
- 会社のミッションやビジョン
- 社員インタビュー
- 働く環境紹介
- 福利厚生
- イベント情報
などを掲載します。
これにより求職者は求人票のスペックだけでなく、企業文化や価値観に触れることができます。
メリットは、自由度の高い情報発信ができることです。
一般の求人広告ではフォーマットや文字数に制限がありますが、自社サイトなら写真や動画を交えながら好きなだけ魅力をアピールできます。
また、自社の採用サイト経由の応募は広告費がかからないため、コスト面でも有利です。長
期的に見れば、自社サイトに蓄積したコンテンツがSEOで上位表示され、「採用 職種名」「会社名 採用」といった検索から継続的に候補者を集める資産にもなります。
一方で、自社採用サイトを運営するにはコンテンツを継続発信する労力が必要です。
更新が止まっていると「最近動いていない会社なのかな?」と印象ダウンにつながりかねません。
社内で記事を書くリソースがない場合は、外部のライターや採用広報サービスを活用するのも手です。
オウンドメディアは企業ブランディングと採用の要となる施策ですので、採用強化を目指すならぜひ取り組みたい施策です。
SNS採用|潜在層へのアプローチと企業文化の発信
Twitter(現X)やFacebook、Instagram、LinkedInといったSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を活用した採用手法も近年主流になりつつあります。
採用の魅力は、なんといっても幅広い年代の潜在層にアプローチできることと、企業の文化や雰囲気をダイレクトに発信できることです。
総務省の調査によれば、SNS利用率は全世代で78.7%、特に20代で93.2%、30代で89.5%にも上ります。
つまり多くの求職者予備軍が日常的にSNS上に存在しているのです。
具体的なSNS採用の方法としては
- 企業公式アカウントで採用情報や社員の日常、オフィスの様子などを発信する
- ハッシュタグを用いて自社に関心を持つフォロワーを増やす施策
などがあります。
たとえばエンジニア社員が技術情報を発信してファンを増やし、その中から採用につながるケースや、代表自ら会社のビジョンを語って共感を得るケースもあります。
SNS採用は基本的にアカウント作成や投稿が無料で始められ、運用コストも抑えられる手軽さがメリットです。
上手く活用できれば求人広告費を削減しつつ、自社にフィットする人材を引き寄せられるでしょう。
また、カジュアルなコミュニケーションができるため、堅苦しい採用サイトでは伝わりにくい社風や社員の人柄を表現しやすい利点もあります。
SNS運用には継続的な取り組みが不可欠です。
フォロワーを増やしエンゲージメントを高めるには、定期的な情報発信とユーザーとの対話が求められます。
一時的に始めても「ネタ切れ」で止まってしまったり、効果が見えずにやめてしまう企業も少なくありません。
SNSはバズれば大きな効果を生む反面、不適切な発信をすると炎上リスクもあります。
社内ルールを整えつつ、コツコツとファンを醸成していく姿勢で取り組みましょう。
採用イベント(説明会・ミートアップ)|直接的なコミュニケーションで魅力を伝える
企業説明会や採用ミートアップなどの採用イベントは、直接候補者とコミュニケーションを取れる貴重な機会です。
特に新卒採用では会社説明会が一般的ですが、中途でも小規模の交流会(ミートアップ)がトレンドとなっています。
またカジュアルな交流が目的で、必ずしも選考を前提としないため、転職潜在層や通常の採用活動では出会えない優秀層にもリーチできます。
イベントの形式は様々です。
会社説明会であれば経営者や採用担当者が会社概要や募集職種についてプレゼンし、その後の質疑応答で双方向コミュニケーションを図ります。
ミートアップ型イベントでは、社内のメンバーと参加者で座談会をしたり、ライトな懇親会形式でお互いを知る場とすることが多いです。
例えばIT企業ならエンジニア同士で技術談義のできる勉強会を開いたり、スタートアップならオフィスでカジュアルなMeetupを開催して会社のカルチャーに共感してもらう、といった工夫がされています。
これら採用イベントのメリットは、文章やオンライン情報だけでは伝えきれない会社の魅力を感じてもらえることです。
社員の人柄や職場の空気感などは直接会ってみないとわからない部分が多いですが、イベントを通じて「この社員たちと一緒に働きたい!」と思ってもらえれば大成功です。
デメリットや注意点としては、準備と運営に手間とコストがかかることが挙げられます。
会場手配や集客告知、当日の運営スタッフ準備などが必要です。
オンライン開催にすれば会場費は抑えられますが、双方向の空気を作る工夫が求められるでしょう。
しかし得られる効果を考えれば投資する価値は大いにあります。最
近では合同企業説明会や業界別イベントも盛んですので、自社単独イベントと外部イベントの両方を上手に活用すると良いでしょう。
以上、代表的な採用施策7選を紹介しました。
では、こうした施策を検討・実行するにあたって土台となる「採用戦略」について次に見ていきましょう。
ただ施策をやみくもに試すのではなく、戦略に基づいてこそ効果を発揮するという点を押さえておく必要があります。
なぜ「施策先行」は危険?採用戦略の重要性
ここまで採用施策を列挙しましたが、闇雲にこれらを実行すれば良いというわけではありません。
場当たり的に施策に飛びつく「施策先行型」の採用活動は、多くの場合うまくいきません。
この章では、「採用戦略」の重要性について解説します。
まずは戦略と施策の違いを整理し、戦略なき施策が招く失敗例、そして明確な戦略を持つことのメリットを確認しましょう。
採用戦略とは?目的・目標達成のための設計図
「採用戦略」とは、一言で言えば企業が必要とする人材を効果的に確保するための長期的な計画のことです。
経営計画や事業計画と連動させつつ、「いつ、どのような人材を、どのような方法で採用するか」を描いた設計図とも言えます。
優秀な人材を安定的に確保するためには場当たりではなく計画的・戦略的な視点が欠かせません。
例えば、「今後3年間で海外展開を進めるので、英語堪能な営業職を毎年5名ずつ中途採用する」「2年後の新工場稼働に向けて、今年は技術者を10名新卒で採用する」といった具合に、将来の組織ビジョンに基づいて採用目標を設定します。
その上で、それを達成するための予算配分、人員体制、スケジュールなどを決めていくのが採用戦略です。
要するに採用戦略は、「誰をどれだけ、いつまでに採用するか」というゴールと、「それをどうやって実現するか」という手段の大枠を示したものです。
採用施策とは?戦略を実行するための具体的な手段
一方、「採用施策」とは、前述してきたような具体的な採用手段・方法を指します。
戦略が設計図だとすれば、施策は実際の建築プロセスや道具にあたります。
戦略を実行に移すための個別施策の組み合わせが、最終的な採用成果を生み出します。
採用戦略と採用施策の関係を簡単な例で示しましょう。
例えば戦略で「経験3年以上のITエンジニアを半年以内に5名採用する」という方針を立てたとします。
これを実現する施策として
- 主要な転職サイトに求人広告を出す(母集団形成)
- 社員紹介制度を活用して紹介を促す(質の高い候補者の獲得)
- 専門特化のエージェントにも並行して依頼する(即戦力層の獲得)
- 技術者向けMeetupイベントを開催する(認知拡大と興味喚起)
など、複数の手段を組み合わせることが考えられます。
これら求人広告・リファラル・エージェント・イベントが採用施策です。
このように、採用戦略(方針)があって初めて、それを実現するための採用施策(手段)が意味を持ちます。
戦略なき施策が招く失敗とは?(コスト増・ミスマッチ・非効率化)
採用戦略を持たずに手当たり次第に施策に飛びつくと、残念ながら失敗につながるリスクが高まります。
具体的にはどのような失敗が起こりうるでしょうか?
まず考えられるのはコスト増大の問題です。
それでいて成果に結びつかなければ、貴重な採用予算を浪費する結果になりかねません。
次にミスマッチの増加です。
戦略がないということは、求める人物像や評価基準も不明確なまま採用してしまう恐れがあります。
その結果、「とりあえず人を入れたものの社風に合わず早期離職してしまった」「ポジションを埋めるために妥協採用したら思うような成果が出ない」といった事態が発生します。
入社後にミスマッチが発覚すれば、採用コストが無駄になるだけでなく、組織にも本人にもダメージがあります。
チームの生産性低下や他社員への負担増、モチベーション低下といった悪影響まで招きかねません。
さらに採用プロセスの非効率化も挙げられます。
場当たり的に動くと、「どのチャネルからどれだけ応募が来て、選考通過率はどうで…」といったデータが散在し、効果検証ができません。
「なんとなく忙しく色々やっているのに成果が出ない」という状況に陥ったら、まさに戦略不在で右往左往しているサインと言えるでしょう。
以上のように、戦略なき採用施策はコスト面・質の面・効率面で負の結果を招きがちです。
では逆に、明確な戦略に基づいて採用施策を展開するとどんなメリットが得られるのでしょうか?
明確な採用戦略がもたらす3つのメリット
採用戦略をしっかり策定してから施策を選択・実行することは、多くのメリットをもたらします。
ここでは代表的なメリットを3つ紹介します。
1. 採用コストの最適化と効率向上
戦略に沿って必要な施策に絞り込むことで、無駄な出費を抑えられます。また応募から内定までのプロセスも整備され、ムダのない効率的な採用活動になります。効果的な採用戦略を立てることで、採用コストを下げたり採用成功率を高めることも可能です。
2. 応募者数・質の向上
戦略立案時に自社の強みや訴求ポイントを整理しておくことで、求人内容や採用広報の質が上がり、結果として応募者が集まりやすくなります。また「誰を採るか」がぶれないため、理想とする人材像にマッチした応募者を惹きつけやすくなります。採用戦略を立てることで求職者にアピールする強みやターゲットが明確になり、理想の人材を採用しやすくなるという効果があります。
3. ミスマッチ・辞退の減少
戦略段階で求める人材像が明確になっていれば、選考基準も一貫性が出ます。その結果、入社後のミスマッチが減り定着率が向上します。また、戦略に基づいた一貫性のある採用プロセスは応募者に安心感を与え、選考辞退・内定辞退の減少にもつながります。
このように、採用戦略を持つことは採用活動全体の質を高め、成功確率を上げる土台となります。
そうならないためにも、次章で紹介する手順で自社に合った採用戦略と施策の組み合わせを検討してみてください。
失敗しない!自社に最適な採用施策を選ぶ4ステップ
では具体的に、自社に最も適した採用施策を選び、効果的に実行するにはどうすればよいでしょうか?
ここでは4つのステップに分けて考えてみましょう。
この手順に沿って計画すれば、戦略から施策実行まで一貫性を持った採用活動をデザインできます。
STEP1:採用目標と求める人物像(ペルソナ)を明確化する
まずは採用のゴールを明確に設定します。
何のために、いつまでに、どんな人材を何名採用したいのか、この採用目標がスタート地点です。
例えば「営業部の拡大のため、来年度中に即戦力の法人営業経験者を3名採用する」や「開発プロジェクト開始に向け、新卒でエンジニア5名採用する」といった具合に、できるだけ具体的に数値目標・期限・必要なスキルなどを定めます。
次に、その目標を達成するために求める人物像(ペルソナ)を描きましょう。
ペルソナとは架空の人物モデルですが、「うちの会社にフィットし活躍してくれそうな人」をイメージします。
例えば営業経験者を採るなら「IT業界で3年以上の法人営業経験があり、新規開拓の実績を持つ30代前半の方。
自主的に動け、当社のベンチャー気質に馴染める柔軟性を持つ人」など、できるだけ具体像を描きます。
採用ペルソナを設定することで、後のステップでどの採用チャネルに注力すべきか、どんなメッセージでアプローチすべきかが見えやすくなります。
ターゲットが明確になれば、求人票の書き方やアピールポイントも的確に定められます。
STEP2:自社の現状と採用課題を正確に把握・分析する
次に現状分析です。自社の採用活動のこれまでの実績や課題点を洗い出しましょう。
具体的には、過去の採用データを振り返り
- 「どの媒体からの応募が多かったか」
- 「内定に至った人はどんな経路か」
- 「応募〜入社までに時間がかかりすぎていないか」
- 「どの段階で歩留まり(辞退や不合格)が発生しているか」
などを確認します。
例えば、「去年は求人サイト経由の応募100件中、内定2名だった」「リファラルで3名採用できたが、エージェント経由は費用の割に成果ゼロだった」等、データを把握することで効果的な施策・非効率な施策が見えてきます。
また、新卒採用なら大学別の応募人数・内定率、中途採用なら年齢層や職種ごとの選考通過率など細かく分析すると、自社の強み弱みが浮き彫りになります。
さらに、外部環境の分析も有用です。
業界の採用市場動向(有効求人倍率や競合他社の動き)、自社の知名度・ブランド力の客観評価、待遇面での競争力などを把握しておくと、戦略立案にリアリティが増します。
このステップのポイントは、自社の採用課題を正確に認識することです。
「応募者数が少ない」「ミスマッチ入社が多い」など漠然とした悩みを具体的な課題として言語化できれば、次のステップで解決策(施策)を検討しやすくなります。
STEP3:各採用施策の特性・コスト・効果を比較検討する
ステップ1で採用したい人材像と目標を定め、ステップ2で現状課題を把握したら、いよいよ適切な採用施策の組み合わせを検討します。
ここで重要なのは、前章で紹介したような各施策の特性やメリット・デメリットを踏まえて、自社の状況にマッチする手法を選ぶことです。
まず採用予算との兼ね合いで、コストを考慮しましょう。
費用対効果を見極めるため、可能であれば1名あたりの採用単価(各施策に投下した費用 ÷ その施策で採用できた人数)などを試算すると判断材料になります。
例えば、昨年求人広告に50万円使って2名採用できたなら単価25万円、エージェント経由で1名採用し80万円手数料を払ったなら単価80万円、といった具合です。
単純比較はできませんが、コスト効率の良し悪しは見えてきます。
次に、各施策の得意領域を考慮します。
- 求人広告は幅広い層の母集団形成に強い
- エージェントは即戦力人材の紹介に強い
- リファラルは文化フィットした人材確保に強い
- SNSは若手層や潜在層へのリーチに強い
など施策ごとに向き不向きがあります。
自社の採用ターゲットがどの層かによって、組み合わせる施策も変わってくるでしょう。
例えばターゲットが専門スキルを持つ人なら専門エージェント+ダイレクトリクルーティング、ターゲットが大量採用の新卒ならナビサイト広告+自社説明会、といった具合です。
また、採用スピードや採用人数も施策選定に影響します。
短期間で一気に採用したいなら募集広告やイベント動員を強化すべきでしょうし、ポジションに余裕があるなら時間はかかってもリファラルやダイレクトで質重視に動く選択もあります。
必要に応じて経営陣や現場マネージャーとも議論し、「このポジションは多少コストかけても失敗できないからエージェント使おう」「この職種は若手が欲しいからSNSやイベントで攻めよう」など方針をすり合わせると良いでしょう。
最後にもう一つ大事な視点は、複数施策の併用です。
ある一つの手法だけに頼るのではなく、リスク分散と相乗効果を狙って複数のチャネルを併用するのが一般的です。
ただし手を広げすぎると管理が煩雑になるため、自社のリソースで無理なく回せる範囲で選択することも忘れずに。
STEP4:実行計画を立て、KPIを設定する
施策の組み合わせ方針が決まったら、具体的な採用実行計画を策定します。
ここでは「誰が」「いつまでに」「何を」行うかを明確にし、実際のアクションに落とし込みます。
例えば、「5月〜6月:求人サイトAに求人掲載(担当:人事○○さん)」「7月:自社採用ページ刷新&社員インタビュー記事公開(担当:広報○○さんと人事で協力)」「8月:エンジニア向けMeetupイベント開催(担当:技術部○○マネージャー、人事調整)」といった形で、カレンダーに主要施策を配置します。
採用は複数月にまたがることが普通なので、年間スケジュールとして計画しておくと抜け漏れ防止になります。
そして**KPI(重要業績評価指標)を設定しましょう。
KPIとは目標達成度を測る中間指標です。
ステップ1で定めた最終目標(例:◯名採用)に向け、途中経過をトラッキングするための数字を決めておきます。
例えば「〇月末までに応募者50名獲得」「書類通過率20%以上維持」「面接辞退率10%以下に抑える」等です。これらKPIをモニタリングすることで、途中で手応えが悪ければ施策の見直し・追加投入を検討できます。
逆に順調ならそのままリソースを集中投入すればよいでしょう。
採用活動のPDCAを回すためにも、計画段階でKPI設定は欠かせません。
また、チームで採用を進める場合は定期的な進捗会議を開き、KPI状況を共有しながら対応策を話し合うことも重要です。
以上の4ステップ(目標・ペルソナ設定 → 現状課題分析 → 施策比較検討 → 計画・KPI設定)を踏めば、少なくとも「なんとなく求人広告出してみたけど効果不明…」といった無計画さは避けられるはずです。
自社に最適な採用施策を選び抜き、計画的に実行する土台が整いました。
【課題別】効果的な採用施策の組み合わせ例
企業によって抱える採用課題は様々です。
「応募者の数が足りない」「良い人が来ない」「内定辞退が多い」などケースごとに有効な対策は異なります。
ここでは典型的な5つの課題を取り上げ、それぞれに合った採用施策の組み合わせ例を紹介します。
自社の状況に近いケースがあれば、ぜひ参考にしてみてください。
応募者の「数」が足りない場合
まず、「応募者自体が集まらない」という課題です。
中小企業や知名度の低い企業、ニッチな職種の採用などでありがちな悩みですね。
応募者数が少ないと、そもそも選考母集団形成ができず採用競争に乗れません。
- 求人広告の露出強化: 大手求人サイトや求人検索エンジンへの掲載を増やし、とにかくまずは目に留まる機会を増やします。予算が許せば複数媒体に同時掲載したり、広告オプションで上位表示を狙うのも手です。求人数が多い現在、埋もれない工夫が必要です。
- 自社サイト・SNSでのPR: 採用ページを充実させSEO対策を行うほか、TwitterやInstagramで求人情報や社員の声を積極発信します。無料手段で露出を増やし、少しでも興味を持つ人を逃さないようにします。
- 採用イベントへの参加・開催: 大学の合同企業説明会や転職フェア等に積極的に参加し、直接アピールの場を増やします。また自社で小規模な会社説明会やウェビナーを開催し、「話だけでも聞いてみたい」層を取り込むのも有効です。
- 応募ハードルの見直し: 必要以上に応募条件が厳しすぎないか見直します。例えば「経験○年以上必須」より「未経験可・研修あり」とした方が応募の門戸が広がります。また応募フォームを簡略化する、履歴書不要にするなどハードルを下げる工夫も検討しましょう。
このように母集団形成策を中心に、量を確保する方向で施策を打つことが重要です。
応募者の「質」に課題がある(ミスマッチが多い)場合
応募は来るものの、自社の求めるレベルやカルチャーフィットに合わない人ばかり…という場合、量より質の改善が課題です。
書類選考通過率が低かったり、面接まで進んでもミスマッチを感じるケースが多いなら、このケースに該当するでしょう。
- ペルソナ再設定と情報発信見直し: まず求める人物像を再確認し、それが応募者に伝わっているか求人情報を点検します。求人票に具体的なミッションや歓迎するマインドを書く、オウンドメディアで社員のリアルな声を載せるなどして、合わない人が最初から避けるような発信に変えていきます。
- リファラル採用の推進: 質重視なら社員紹介で信頼できる人材を狙うのが近道です。現場社員に「こんな人が来てほしい」という像を共有し、積極的に友人知人を紹介してもらいます。社員経由だと会社とのマッチング精度が高まります。
- ダイレクトリクルーティング: こちらも質の高いターゲットに直接アプローチできる手法です。理想的な経験を持つ候補者にこちらから口説くことで、ピンポイントで「欲しい人」を採用できる可能性があります。手間はかかりますがミスマッチは減るでしょう。
- 選考プロセスで相互理解を促進: 質の担保には選考段階も重要です。一方的な面接だけでなく、オフィス見学や現場社員との座談会を選考途中に挟み、候補者自身に自社を判断してもらう機会を設けます。カルチャーフィットしない人はその時点で辞退となり、結果的にミスマッチ入社が防げます。
「母集団の質向上」は一朝一夕には難しいですが、地道なブランディングと発信改善が効いてきます。
内定辞退率が高い場合
苦労して選考を進め内定を出したのに「候補者から辞退されてしまう…」これは採用担当にとって非常に痛い課題です。
特に複数オファーを得ている優秀層や売り手市場の新卒では起こりがちです。
内定辞退率が高い場合、オファー承諾までのプロセス改善が求められます。
- 候補者体験の改善(CX向上): 選考中のフォローアップを手厚くします。面接間隔を空けすぎない、合否連絡を迅速にする、面接で感じた魅力ポイントを後日改めてフィードバックする等、候補者の温度感を下げない工夫を凝らします。内定後も入社まで定期的にコンタクトを取りフォローします(懇親会招待や社長からのメッセージなど)。
- オファー面談で魅力訴求: 単に内定通知を出すだけでなく、最終面接後に改めて「オファー面談」の場を設け、待遇説明や入社後の期待役割の話をするとともに、候補者の不安点をヒアリングして解消します。「ぜひうちに来てほしい」という熱意を伝えることも大切です。
- 競合他社との差別化ポイント整理: 候補者が迷う要因として他社オファーとの比較があります。自社の強み(例えば成長機会、社風の良さ、技術力、福利厚生 etc.)を改めて整理し、内定者に資料や口頭で伝えます。他社にはない魅力を感じてもらえれば承諾率アップにつながります。
- 内定者フォロー施策: 内定受諾後から入社日まで時間がある場合、内定者研修や内定者懇親会を実施して絆を深めます。同期となる他の内定者や先輩社員との交流で「入社するのが楽しみ」という気持ちを醸成できれば、辞退リスクは下がります。
内定辞退への対策は、一言で言えば「選ばれる企業」になるためのきめ細かな配慮です。
採用コストを抑えたい場合
「できるだけ費用をかけずに採用したい」というニーズも多いでしょう。
特にスタートアップや予算が限られる部門では、採用コストを最小化しつつ必要な人材を確保する工夫が求められます。
- リファラル採用の活用: 前述のとおり社員紹介は低コストで質の高い人材獲得につながる手法です。多少の紹介インセンティブを払ってもエージェント手数料に比べれば微々たるものですので、まず優先的に推進しましょう。
- SNS・無料媒体の活用: 自社SNSでの情報発信や、LinkedInの無料求人投稿、Wantedlyなど安価なダイレクトリクルーティングサービスを活用します。SNS採用は工夫次第で採用コストを大幅に抑えられる手法です。また自治体やハローワークの無料求人サービスも利用を検討します。
- 自社サイト強化: オウンドメディアに力を入れ、広告費をかけずともオーガニック流入で応募が得られる状態を作ります。時間はかかりますが、採用広報の蓄積は長期的に見て費用対効果抜群です。
- 選考プロセス効率化: コストには人件費も含まれます。採用担当者や面接官の工数削減のため、応募者管理システム(ATS)の導入や、一次面接をビデオ録画によるエントリー動画選考に置き換えるなど、省力化施策もコスト削減につながります。
なお費用を抑えるとはいえ、出すべき投資まで出し渋るのは危険です。
例えば急募ポジションでどうしても採用が必要な場合、費用を惜しんで時間を浪費する方が機会損失が大きくなります。
「ここは出す」「ここは抑える」のメリハリをつけ、限られた予算を賢く配分しましょう。
採用担当者のリソースが不足している場合
人事部の人数が少なく採用業務に割ける時間が足りない、あるいは他業務と兼任で忙しい…といった場合、省力化や外部リソース活用が鍵となります。
限られたマンパワーで最大の成果を出す工夫を考えましょう。
- 採用管理ツールの導入: エクセル管理からATS(採用管理システム)に移行し、応募者への一括連絡や進捗管理の自動化を図ります。これにより日程調整メールの送付漏れや重複対応などのミスも減り、担当者の負担軽減になります。
- 採用代行サービス(RPO)の利用: リソースが本当に足りなければ、思い切って採用の一部を外部委託するのも手です。候補者スクリーニングや面接調整、時には面接代行まで行ってくれるRPO(Recruitment Process Outsourcing)を利用すれば、戦略策定や最終判断など要所に集中できます。
- エージェントの併用: 忙しくて母集団形成に時間を割けないなら、人材エージェントにある程度任せるのも現実解です。紹介会社が候補者を選んでくれる分、自社でゼロからスカウトする手間が省けます。ただし任せきりにせず定期的に要件すり合わせは必要です。
- 社内協力体制の構築: 採用は人事だけの仕事ではありません。現場社員から社員紹介を募ったり、各部署に面接官をアサインしてもらったりと、全社協力モードを作りましょう。特にベンチャーなどでは役員自らTwitterで採用発信したりする例もあります。「採用は経営課題」と位置付け、社内の理解を得ることもリソース不足解消につながります。
要は、テクノロジーの力と外部・社内の人の力を借りて、自社人事の労力をセーブする発想です。
限られたリソースで最大限の成果を出すには、必要に応じて外部サービスを使うことも恥ではありません。
「人手が足りない…」と嘆くより、使えるものはどんどん使いましょう。
以上、5つの課題に対する施策例を見てきました。当てはまるものはありましたでしょうか?
流行りの手法だからと飛びついても、自社に合わなければ意味がありません。
ぜひ自社の状況を分析し、最適解を導き出してみてください。
採用施策の効果を最大化するためのポイント
最後に、選んだ採用施策を最大限効果的に機能させるコツについて触れておきます。
どんな施策でも、やりっぱなしでは本来のポテンシャルを活かせません。
採用活動の成果をぐっと高めるために、人事担当者が注力すべきポイントを4つ挙げます。
採用ブランディング|「選ばれる企業」になるための魅力づくり
近年の採用市場では、「企業が候補者を選ぶ」だけでなく「候補者に企業が選ばれる」状況が強まっています。
優秀な人材ほど複数社からオファーを受け取る中で、自社を選んでもらうには採用ブランディングが重要です。
採用ブランディングとは、採用候補者に対する自社の魅力づくり・イメージ戦略のことです。
具体的には、自社のビジョンやカルチャーを明確に打ち出すことから始まります。
オウンドメディアや説明会資料で社員の活躍ストーリーを紹介したり、SNSで社内イベントの様子を発信したりするのもブランディング施策です。
面接時にも一貫して自社の価値観を語り、応募者に「ここなら自分らしく働けそうだ」と思ってもらえるよう努めましょう。
また、他社にはない強みを洗い出し、それをブランディングの軸に据えることも有効です。
例えば「圧倒的な技術力」「フラットで風通しの良い組織」「社会課題を解決するビジネス」など、自社ならではの魅力ポイントを見極めて発信します。
これが明確だと、採用コピーや求人広告の訴求メッセージにも芯が通り、印象に残りやすくなります。
採用ブランディングは一朝一夕に成果が出るものではありませんが、地道に続けることで「ファン候補者」を増やし、結果的に採用成功率を高める効果があります。
小さな企業でも、採用広報に創意工夫を凝らして強いブランディングを確立している例は多数ありますので、ぜひ挑戦してみてください。
候補者体験(採用CX)向上|応募から入社までの体験価値を高める
CX(カスタマーエクスペリエンス)ならぬ**候補者エクスペリエンス(採用CX)という考え方が注目されています。
これは、応募者・候補者が採用プロセスを通じて感じる体験価値のことです。
採用CXを向上させることで、途中辞退の減少や内定承諾率の向上、さらに入社後の満足度向上まで期待できます。
具体的なCX向上施策としては、応募者目線に立ったコミュニケーションが挙げられます。
また、不合格の場合でも丁寧なお断りメールを送るなど、最後まで礼を尽くすことで企業イメージアップにつながります。
選考プロセス自体も見直しましょう。
例えば面接官が皆バラバラの質問をしていたり、高圧的な態度をとっていたりすると最悪です。
統一した評価基準で公正に選考することは応募者に安心感を与えますし、面接中もリラックスして話せる雰囲気づくりが大切です。
さらに、内定後のフォローも採用CXの一環です。
歓迎の意を伝える手紙やギフトを送ったり、入社までの間に定期連絡して質問を受け付けたりする企業もあります。
「入社日が待ち遠しい」と思ってもらえるような体験を提供できれば最高です。
このように採用CXを向上させる施策は、大きなコストをかけずともホスピタリティと工夫で実現できます。
候補者との接点一つひとつを大事にし、「さすが○○社は対応が違うな」と思ってもらえればしめたものです。
その積み重ねが、最終的に採用競争力の差となって表れます。
データ分析と効果測定|PDCAサイクルで施策を改善する
良い施策を選んで実行しても、それをきちんと効果検証し改善につなげるプロセスがないと、持続的な採用力向上は望めません。
そこで重要なのが、採用データの分析とPDCAサイクルの徹底です。
まず、採用に関する様々な指標をトラッキングしましょう。
前述のKPIもそうですが
- 応募経路ごとの書類通過率・内定率
- 面接官ごとの評価傾向
- 入社者の活躍度合い(パフォーマンス評価や定着状況)
など、測れるものはできるだけデータ化します。
最近はATSやHRテックツールの発達で、ダッシュボードで一目で把握できるようになってきています。
これらデータを用いて、「どの施策がどれだけ効果的だったか」「どこにボトルネックがあるか」を定期的に分析します。
例えば「SNS経由の応募者は内定率が低い、なぜならスキル要件を満たさない人が多い→発信内容を見直そう」とか、「エージェントA社からの紹介は内定承諾率が高い→A社との関係を強化しよう」など、事実に基づいた改善策が見えてきます。
四半期ごとや採用プロジェクト終了時などに、関係者で集まって「うまくいったこと・課題だったこと」を洗い出し、次回への改善策をまとめます。
例えば「面接プロセスが長すぎたので今後は回数を減らそう」「イベント参加者をもっとフォローすべきだった」など具体的な反省を次の施策計画に組み込みます。
こうしたPDCAサイクルを回すことで、採用施策の精度と効果は徐々に高まっていきます。
一度決めたやり方に固執せず、データを根拠に柔軟に戦術を変えていく姿勢が、変化の激しい採用市場では求められます。
最新の採用トレンドをキャッチアップする
最後に、常に最新の採用トレンドや手法にアンテナを張っておくことも、人事担当者として大切なポイントです。
採用手法は時代とともに変化しますし、新しいサービスやテクノロジーも続々登場しています。
取り残されないようキャッチアップを習慣化しましょう。
具体的には、人事向けのセミナーや勉強会に参加したり、採用業界のニュースや専門メディアを定期的にチェックしたりすると良いでしょう。
例えば最近で言えば、オンライン面接ツールの活用、AIによる適性検査や面接評価、アルムナイ採用(元社員の再雇用)や副業人材活用といった新しいキーワードが出てきています。
また、新卒採用のナビサイトに代わるダイレクトリクルーティング型サービスの台頭や、地方人材獲得のための地域特化型施策など、トレンドは多岐にわたります。
もちろん何でも飛びつく必要はありませんが、「今はこんな方法もあるのか」と知っておくだけでも、自社に合った時にすぐ検討に移せます。
逆に変化に気づかず旧来手法に固執していると、いつの間にか競合他社に遅れをとることにもなりかねません。
社内で最新情報を共有する場を設けたり、若手社員の意見を聞いてみるのも良いでしょう。
例えば「最近の学生はどんな就活サイト使ってる?」とか「エンジニア界隈で評判の良い会社採用手法って何?」など、生の声からヒントを得ることもあります。
常に学ぶ姿勢を持ち、採用担当者自身がアップデートし続けることが、長期的には最も大きな力になるでしょう。
まとめ:戦略に基づいた採用施策で、優秀な人材獲得を実現しよう
採用成功には、「何となく良さそうだから」と場当たり的に施策を打つのではなく、明確な採用戦略に基づいて最適な施策を選択・組み合わせることが肝心です。
求人広告・エージェント・ダイレクトリクルーティング・リファラル・自社サイト・SNS・イベントといった各種採用施策はそれぞれ特徴が異なるため、自社の採用目的や課題に合ったものを見極めて活用しましょう。
紹介した4ステップを参考に、自社にフィットした採用計画を描いてみてください。
また、採用施策の効果を最大化するために、採用ブランディングで候補者に選ばれる魅力を発信し、採用CX向上で候補者一人ひとりに良い体験を提供することも忘れずに。
さらにデータをもとにPDCAを回し、常に採用手法をアップデートしていく姿勢が、これからの人事担当者には求められます。


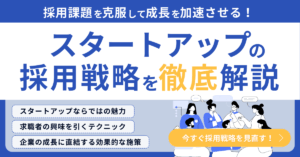
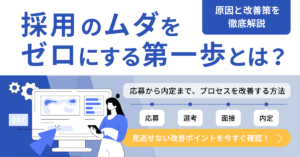





とは?メリット・デメリットや導入ポイントを徹底解説-300x157.png)
コメント