スタートアップ企業の採用は今、大きな課題とチャンスが共存しています。
シリコンバレーで広まった「スタートアップ」は日本でも新たな価値創造や経済成長の原動力として注目されています。
しかし、優秀な人材の獲得なくしてスタートアップの成長は語れません。
現状、スタートアップ各社は人材確保に苦戦しがちであり、従来の採用手法だけでは十分な成果を上げにくいのが実情です。
2023年までにスタートアップの求人需要は2015年比で6.8倍に増えた一方、転職者数(スタートアップへ流入する人材)は3.1倍に留まっています。
このギャップが示すように、スタートアップの採用市場は深刻な人材不足で競争が激化しているのです。
本記事では、人事担当者必見の「スタートアップ採用戦略」について網羅的かつ実践的に解説します。
スタートアップ採用成功の鍵:課題の理解・戦略策定・最適な手法
スタートアップの採用を成功させるためには、闇雲に人材募集をするのではなく「課題の正確な理解」「戦略の策定」「適切な手法の選択」という3つのステップが重要です。
それぞれ順を追って見ていきましょう。
採用課題をまず理解する
スタートアップ採用に挑む前に、自社の置かれた状況や採用面の課題を客観的に洗い出すことが不可欠です。
一般にスタートアップは大企業ほど知名度も資金もないため、求人を出しても応募が集まりにくい傾向があります。
また、限られたメンバーで事業を回しているため採用に割ける人手や時間も不足しがちです。
こうした課題を放置したままでは優秀な人材確保は困難です。
まずは自社の課題を明確化し、「何がボトルネックになっているのか」「どんな人材が不足しているのか」を整理しましょう。
採用戦略を策定し計画する
課題を認識したら、次に採用戦略の策定です。
経営陣とも連携し、事業計画や成長フェーズに合った人員計画を立てましょう。
創業期なのか成長期なのかによって求める人材像も異なります。
例えば創業初期であれば役割分担が固定されていないため「何でも自分事として取り組めるゼネラリスト」を、拡大期であれば現状を打破し組織を再構築できる人材を求める、といったようにフェーズごとに戦略を練ります。
また、採用ターゲットの明確化も重要です。
どのポジションにどんなスキルやマインドセットを持つ人が必要か、ペルソナを描きましょう。
スタートアップでは即戦力志向が強い一方でミスマッチは致命的です。
スキルセットだけでなくカルチャーフィットも考慮した人物像を定義し、それに基づいて採用メッセージや選考基準を設計します。
最適な採用手法を選択する
戦略が定まったら、実行段階では最適な採用手法(チャネル)を選びます。
大企業のように知名度任せで求人広告を出すだけでは埋もれてしまいがちです。
待ちの採用ではなく攻めの採用手法を積極的に検討しましょう。
具体的には後述するようなダイレクトリクルーティングやリファラル(社員紹介)、SNSの活用など、スタートアップに適したチャネルを組み合わせて母集団形成を行います。
また、限られたコストで最大の効果を上げるため、各手法の費用対効果も見極めが必要です。
たとえば求人媒体への掲載は予算競争になりやすく、十分な予算がなければ広告出稿だけでは成果に結びつかない可能性があります。
一方、エージェントやヘッドハンティングを使う場合は成功報酬型とはいえ費用は高額になるため、本当に必要なポジションに絞るなど工夫しましょう。
自社のリソースとニーズに合った手法を選ぶことが成功への近道です。
スタートアップで働くということ:メリット・デメリット
スタートアップ採用を語る上で、スタートアップで働くことの魅力とリスクを理解しておくことは重要です。
人事担当者は候補者にスタートアップ勤務のメリットを伝える一方、デメリットに対する不安にも答える必要があります。
ここでは、スタートアップで働く主なメリットとデメリットを整理します。
スタートアップで働くメリット
- 裁量権が大きく成長機会が豊富:少人数組織のため一人ひとりに大きな裁量権があり、若手でも重要な仕事を任されます。大企業では得られないスピードでPDCAを回し、多彩な業務に挑戦することで短期間で実力を伸ばすことができます。成果を出せば早期に昇進・昇給につながり、自分の成長を実感できる環境です。
- 幅広いスキル習得とキャリア形成:マーケティングも開発も一手に担うなど、複数ポジションを兼任することも珍しくありません。その結果、新しいスキルの習得やスキルの複合による市場価値向上が期待できます。例えば「エンジニア×ビジネス」のように、異なる領域の知識を掛け合わせることで希少な人材へと成長できます。
- 経営に近い立場で仕事ができる:経営層との距離が近く、会社全体を俯瞰する視点が養われます。経営判断に触れながら働くことで、将来マネジメント層として必要な視座や意思決定力を早いうちから培うことができます。会社の成長に直接貢献している実感を持てる点も大きな魅力でしょう。
- 新しい価値創造への挑戦:スタートアップは既存にないサービスや技術で市場を切り拓くのが醍醐味です。困難も多いですが、自ら描いたビジョンを形にし社会にインパクトを与えられる経験は、他では得難いやりがいです。達成した際の充実感や、自身のキャリアへの自信にもつながります。
- 将来的なリターンの可能性:事業が成長すれば創業メンバーとして将来的に大きな報酬を得るチャンスがあります。例えば、ストックオプションを通じて会社の成功を自分のリターンとして享受できる可能性があります。短期的には報酬面で劣ることもありますが、上場やM&A(エグジット)によって、将来的には大企業以上の収入を得ることもあります。
スタートアップで働くデメリット
- 業務量が多くハードワークになりやすい:幅広い業務を少人数で回すため、必然的に一人当たりの仕事量は多くなります。残業や休日出勤が発生しやすく、仕事とプライベートの境目が曖昧になりがちです。ワークライフバランスを重視する人にとっては負担となる可能性があります。
- 責任の重圧が大きい:大きな裁量と引き換えに、自分の下す判断一つひとつが事業に直結します。常に成果を求められるプレッシャー下で働くため、精神的なタフさが求められます。失敗した場合のリスクも自分に跳ね返ってくるため、ストレス耐性が必要です。
- 給与・福利厚生が限定的:創業間もない企業では資金に余裕がなく、高待遇を提示するのが難しい場合があります。大手企業と比べると年収が下がる可能性は否めませんし、住宅補助や研修制度など福利厚生も最低限であることが多いです。ただ近年では大企業に遜色ない報酬や柔軟な働き方を提供するスタートアップも増えており、この点は企業によって差が出てきています。
- 事業の不確実性(倒産リスク):スタートアップは成功すれば大きい反面、事業が軌道に乗らず撤退・倒産するリスクも付きまといます。将来の安定が約束されていないため、長期的な雇用やキャリアパスの見通しが立ちにくい不安があります。特に創業初期は資金繰りの悪化で急に計画変更や人員整理が行われる可能性もあり、安定志向の人には大きなリスク要因です。
- 社内体制の未整備:人事制度や研修プログラム、業務プロセスなどが整っていないケースが多く、自分で道を切り拓く姿勢が求められます。「放任主義」でサポートが少ない環境では、受け身の人や指示待ちタイプの人は力を発揮しにくいでしょう。裏を返せば自律的に動ける人には自由度が高い環境ですが、人によって向き不向きがあります。
人事担当者はこれらメリット・デメリットを把握した上で、候補者の不安を和らげつつスタートアップで得られる魅力を伝えることが肝心です。
「裁量が大きく成長できる一方でハードワークにもなる」というように表裏一体の部分も多いので、候補者の志向に合わせて伝え方を工夫しましょう。
大手・他ベンチャーとは違う!スタートアップ採用と働き方の特徴比較
スタートアップの採用活動や働き方は、大手企業や既存の中小ベンチャー企業と比べて独特の特徴があります。
違いを理解することで、スタートアップならではの強みを採用戦略に活かすことができます。
以下に主な相違点を比較します。
- 採用リソースとプロセスの違い:大手企業は知名度と整備された人事部門を活かし、大量採用が可能です。スタートアップでは「ひとり人事」が多く、採用の実務を一人で担うことが一般的です。知名度が低いため、積極的な「攻めの採用」が求められます。
- 企業文化・魅力の伝え方:大企業は長年の知名度や企業イメージがあり、福利厚生や安定性が魅力的です。スタートアップは企業のビジョンや文化を積極的に発信することで、共感する人材を惹きつけるチャンスがあります。特に、ゼロから文化を創れる点で、候補者に「自分も文化を作る一員になれる」という訴求が可能です。
- 働き方・キャリアの違い:大手企業は役割分担が明確で安定した働き方ができ、昇進には時間がかかる傾向があります。スタートアップは裁量が大きく仕事の幅が広いため、短期間で多様な経験を積むことができ、成長意欲の高い人にとっては魅力的です。スタートアップでは急成長を目指すプレッシャーが強いものの、得られる経験値も大きく、刺激的な環境となります。
このように、スタートアップの採用・働き方は大手とも従来型ベンチャーとも異なるポイントがあります。
人事担当者はスタートアップならではの魅力(裁量の大きさ、成長環境、新しい価値創造への参画など)と懸念点(安定性の低さ、制度未整備など)を整理し、自社の候補者に対して的確に伝えることが重要です。
大手出身者には「大企業にはないやりがい」を、ベンチャー出身者には「さらにスピード感ある環境での挑戦」を訴求するなど、相手のバックグラウンドに応じてメッセージを調整しましょう。
なぜスタートアップの採用は難しいのか?根本的な原因を分析
スタートアップ採用が難しいと言われるのはなぜでしょうか。ここでは根本的な原因をいくつか分析します。
先に述べたような他社との違いとも関係しますが、改めて課題を整理しましょう。
- 資金・人員リソースの不足: スタートアップは多くの場合、採用に割ける予算や人手が限られており、他社より高い給与や豪華な福利厚生を提供することが難しいです。採用専任チームを持てない場合もあり、求人広告の露出が十分に得られなかったり、採用活動が後手に回ることがあります。限られたリソースで最大の効果を上げる必要があるため、採用活動の難易度が高くなります。
- 知名度の不足とブランディング不足: スタートアップは多くの場合、知名度が低く、求職者がどんな事業をしている会社か把握していないことが多いです。知名度が不足しているため、求人情報が優秀な人材の目に留まりにくく、応募者数が伸び悩む傾向にあります。また、会社の魅力や将来性が伝わりにくいため、「リスクを冒してまで応募しよう」と思ってもらえないことが多いです。
- 即戦力人材の獲得競争: スタートアップは即戦力となる人材を求める一方、即戦力人材は市場で引く手数多で、知名度や待遇が良い企業からのオファーも集中します。そのため、スタートアップは大企業や有名企業に競り勝たなければならず、内定承諾を得るハードルが高くなります。また、スタートアップでは一人の採用ミスが事業に大きな影響を与えるため、慎重になりすぎて採用スピードが遅れることがあります。
- 候補者側の不安と躊躇: 求職者はスタートアップに対して「社風になじめるか」「給与が下がるのでは」「激務でついていけるか」などの不安を抱き、応募をためらうことが多いです。特に日本では、大企業に勤めるのが一般的なキャリアパスとされ、スタートアップに対するリスクのイメージが強いです。働き方改善や処遇向上が進んでいるものの、不安を解消できないと応募には至りません。
以上のような理由から、スタートアップの採用は一筋縄ではいかないのです。
スタートアップ採用を成功に導く!具体的な戦略と対策
スタートアップが採用競争を勝ち抜くためには、課題を踏まえた上での具体的な戦略と施策が必要です。
ここでは前項の課題解決に役立つ実践的な対策を紹介します。
- 採用ブランディング(採用広報)の強化: スタートアップ採用成功のためには、企業のミッションや文化を積極的に発信し、企業認知度を高めることが重要です。SNSやブログを活用し、社員のストーリーや価値観を伝えることで、共感を呼び、応募者の増加や母集団形成を促進します。
- 候補者体験(CX)の向上: スタートアップが採用で差別化を図るには、候補者体験(CX)を重視することが鍵です。選考プロセスをスムーズかつ魅力的にし、候補者が「この会社で働きたい」と感じるように工夫しましょう。具体的には、迅速なレスポンス、柔軟な面接日程調整、会社のビジョンや魅力を伝える時間を設けることが有効です。カジュアル面談やオフィス訪問を通じて、リラックスした雰囲気で相互理解を深めることも効果的です。
- スピード採用と柔軟なオファー: 優秀な人材を逃さないためには、スピード感のある採用プロセスが重要です。スタートアップは意思決定を迅速に行い、選考回数を絞って短期間で内定を出すことが求められます。また、オファー内容も柔軟に検討し、金銭以外の魅力(ストックオプション、役職登用、リモートワークなど)を提示することで候補者の心をつかみ、条件差を埋めることが可能です。
- 社員を巻き込んだ採用(スクラム採用)の推進: スタートアップでの採用成功には、社員全員を巻き込んだ「スクラム採用」が重要です。人事だけでなく現場社員にも採用活動に参加してもらい、リファラル採用や面接官、会社説明などを担ってもらうことで、採用チームを拡大します。
- 多様な採用チャネルの活用: スタートアップでの採用成功には、多様な採用チャネルの活用が不可欠です。ターゲットを明確にし、採用広報を強化することで、ダイレクトリクルーティング、リファラル、SNS採用などの手法を組み合わせて、成長意欲が高い柔軟な人材を惹きつけます。自社のフェーズや職種に応じて、有効なチャネルを選び、戦略的に運用することが重要です。
- 採用データの活用と改善サイクル: スタートアップの採用活動では、データ分析と改善サイクルを活用することが重要です。応募経路ごとの通過率や内定率、選考期間などをトラッキングし、優秀な人材を獲得できているチャネルや選考プロセスの改善点を把握します。状況に応じてチャネルの強化や改善を行い、PDCAサイクルを高速で回しながら、採用活動を常にアップデートすることで、自社に合った採用パターンを築くことができます。
以上のような戦略・施策を組み合わせて実行することで、スタートアップ採用の成功率は確実に高まります。
たとえば「まずは採用広報に注力して応募数を増やす」「直近はエンジニア1名確保が急務なのでリファラルとダイレクトを総動員する」といった具合に段階的に進めると良いでしょう。
【手法別】スタートアップにおすすめの採用チャネルと活用法
スタートアップ採用を成功させるには、適切な採用チャネルを選び活用することが極めて重要です。
ここではスタートアップ人事におすすめの主な採用チャネルと、その特徴・活用ポイントを紹介します。
ダイレクトリクルーティング(直接スカウト)
自社から候補者に直接アプローチするダイレクトリクルーティングは、スタートアップにとって最も有効な手法の一つです。
求人を出して待つだけでは出会えない「転職潜在層」にもアプローチできる点が大きな強みです。
ある調査では「今すぐ転職意向はないが良い話があれば転職を考える」という層が市場の約80%存在するとの結果もあります。
この層に積極的に働きかけられるダイレクトリクルーティングは、母集団拡大に欠かせません。具体的にはビズリーチやLinkedInなどのデータベースで条件に合う人材を検索し、メッセージを送る方法が一般的です。
一方的な自社アピールだけでは良い反応は得られにくいので注意しましょう。
ダイレクトスカウトは手間はかかりますが、ターゲットを絞って効率良くアプローチできるうえ、成功すれば即戦力の獲得につながるリターンの大きい手法です。
リファラル採用(社員紹介)
リファラル採用は、社員の知人・友人などに会社を紹介してもらい応募につなげる手法です。
コストがほとんどかからず手軽に始められるうえ、候補者の人柄やスキルも事前に把握しやすいため、創業初期の採用には特に有効です。
スタートアップのように選考体制が整っていない場合でも、社員が保証人となる形で安心して採用を進めやすい利点があります。
一方でデメリットとしては偶発性に左右される点があります。
紹介してもらえる人材の数には限りがあり、たまたま良い人が見つかるかどうか運の要素もあります。
まずは全社員にリファラル採用の意義を説明し協力を仰ぐことから始め、リファラルで入社した社員にインセンティブを支給する制度を設ける企業もあります。
また候補者側から見ても「知人が働いているから安心」という心理的ハードルの低さがあるため、うまくいけば入社後の定着率も高まりやすい傾向にあります。
創業メンバーのネットワークを活用して優秀層を紹介してもらい、まず核となる人材を揃えるのに適した手法と言えるでしょう。
SNS採用(ソーシャルリクルーティング)
TwitterやFacebook、LinkedIn、そして日本発のキャリアSNS「YOUTRUST」など、SNSを活用した採用もスタートアップとの親和性が高い手法です。
SNS発信による情報拡散力を使って採用広報することで、低コストながら幅広い層にリーチできる点が魅力です。
特にエンジニア界隈ではTwitterやQiita、GitHubといったコミュニティでのつながりから採用に発展するケースも多々あります。
SNS採用のメリットは、会社のリアルな姿を伝えられることです。
日々の投稿や社員の発信を通じて社風やプロダクトへの想いが伝われば、応募前に候補者の自社理解が深まり、入社後のミスマッチ防止にもつながります。
注意点として、SNS運用は継続的な発信が必要で手間がかかること、拡散力ゆえに発信内容には十分気を配る必要があることが挙げられます。
とはいえ工夫次第で採用目的の投稿がバズり、思いがけない優秀層から問い合わせが来ることもあります。
社員にブログ執筆や登壇を促しそれをSNSで共有する、採用担当自ら会社や求人の魅力を発信するなど、「中の人」の熱意が伝わる情報発信でファンを増やす気持ちで取り組みましょう。
実績として、ある調査ではベンチャー企業の中途採用でYOUTRUSTなどキャリアSNS経由の内定数が増加傾向にあるとの報告もあります。
求人サイト・エージェントの活用
転職求人サイト(求人媒体)や人材エージェントの活用も、スタートアップの状況によっては有効なチャネルです。
特に即戦力の中途採用で母集団を広げたい場合、主要な転職サービスに求人を掲載することで一定数の候補者集客が見込めます。
加えて、年収やスキルでフィルタし直接スカウトもできるビズリーチはスタートアップにも導入企業が多く、ある調査ではベンチャー企業の72.9%がビズリーチを活用し、内定実績も最多との結果が出ています。
Wantedly(後述)も含め、複数の媒体を組み合わせて露出を増やすのが一般的です。
また、人材エージェント(人材紹介会社)に依頼すると、希望条件に合った候補者を紹介してもらえます。
エージェント経由は成功報酬型でコストは高めですが、自社ではリーチできない優秀層(特にマネジメントクラス)を獲得できる可能性があります。
スタートアップが求人媒体やエージェントを使う際のポイントは、求人票の書き方です。
大企業のように社名や知名度で興味を引けない分、求人タイトルや紹介文でいかに魅力を伝えるかが勝負になります。
オウンドメディア・採用サイト(Wantedlyなど)の活用
自社で運営するブログや採用サイトといったオウンドメディアも、スタートアップの採用力強化に役立つチャネルです。
自社メディアであれば詳細かつ多様な情報を自由に発信でき、会社の世界観に共感するファン層を育てることができます。
例えば技術ブログでプロダクトへのこだわりを書く、人事ブログでカルチャーや社員インタビューを掲載するといった形でコンテンツを蓄積すれば、SEO経由での流入増加や志望度向上にもつながります。
しかし本格的なメディア立ち上げには時間と労力がかかるため、ハードルが高い場合はWantedlyのようなサービスを活用する手もあります。
Wantedlyは求人情報とブログ的コンテンツを合わせて発信できるプラットフォームで、テンプレートに沿って入力するだけでモダンな採用ページが作成可能です。
しかも作成したページは高確率でGoogle検索の1ページ目に表示される仕様になっており、SEO対策としても有効です。
オウンドメディアはいわば長期的な採用資産です。
一朝一夕で成果は出にくいものの、継続すれば応募数・質の向上や採用コスト削減に大きく寄与します。
自社で運営するか外部サービスを使うかは状況によりますが、「会社のストーリーを伝える場」を持つことをぜひ検討しましょう。
インターン・新卒採用の活用
即戦力の中途採用に注力しがちなスタートアップですが、長期インターンや新卒採用にも目を向けると将来の人材確保につながります。
長期インターンに参加する学生はキャリア意識が高く、前述の「スタートアップが採用すべき人材」に当てはまる成長意欲旺盛な層が多い傾向があります。
インターンを経てそのまま新卒入社してもらえれば、お互いに働き方や適性を確認済みの状態でミスマッチなく戦力化できます。
実際に数ヶ月の実務を通じて人柄や能力を見極められるため、書類と面接だけの新卒採用よりも定着率が高まるメリットがあります。
スタートアップにとって新卒育成はハードルが高いと思われがちですが、将来のコア人材を早期に囲い込めるチャンスでもあります。
インターン受け入れの体制がない場合は、まずは週数日からでも学生に実務を手伝ってもらい、優秀でフィットする人がいれば正式にオファーする流れを作ってみましょう。
「学生とはいえ即戦力級」の人材に出会える可能性もあり、市場が取り合う前に自社の仲間にできれば大きな戦力となります。
以上、スタートアップに適した主要な採用チャネルを紹介しました。
ポイントは複数チャネルを組み合わせ、相乗効果を狙うことです。
例えば、自社ブログで社員の熱量を伝えつつ、その内容をSNSで拡散し、興味を持った人にダイレクトスカウトを送る――このように一貫したメッセージで様々な経路からアプローチするのが理想です。
また、どのチャネルが自社にとって成果が出やすいかはトライ&エラーで見極める必要があります。
定期的に分析し、リソース配分を調整しながら最適なチャネル運用を探っていきましょう。
スタートアップは市場価値を高めるチャンス?スキルアップとキャリアの視点
最後に視点を変えて「スタートアップで働くことは個人の市場価値を高めるのか?」というテーマを考えてみます。
この点を理解することは、人事担当者が候補者にスタートアップで働く意義を伝える上でも役立ちます。
結論から言えば、スタートアップでの経験は個人の市場価値を大いに高め得ると言えます。
スタートアップ転職を希望する人の最大の理由は「自分の市場価値を上げたい」ことです。
実際、スタートアップで得たスキルや実績を武器に、大手企業への再転職や独立起業など次のキャリアで飛躍する人は数多くいます。
新規事業の立ち上げに携わったり、マネージャー級の役割を若くして経験したりすることで、ビジネスパーソンとしての厚みが増すでしょう。
スタートアップでは仕事の実力が重視されるため意欲と能力があれば早期に上流ポジションに就けます。
その経験自体が市場で評価される貴重なものとなり、結果として自身の市場価値向上に直結します。
また、スタートアップ経験者は不確実性下での問題解決力や主体性が養われているため、変化の激しい現代のビジネス環境において引く手数多です。
「名の通った企業にいた」という肩書き以上に、「何を成し遂げたか」「どんな価値を生み出したか」が重視される時代において、スタートアップでの濃密な経験は強力なアピール材料になります。
さらに、スタートアップで働くことで形成される人的ネットワークも無視できません。
志の高い経営者や優秀なメンバーと切磋琢磨した人材は、業界内で評価が高まります。
同じ志を持つ仲間との繋がりから新たなチャンスが生まれることもあります。
もちろん、市場価値の向上は本人の努力次第な部分もあります。
スタートアップで与えられる機会を生かしきれるか、自己研鑽を怠らないかといった姿勢が重要です。
スタートアップに飛び込めば自動的に市場価値が上がるわけではありません。
しかし、意欲的な人にとってスタートアップは自己成長の機会に溢れた環境であり、その経験は次のキャリアで大いに糧となるでしょう。
人事担当者はこの「市場価値が高まる」という点を、採用時の訴求材料として活用できます。
「当社で〇〇の立ち上げを任された経験はあなたのキャリアにとって貴重なものになる」「大企業では得られない成長機会がある」といったメッセージは、成長意欲の高い候補者の心に響くはずです。
スタートアップ経験を経て大手への転職や起業に繋げたケースも多いと伝えれば、将来の選択肢が広がる魅力的なキャリアステップだと感じてもらえるでしょう。
まとめ
スタートアップの採用は確かに難易度が高いですが、本記事で述べたように課題を正しく認識し戦略的に取り組めば、十分に成功可能です。
人事担当者はスタートアップ特有の魅力と課題を理解し、自社の強みを最大限に打ち出しながら、多様なチャネルと施策を駆使して人材獲得に挑んでください。
「スタートアップ採用戦略」の実践により、優秀な仲間を迎え入れて組織を成長軌道に乗せることを願っています。

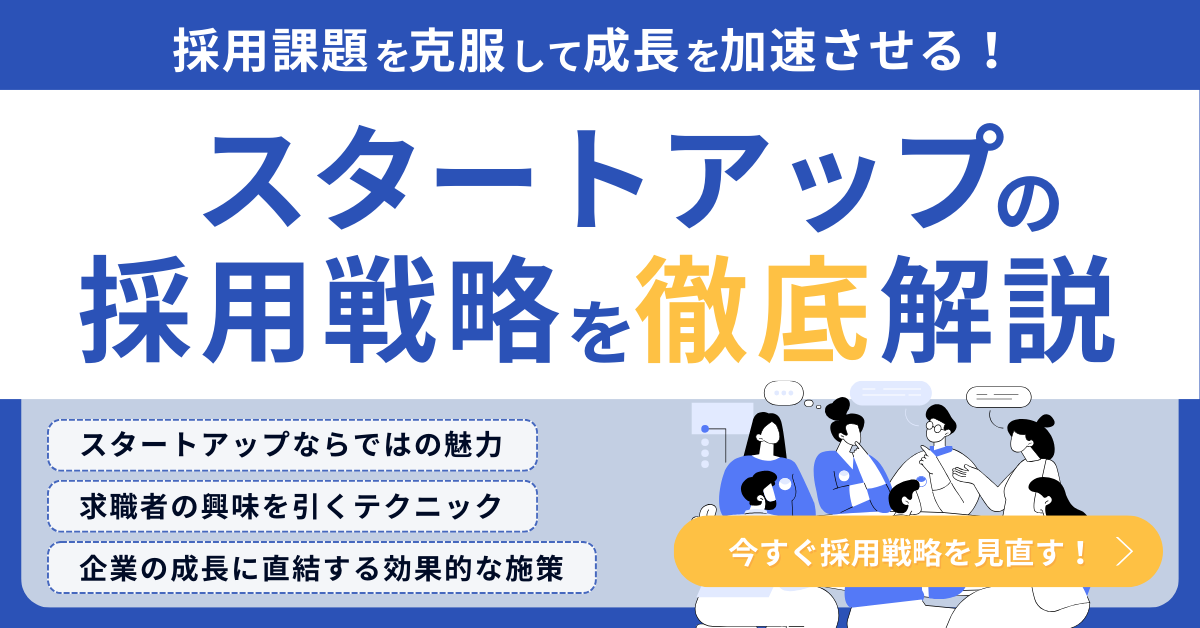
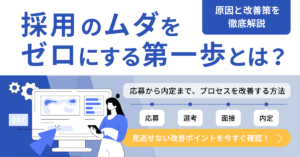






とは?メリット・デメリットや導入ポイントを徹底解説-300x157.png)
コメント